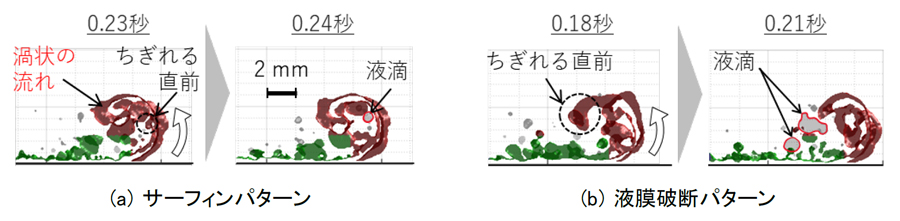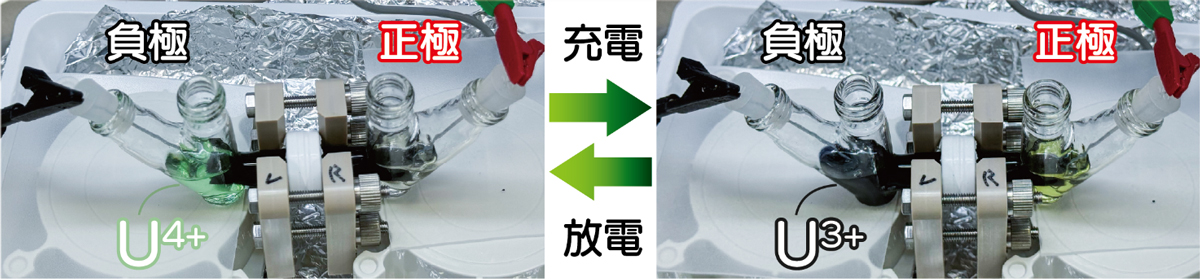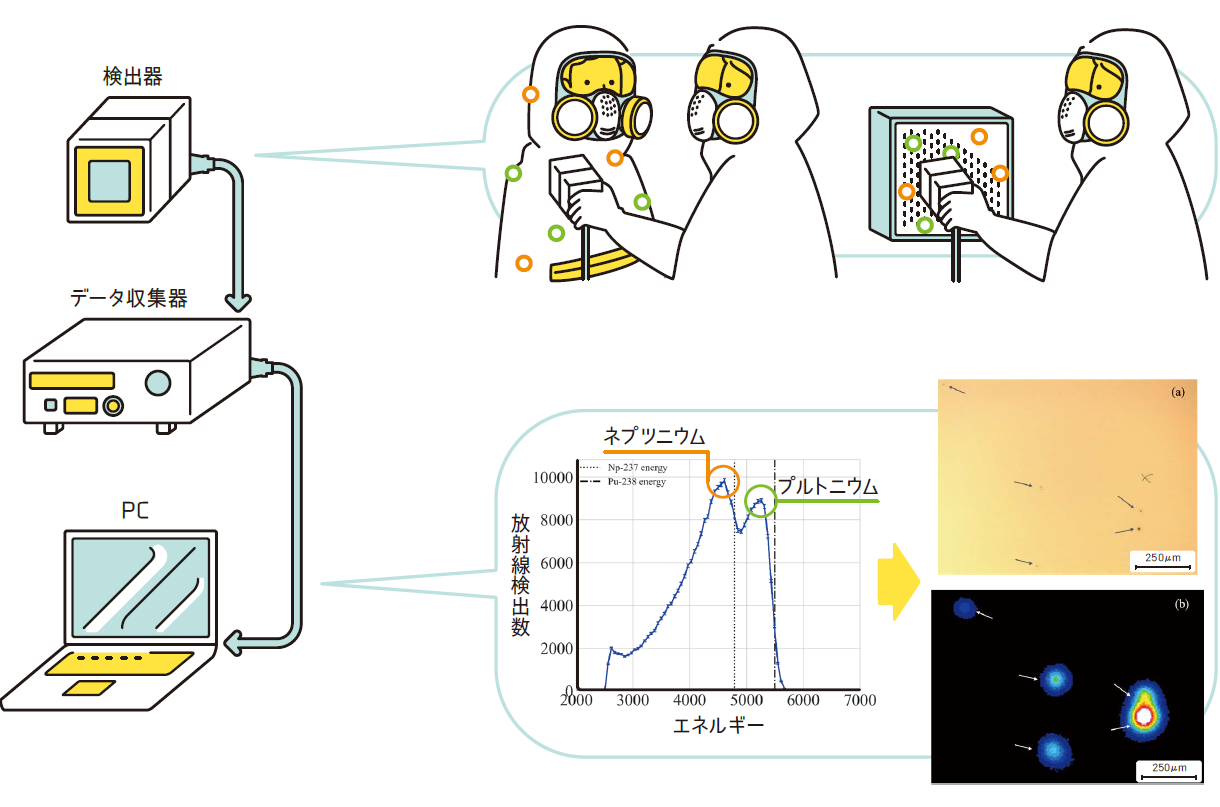学術会議 原子力災害対策に向けSPEEDIの活用を提言
03 Oct 2023
日本学術会議の地球惑星科学委員会(委員長=田近英一・東京大学大学院理学系研究科教授)は9月26日、より強靭な原子力災害対策に向け「放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべき」との見解を発表した。
見解では、福島第一原子力発電所事故の発生直後、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)[1] … Continue readingの情報が住民避難などの防護措置に活用できなかったことをあらためて指摘。事故を教訓として、「放射性物質の拡散に伴う災害を軽減・回避する手立てについて、国、原子力規制委員会、自治体、科学者コミュニティは、様々な取組を通して模索してきたが、解決への道のりが見出せたとは言いがたい」と、SPEEDIを有効活用する必要性を示唆している。
その上で、「国民の安全を確保するためには、放射性物質の拡散に関するあらゆる科学情報を収集し、防護措置の判断に活用することが必要不可欠」と強調。アカデミアとして、
- 放射性物質の拡散に対して国民の安全を確保するための防護策は、モニタリングデータだけでなく、数値シミュレーションによる予測から得られる科学的な情報と知見を最大限に活用して策定
- 規制委員会は現行の「原子力災害対策指針」を改訂し、拡散予測情報の活用指針を統一し、責任の所在を明らかにした上で、最適な防護策を策定・施行
- 規制委員会は科学者・専門家の能力を最大限に活用
- 国、規制委員会、自治体、科学者コミュニティ、市民は互いに協力し、市民の視点から防護策を策定し、緊急時に確実に運用するため準備
――すること、と提言している。
規制委員会では、2012年の発足以降、事故の教訓を踏まえ、「原子力災害対策指針」および、これに付随するマニュアル・ガイドラインの見直しを進めてきたが、気象予測の不確かさから、緊急時における避難など、防護措置の判断に当たって、SPEEDIによる計算結果は使用しないこととしている。一方で、原子力施設の立地地域からは、複合災害を見据え、SPEEDIの有効活用を求める声もあがっていた。SPEEDIは、放射性物質の拡散予測だけでなく、2000年の三宅島噴火時に、火山性ガスの分析にも活用できることが検証されている。日本原子力研究開発機構でSPEEDIの開発に長く取り組んできた茅野政道氏(現在、量子科学技術研究開発機構理事)は、福島第一原子力発電所事故後、国外事故時や緊急時海洋モニタリングに備え、世界版SPEEDI、SPEEDI海洋版の開発も提唱してきた。
脚注
| ↑1 | 原子力施設から大量の放射性物質が放出された場合や、その恐れがある事態に、周辺環境における放射性物質の大気中濃度、および被ばく線量等の環境影響を、放出源情報、気象条件、地形データをもとに迅速に予測するシステム |
|---|