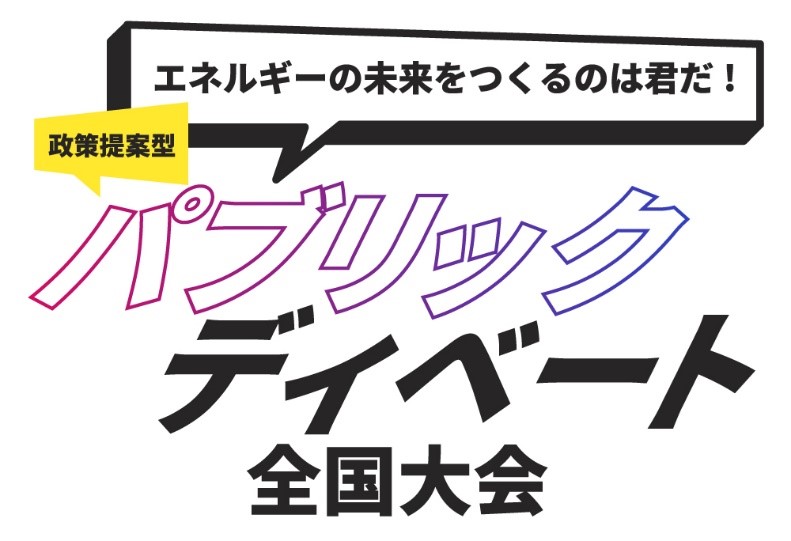三村会長が「エネ基への新設明記」を 新理事長に増井氏
19 Jun 2024
日本原子力産業協会は6月18日、定時社員総会を日本工業倶楽部(東京・千代田区)で開催し、2023年度決算および事業計画、2024年度の事業計画・予算案がそれぞれ承認、報告された。また、理事8名の改選を承認。総会終了後の理事会で、東原敏昭氏(日立製作所会長)が副会長に、増井秀企氏(東京電力原子力・立地本部副本部長)が理事長に就任することが決定された。
総会の冒頭、三村明夫会長は、「原子力は優れた安定供給性と経済効率性を有しており、運転コストが低廉・安定な準国産の脱炭素電源であることから、長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する、重要なベースロード電源」と強調。現在、検討が進められている次期エネルギー基本計画策定に向けては、「原子力の持続的かつ最大限の活用、ならびに早期の新規建設開始を明記するべき」とした。その上で、「産業界の声」として、
- 既設炉の最大限の活用
- 原子力サプライチェーンの維持・強化
- 新規建設の投資判断を可能とするための事業環境整備
- 国民理解の促進
――の4点をあげ、既設炉の活用に関しては、再稼働の他、長期サイクル運転の導入、運転中保全の導入拡大、既設炉の出力向上など、設備利用率の向上に言及。新規建設に向けては、電力の事業予見可能性の著しい低下を懸念し、「投資回収面および資金調達面での課題に対処し、約20年にも及ぶ建設リードタイムを踏まえた適切な時期に事業者が投資判断できる事業環境整備が必要」と訴えた。核燃料サイクル事業をめぐっては現在、六ヶ所再処理工場の年内しゅん工が見込まれ、高レベル放射性廃棄物の地層処分地選定に向けた文献調査が佐賀県玄海町で開始されている。三村会長は、日本原燃の再処理工場・MOX燃料工場について「サイクルの要」との認識をあらためて述べ、しゅん工への取組を着実に進め、バックエンドに関しても「国・原子力発電環境整備機構(NUMO)と密接に連携していく」と、原子力産業界として着実に支えていく姿勢を示した。〈挨拶文は こちら〉
来賓として訪れた齋藤健経済産業相は挨拶の中で、日本のエネルギー情勢をめぐり、化石燃料の輸入に伴う国富流出など、昨今の状況から、「戦後最大の難所を迎えている」との危機感を示した上で、エネルギー安定供給とGXの両立を実現するため、「原子力の活用が不可欠」と強調。一方で、「福島第一原子力発電所事故の反省を一時も忘れることなく、高い緊張感を持って安全最優先で万全を期すこと」をあらためて述べた上で、原子力産業界との連携に関し、サプライチェーンの維持・強化、人材育成、国際競争力の強化、事業環境整備などの課題を列挙。5月に開始した次期エネルギー基本計画策定の関連では、将来的な電力需要の増大、それに伴う大規模な脱炭素電源投資の必要性に鑑み、今後、「政府のみならず、電力・産業、金融など、官民の様々なプレイヤーが危機感を共有し、それぞれの役割を果たしていくことが重要」と、訴えかけた。続いて、本田顕子・文部科学政務官が挨拶。研究開発・人づくりを担う立場から、日本原子力研究開発機構の「JRR-3」や「常陽」の活用とともに、現在、作業部会で検討が進められる「もんじゅ」跡地の試験研究炉設置にも期待を寄せ、産業界による理解・支援を求めた。
新任の増井理事長は、19日に就任挨拶を発表。その中で「稼働する原子力発電プラントは12基と、現存する33基の約3分の1にとどまっている」と、原子力発電をめぐる現状を懸念。次期エネルギー基本計画の策定に向け、原産協会として、「IT需要や脱炭素化の進展で増加すると予想される電力需要に応えるため、既存プラントの再稼働はもとより、リプレースや新増設の必要性の明記、そしてそれらを実現するために必要な事業環境の整備について明示してもらうよう求めていきたい」と強調した。