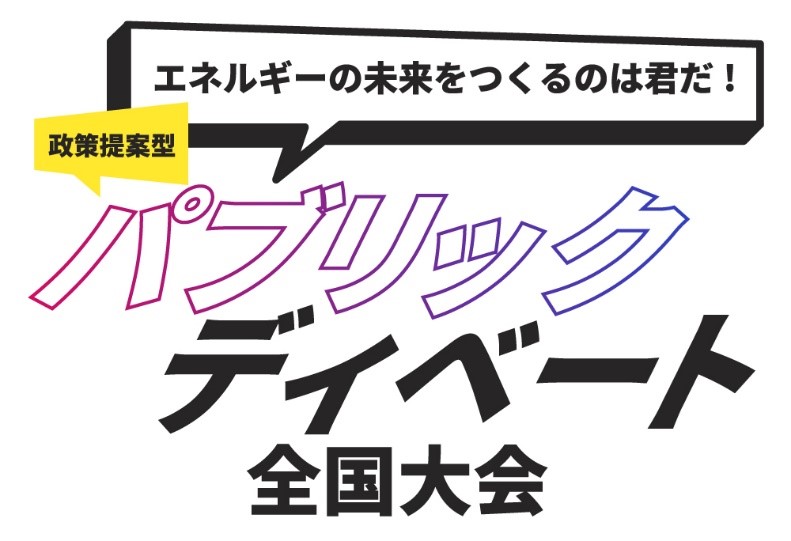「原子力サプライチェーンシンポジウム」でパネル討論
24 Mar 2025
原子力サプライチェーンの維持・強化策について議論する「原子力サプライチェーンシンポジウム」(第3回)が3月10日、都内ホールで開催された。経済産業省資源エネルギー庁が主催し、日本原子力産業協会が共催した。
武藤容治経産相の開会挨拶(ビデオメッセージ)、資源エネルギー庁の村瀬佳史長官の基調講演などに続き、「サプライチェーン強化に向けた取組」と題しパネルセッション(ファシリテータ=近藤寛子氏〈マトリクスK代表〉)が行われた。
パネルセッションの前半では、三菱重工業、東芝エネルギーシステムズが、革新型軽水炉として、それぞれ取り組む「SRZ-1200」、「iBR」の開発状況を紹介。サプライチェーンとしては、岡野バルブ製造が自社の取組について発表。同社は、高温高圧バルブを90年以上製造している実績を活かし、2023年より次世代革新炉向けのバルブ開発に取り組んでいるという。
パネルセッションの後半では、三菱総合研究所と日本製鋼所M&E、日立GEと四国電力がペアとなって発表し議論。それぞれ、次世代炉建設に必要な人材維持に向けた「技能者育成講座」、原子力発電所におけるAI活用の取組について紹介した。
これを受け、原産協会の増井秀企理事長は、ものづくりにおける人材確保の重要性をあらためて強調。原産協会が行う就活イベント「原子力産業セミナー」など、学生・次世代層への働きかけを通じ、「多様な人材確保につながれば」と期待した上で、「情報に触れて自分の頭で考える機会を与える」ことの意義も述べた。また、「サプライチェーンの課題を解決するためには、産官学の緊密な連携が必要」とも指摘。引き続き広報・情報発信に努めていく姿勢を示した。増井理事長は、プレゼンの中でリクルートワークス社による労働需給シミュレーションを紹介し、「2040年に1,100万人の働き手不足が生じる」と危惧し、将来的に「人口減・仕事増の矛盾解消策、総合的な対策が必要」と指摘。同シミュレーションによると、2040年の労働人口不足率は、地域別に、東京都はマイナス8.8%と供給過剰の見通しだが、原子力発電所の立地道府県では、新潟県が34.4%と全国的に最も厳しく、女性の就業率が高いとされる島根県では0.9%と、地域間のギャップが顕著となっている。
同シンポジウムの初開催(2023年3月)に合わせ設立された「原子力サプライチェーンプラットフォーム」(NSCP)の会員企業は現在、約200社に上っている。パネルセッションの前半と後半の合間に、NSCP参画企業約20社によるポスターセッションが行われた。
パネルセッションの締めくくりに際し、行政の立場から、文部科学省原子力課長の有林浩二氏がコメント。業種の枠を越え交流が図られたポスターセッションについては「いかに企業が若い人材を確保することが大変か」との見方を示した上、北海道大学で制作・公開が始まっている誰もが利用可能なオンライン型「オープン教材」の企業内教育における活用などを提案。また、資源エネルギー庁原子力政策課長の吉瀬周作氏は、国際展開の見通しにも言及し「若者に未来を示すことが出発点」、「しっかりと次世代にバトンをつないでいくことが必要」、「新たなチャレンジを」と所感を述べ、産官学のさらなる連携強化の必要性を示唆した。
なお、電気業連合会の林欣吾会長は、3月14日の定例記者会見で、今回のシンポジウムに関し、先に決定されたエネルギー基本計画にも鑑み「サプライチェーンの維持には、事業予見性の向上はもとより、技術・人材を維持する観点から、国が具体的な開発・建設目標量を掲げることが重要だと考えている」とコメント。さらに、「将来にわたり持続的に原子力を活用していくには、いずれ新増設も必要になると考えている」とも述べている。