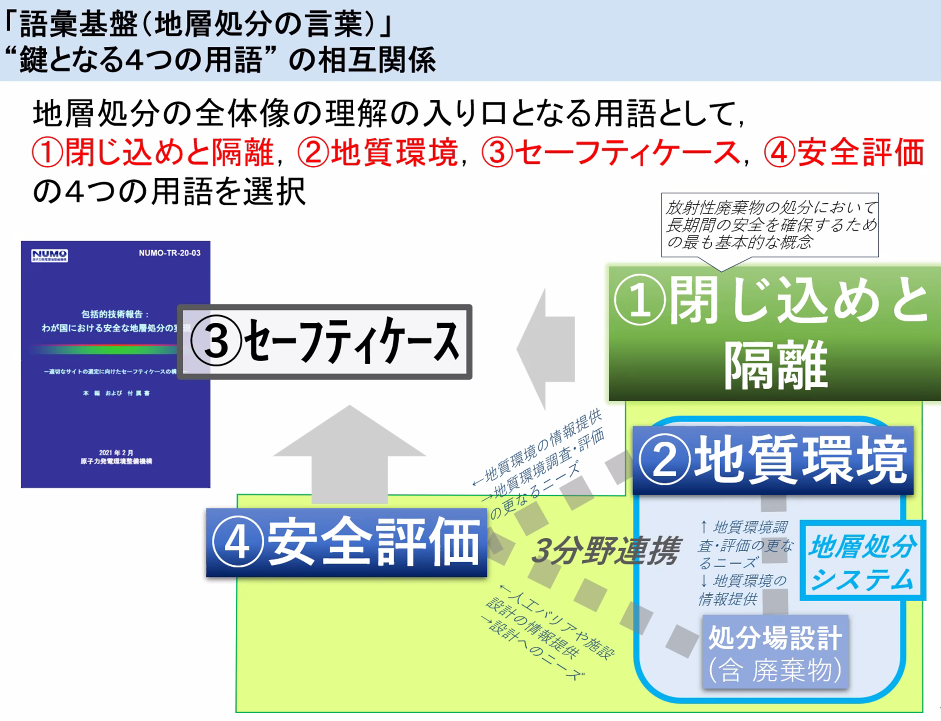学術会議・安全工学シンポ、リスク学の視点で集中議論も
07 Jul 2022
日本学術会議主催の「安全工学シンポジウム」が6月29日~7月1日、オンラインで開催された。同シンポジウムは、関連学協会の共催により、毎年、「国民安全の日」(7月1日)の時期に行われているもの。
シンポジウム初日の6月29日には、パネルディスカッション「リスク学の歴史・展開・社会実装」を実施。リスク概念の変遷をたどりつつ、リスク評価、リスクコミュニケーションのあり方などを巡り意見が交わされ、3日間にわたる工学各分野の安全に係る議論に先鞭をつけた。
同パネルで座長を務めた岸本充生氏(大阪大学データビリティフロンティア機構教授)によると、1950年代に国際放射線防護委員会(ICRP)がリスク概念を導入し、原爆被爆生存者の疫学調査に基づく発がんリスクの定量化を実施。60年代からは英国や米国で原子力発電所を対象とした確率論的リスク評価(PRA)の手法開発が進められ、70年代からは健康リスク分野、特に発がんに係る定量的なリスク評価手法が導入され始め、「1960~90年代にリスク学が興隆した」という。自然災害の甚大化やテロの脅威など、昨今、リスク概念は一層多様化しており、同氏は、「リスク学の歴史は『守りたいもの』、『脅かすもの』の拡大の歴史だ」と説いた。
また、リスク評価に関連し、米田稔氏(京都大学大学院工学研究科教授)は、「リスク比較の重要性を行政や市民が認識した」事例を2つ紹介。一つは、新型コロナのワクチン接種に関し、「接種した場合の副作用リスク」と「接種しない場合の感染リスク」を比較したというもので、東京都の2回目ワクチン接種率(2022年6月時点)が50歳以上で90%だったのに対し、40歳代以下では80%前後だったことから、「若い世代は高齢の世代に比べ、感染リスクよりも副作用リスクの方を大きく認識したのでは」と推察。もう一つは、コロナ拡大下、洪水による避難勧告(法改正により現在は「避難指示」に一本化されている)を受け、住民が「自宅に留まることによる被災リスク」と「避難所における感染リスク」を比較し行動したというもの。こうした事例を通じ、米田氏は、死亡リスク、生活の質低下のリスク、災害リスク、経済的リスクなど、トレードオフ関係ともなる「異なる価値」に基づくリスク比較が必要だとした。
これに対し、岸本氏は、夏季の学校における生徒のコロナ対策と熱中症対策のトレードオフ関係を例に、「リスクの定量的評価が難しい」とした上で、ステークホルダーである保護者や地域の人たちの話をまず聞くなど、「意思決定のプロセス」の重要性を繰り返し強調。化学物質のリスク管理を専門とし基準値の設定に関する著書を持つ小野恭子氏(産業技術総合研究所安全科学研究部門主任研究員)は、「ALARA」(As Low As Reasonably Achievable:合理的に達成可能な程度に低いならば許容しうるリスク)の考え方に言及し、「他分野の事例を広く知ることも重要」と指摘した。
高レベル放射性廃棄物の処分地選定に向けて文献調査が進む寿都町で「対話の場」のファシリテーターを務める竹田宜人氏(北海道大学大学院工学研究院客員教授)も登壇し、リスクコミュニケーションのあり方について発表。福島第一原子力発電所事故発災時の被災地の状況を振り返り、「『毎日の生活が大事と思っている人』、『将来世代の健康影響が大事と思っている人』、それぞれ持っている価値観は皆違い、どうしても定量的な比較はできない」とした上で、「意思決定に係るプロセスの大事さを理解できる社会」を構築する重要性を主張。同氏がナッジ(チラシ配布や映像などを通じて人の感情に働きかけ“何となく”行動を促す行動科学の手法)の有効性を提案したのに対し、「一つの価値観を指向した説得のための手段」に凝り固まってしまうことを危惧する意見も出された。
討論を受け、これまでも「リスク共生社会の構築」を標榜し意見を述べてきた野口和彦氏(横浜国立大学リスク共生社会創造センター客員教授)がコメント。同氏は、「人間社会はそれぞれの価値観で動いているので整合させることが難しい。これを前提に、意思決定をするため、どのようなリスクを考えておけばよいのか、整理しておくことが重要」と述べた。