【第56回原産年次大会】2050年を見据えた原子力技術
24 Apr 2023
「第56回原産年次大会」では2日目の4月19日、セッション4「原子力の最大限活用とその進化―2050年を見据えて」が行われた。
黒﨑健氏(京都大学複合原子力科学研究所所長・教授)をモデレーターに、パネリストとして、神﨑寛氏(三菱重工業原子力セグメント原子力技術部部長)、姉川尚史氏(東京電力ホールディングフェロー)、大島宏之氏(日本原子力研究開発機構理事)、ミカル・ボー氏(英国 CORE POWER社創設者、会長兼CEO)、曽根理嗣氏(宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所准教授)が登壇。セッション開始に際し、黒﨑氏は、「原子力は発電分野にとどまらず、様々な社会・経済活動と脱炭素化に貢献できる技術だ。2050年の姿を見据え、原子力のポテンシャルや多様な利用形態に焦点を当て、原子力利用の幅を広げ深化させていくための示唆を得たい」とねらいを述べた。
 同セッションには原子力分野に関心を持つ学生ら約50人も訪れ聴講。総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループで座長を務めている黒﨑氏は、「革新炉開発をきっかけに原子力イノベーションを実現していきたい」と強調するとともに、「原子力の新しい価値の創造」、「最先端分野・異分野との融合」、「人を呼び込む・若者にとって魅力ある原子力」をキーワードに掲げ、口火を切った。
同セッションには原子力分野に関心を持つ学生ら約50人も訪れ聴講。総合資源エネルギー調査会の革新炉ワーキンググループで座長を務めている黒﨑氏は、「革新炉開発をきっかけに原子力イノベーションを実現していきたい」と強調するとともに、「原子力の新しい価値の創造」、「最先端分野・異分野との融合」、「人を呼び込む・若者にとって魅力ある原子力」をキーワードに掲げ、口火を切った。
 日本における革新炉開発の取組については、神﨑氏が三菱重工の取り組む革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW、2030年代半ばの実用化が目標)のコンセプトを中心に説明。同氏は、「SRZ-1200」の他、小型軽水炉(電気出力30万kW)、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉(離島・へき地・災害地用の電源に利用できるポータブル炉)からなる同社の「革新炉ラインナップ」を披露した上で、参集した学生たちに対し「色々な技術、オポチュニティがある。是非挑戦し社会に貢献して欲しい」と呼びかけた。
日本における革新炉開発の取組については、神﨑氏が三菱重工の取り組む革新軽水炉「SRZ-1200」(電気出力120万kW、2030年代半ばの実用化が目標)のコンセプトを中心に説明。同氏は、「SRZ-1200」の他、小型軽水炉(電気出力30万kW)、高温ガス炉、高速炉、マイクロ炉(離島・へき地・災害地用の電源に利用できるポータブル炉)からなる同社の「革新炉ラインナップ」を披露した上で、参集した学生たちに対し「色々な技術、オポチュニティがある。是非挑戦し社会に貢献して欲しい」と呼びかけた。
 また、研究開発の立場から、大島氏は、社会実装に向けた次世代革新炉に求められる要件として、「一層の安全性向上」を前提に、「安定供給」(大規模で安定な脱炭素電源、革新的安全性向上、サプライチェーンの維持・強化や技術自給)、「資源循環性」(廃棄物問題の解決、資源の有効利用)、「柔軟性」(再エネを支える出力可変性、水素・熱利用、立地の柔軟性、医療用RI製造)を提示した上で、原子力機構が取り組む高温ガス炉、高速炉に係る技術開発について紹介。高速炉については、廃棄物減容・有害度低減の他、他産業からの廃熱も組み合わせ再生可能エネルギーと共存する新たなエネルギー供給システムの可能性を展望。「様々なチャレンジがある。われわれと一緒に開発を進めていければ」と、意欲ある学生たちの参入に期待を寄せた。
また、研究開発の立場から、大島氏は、社会実装に向けた次世代革新炉に求められる要件として、「一層の安全性向上」を前提に、「安定供給」(大規模で安定な脱炭素電源、革新的安全性向上、サプライチェーンの維持・強化や技術自給)、「資源循環性」(廃棄物問題の解決、資源の有効利用)、「柔軟性」(再エネを支える出力可変性、水素・熱利用、立地の柔軟性、医療用RI製造)を提示した上で、原子力機構が取り組む高温ガス炉、高速炉に係る技術開発について紹介。高速炉については、廃棄物減容・有害度低減の他、他産業からの廃熱も組み合わせ再生可能エネルギーと共存する新たなエネルギー供給システムの可能性を展望。「様々なチャレンジがある。われわれと一緒に開発を進めていければ」と、意欲ある学生たちの参入に期待を寄せた。
 他分野と連携した原子力開発・利用の可能性に関しては、姉川氏、ボー氏、曽根氏が発表。姉川氏は、造船関連企業も参画した「産業競争力懇談会」が検討を進めている浮体式原子力発電について紹介。海外の石油掘削などで実用化されている海上浮揚型プラントの技術を原子力発電にも応用するもので、沖合に係留することにより、津波の被害を避ける、海水を利用した除熱ができる、事故時の住民避難が不要となるといったメリットを持つとしている。同氏は、将来的に地震リスクの高い東南アジア諸国への導入も展望し、今後の基本設計・具体化に向けて、技術継承も合わせ原子力発電所の建設経験を持つ技術者OBと学生との共同作業を提案した。
他分野と連携した原子力開発・利用の可能性に関しては、姉川氏、ボー氏、曽根氏が発表。姉川氏は、造船関連企業も参画した「産業競争力懇談会」が検討を進めている浮体式原子力発電について紹介。海外の石油掘削などで実用化されている海上浮揚型プラントの技術を原子力発電にも応用するもので、沖合に係留することにより、津波の被害を避ける、海水を利用した除熱ができる、事故時の住民避難が不要となるといったメリットを持つとしている。同氏は、将来的に地震リスクの高い東南アジア諸国への導入も展望し、今後の基本設計・具体化に向けて、技術継承も合わせ原子力発電所の建設経験を持つ技術者OBと学生との共同作業を提案した。
 さらに、海上輸送の生産性向上に向けて新たな原子力技術開発に取り組むボー氏は、世界の船舶約10万隻のうち、主に大型船7,300隻が海上燃料の50%超を消費し、CO2や大気汚染物質を排出している現状を示し、船舶の動力源としてクリーンな燃料供給が可能な浮体式原子力発電を導入する意義を強調。その市場規模は6兆ドルにも上ると見込んだ。技術的な実現性として、同氏は、最長30年間の燃料交換不要、組立ラインでの製作可能性などから検討を行った結果、最適な炉型とされた「溶融塩高速炉」(MCFR)の米国アイダホ国立研究所での実証を2026年頃に目指しているとした。
さらに、海上輸送の生産性向上に向けて新たな原子力技術開発に取り組むボー氏は、世界の船舶約10万隻のうち、主に大型船7,300隻が海上燃料の50%超を消費し、CO2や大気汚染物質を排出している現状を示し、船舶の動力源としてクリーンな燃料供給が可能な浮体式原子力発電を導入する意義を強調。その市場規模は6兆ドルにも上ると見込んだ。技術的な実現性として、同氏は、最長30年間の燃料交換不要、組立ラインでの製作可能性などから検討を行った結果、最適な炉型とされた「溶融塩高速炉」(MCFR)の米国アイダホ国立研究所での実証を2026年頃に目指しているとした。
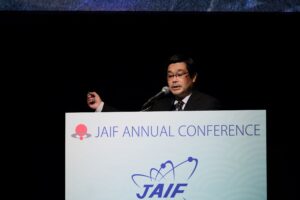 また、JAXAで宇宙用蓄電池の研究開発に従事してきた曽根氏はまず、小惑星探査機「はやぶさ」のカプセル回収の経験を披露。「惑星間往復航行が今の日本で可能な技術となった」とした上で、今後、さらに木星以遠への到達を目指す「深宇宙探査船団構想」の課題として、太陽光利用の限界をあげた。同氏は、宇宙の原子力電源として、崩壊熱利用と連鎖核分裂利用の2つをあげ、それぞれ探査機、拠点開発での適用を見込むとともに、ラジオアイソトープの利用が小電力稼働の探査機の設計に革命を起こす可能性に強く期待。原子力産業界への理解・協力を求めた。「宇宙の電池屋」を自称する曽根氏は、現在も深宇宙探査を展望し、セイル(帆)膜面上に搭載した薄膜太陽光電池で推進する「ソーラー電力セイル探査機システム」の開発に取り組んでいる。同氏は、かつて電池研究への志を周囲に否定された経験を振り返りながら、学生たちに対し「自分の目指すところに逆風が吹いていると思ったら、それはむしろチャンスだと思って欲しい」とエールを送った。
また、JAXAで宇宙用蓄電池の研究開発に従事してきた曽根氏はまず、小惑星探査機「はやぶさ」のカプセル回収の経験を披露。「惑星間往復航行が今の日本で可能な技術となった」とした上で、今後、さらに木星以遠への到達を目指す「深宇宙探査船団構想」の課題として、太陽光利用の限界をあげた。同氏は、宇宙の原子力電源として、崩壊熱利用と連鎖核分裂利用の2つをあげ、それぞれ探査機、拠点開発での適用を見込むとともに、ラジオアイソトープの利用が小電力稼働の探査機の設計に革命を起こす可能性に強く期待。原子力産業界への理解・協力を求めた。「宇宙の電池屋」を自称する曽根氏は、現在も深宇宙探査を展望し、セイル(帆)膜面上に搭載した薄膜太陽光電池で推進する「ソーラー電力セイル探査機システム」の開発に取り組んでいる。同氏は、かつて電池研究への志を周囲に否定された経験を振り返りながら、学生たちに対し「自分の目指すところに逆風が吹いていると思ったら、それはむしろチャンスだと思って欲しい」とエールを送った。









