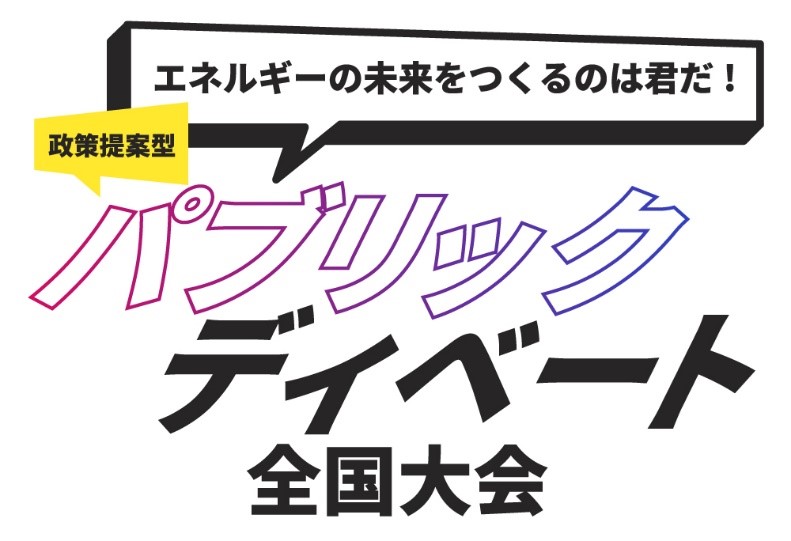日立 PRイベントを開催
22 Sep 2023
日立製作所は9月20、21日、顧客・ビジネスパートナーとの「協創に向けたきっかけ作りの場」とする日立グループのイベント「Hitachi Social Innovation Forum 2023 JAPAN」を、東京ビッグサイト(東京・江東区)で開催。4年ぶりの対面開催となった今回は、有識者を交えた討論、最新の技術開発の成果を紹介する展示など、60以上のセッション・ブースが設けられ、人気のコーナーには入場待ちの行列ができるほどの盛況ぶりだった。
21日に行われたセッション「脱炭素社会における原子力の役割」(モデレーター=間庭正弘氏〈電気新聞新聞部長〉)では、日立製作所原子力ビジネスユニットCEOの稲田康徳氏他、東京大学公共政策院特任教授の有馬純氏、脳科学者の中野信子氏が登壇。カーボンニュートラル実現に向けた原子力の果たす役割、人材確保・科学リテラシーに係る課題を巡り意見交換がなされた。
稲田氏は、エネルギーに由来するCO2排出量の各国比較データを示し、日本のエネルギー需給における脱炭素化の課題として、「化石由来の電源を減らすことが大変重要」と強調。さらに、東京大学との共同研究による試算から、今後のデジタル社会の発展に伴い「日本の電力需要は現在の1.5倍程度となる」可能性を示した。一方で、「天候の影響を大きく受ける再生可能エネルギーは、電力系統の安定性からも課題がある」と指摘。その上で、原子力発電のメリットについて、「運転時にCO2を排出しないという基本的価値に加え、天候の影響を受けず、昼夜を問わず大規模な電力を安定的に供給できる。ベースロード電源として最適」と述べた。日立の取り組む新型炉開発について、稲田氏は、米国GE日立と共同開発する電気出力30万kW級小型炉「BWRX-300」と、135~150万kWの大型炉「Hi-ABWR」(Highly innovative ABWR)を紹介。それぞれの技術的・経済的特長・開発スケジュールについて説明した。
科学技術行政に係る取材経験の豊富な間庭氏は、“Innovation”を切り口に原子力に対する人々の理解に関し問題提起。これに対し、脳科学・心理学で多くの著書を有する中野氏は、社会学的観点から、人々の「不安」に関しては、それを背景とする数多くの映画・小説が発表され「エンターテイメントにもなっている」とする一方、「安全」に関しては、「日常不可欠のことでまったくエンターテイメントになっていない」と述べ、「実際、エンターテイメントは人々の『不安』をもとに創られている」と指摘。さらに、「正しく怖がる」科学リテラシーの重要性について、昨今の新型コロナに係る情報流布にも言及し、「残念ながら十分とは言えない。現代社会を生きていくには不可欠のもの」と強調し、理科教育、教員の育成、いわゆる「大人の学び直し」の必要性などを訴えた。
また、間庭氏は、原子力産業のサプライチェーン維持・強化の観点から、人材育成の問題を提起。これに対し、高等教育の立場から有馬氏は、「日本の学生は講義を聴くだけで、人前で発言しない傾向にある。一方で、海外の学生は子供の頃から『議論しながら確かめていく』マインドが養われている」と、コミュニケーション能力の課題をまず指摘。さらに、稲田氏は、バーチャル空間やシミュレーションなど、デジタル技術を活用した技術伝承の取組を紹介したほか、海外プロジェクトへの参画を通じ若手に対する原子力技術への関心喚起を図っていく考えを示した。