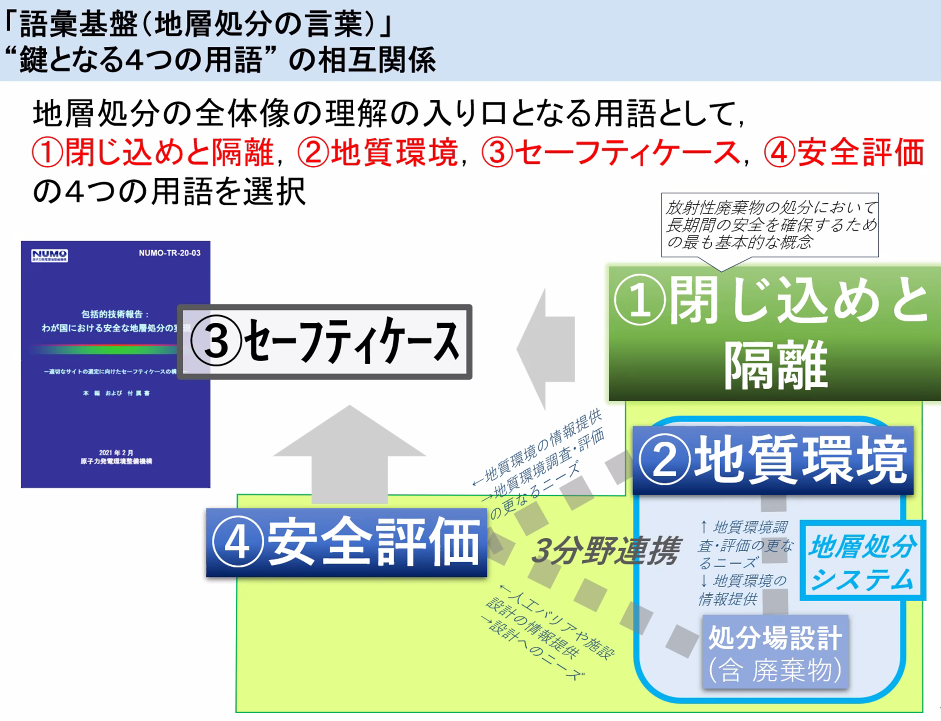原子力総合シンポ 「多様なステークホルダー」を巡り議論
02 Feb 2024
「原子力総合シンポジウム2023」が1月22日、日本学術会議本部講堂(東京都港区)で開催された。同シンポジウムは、日本学術会議の主催により、関連学協会の協力のもと、わが国の原子力を巡る諸課題について、社会と対話しながら総合的に討論する場として1963年より行われている。
今回のシンポジウムでは、総合討論に先立ち、橘川武郎氏(国際大学学長)、寿楽浩太氏(東京電機大学工学部教授)、山本章夫氏(名古屋大学大学院工学系研究科教授)、岡田往子氏(原子力委員)、山中伸介氏(原子力規制委員会委員長)が講演。橘川氏は元旦に発生した能登半島地震による影響を、寿楽氏は地層処分問題に関わった経験などを踏まえ、原子力を進めていく上での一般社会からの理解に関する問題を提起。岡田氏は原子力分野のジェンダーバランスについて講演し、「イノベーションは“個”を認め合ってこそ成しうるもの」と、多様性の重要さを強調。山中氏は、福島第一原子力発電所事故発生からの13年間を振り返り、原子力の安全規制を担う立場として、「制度改善には継続的に取り組んでいかねばならない」と、慢心に陥らぬよう、情報発信・対話、国際機関のレビューも通じた新知見の活用に努めている姿勢を述べ、議論に先鞭をつけた。
総合討論(コーディネーター=関村直人氏〈東京大学副学長〉)では、まず、日本原子力学会会長の新堀雄一氏(東北大学大学院工学系研究科教授)が、「エネルギーの選択肢としての原子力を巡る課題や社会の多様なステークホルダー」と題し論点を提起。
これに対し、産業界の立場から、東芝エネルギーシステムズの岩城智香子氏は、カーボンニュートラル実現に向けて革新技術への関心が高まる一方、既設炉の再稼働の遅れ、これに伴う技術維持・継承の困難さや人材流出、研究開発投資の縮小、大型試験施設の陳腐化といった課題を指摘した上で、「学会の役割は重要性を増している」と強調。また、革新軽水炉の研究開発に関わる名古屋大学大学院工学系研究科教授の山本章夫氏は、「技術的成熟度が社会に共有されていないのではないか」と、技術の実現性に係る「可視化」の必要性を問いかけた。
さらに、ステークホルダーの関与について、福島第一原子力発電所事故以降、学術会議で人文科学分野と横断的議論に関わっている国立環境研究所理事の森口祐一氏は、除染に伴う除去土壌の県外再生利用に向けた実証試験を例に、「首都圏の人たちも自分事としてとらえるとともに、科学者もステークホルダーの一員として考えるべき」と、今後のアカデミアの果たす役割を切望。また、会場からは、能登半島地震に伴いリスクマネジメントに係る課題が指摘されるとともに、「エネルギーの選択肢」に関して、「既にあることを前提に議論されてはいないか。今やその選択肢すら失われつつあるのではないか」といった危惧の声もあがり、コーディネーターの関村氏は、今後、他学会とも連携しさらに議論を深めていく考えを述べ討論を締めくくった。