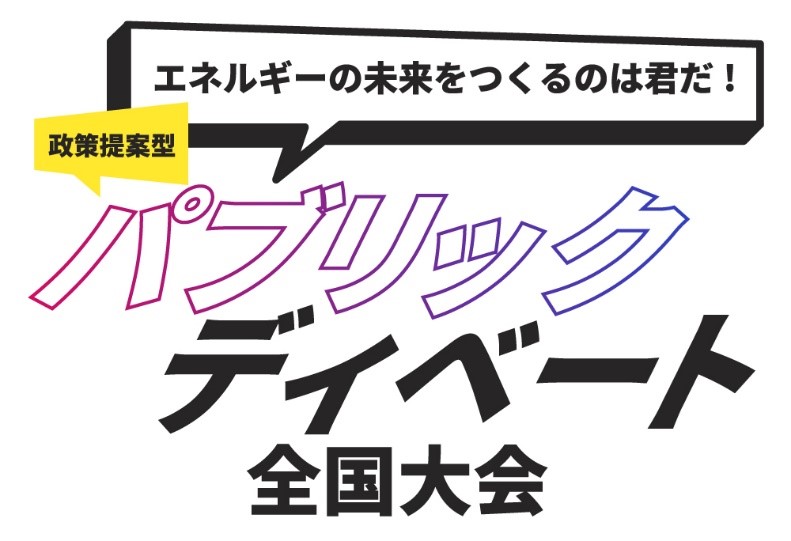エネ基改定に向け有識者らが「エネルギードミナンス」を発表
05 Mar 2024
第6次エネルギー基本計画の策定(2021年10月閣議決定)から間もなく2年半となり、法令に定める見直しの時期を迎えつつある中、原子力委員会前委員長の岡芳明氏を含む9名の有識者らが「第7次エネルギー基本計画」の検討に向けて、2月24日に報告書「エネルギードミナンス」を発表した。これまでも政府審議会などで意見を述べてきたキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏が全体を取りまとめている。
同報告書では、「強く豊かな日本を造るために、豊富、安価、安定なエネルギーを供給し、エネルギーに関する優勢(ドミナンス)を築く」という概念から、「電気料金は東日本大震災前の水準を数値目標とする」など、計11項目の提言を発表。エネルギー需給に関しては、「原子力を最大限活用する(全電源に占める比率50%を長期的目標)」、「化石燃料の安定利用をCO2規制で阻害しない」こと、さらに、再生可能エネルギーの導入や省エネに係るコスト低減や規制制度とともに、EV推進に伴う日本の自動車産業振興への影響にも留意。国際公約の関連では、「パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する」ことにも言及している。
現行のエネルギー政策については、「極端なCO2排出削減目標に束縛され、かつイデオロギー的に技術選択が太陽光・風力・電気自動車などに偏狭に縛られているがゆえに、コストが高く、持続不可能に陥っている」と指摘。その中で、太陽光発電に関しては、天候に左右されるデメリットを「間欠的」と懸念したほか、昨今の自然災害多発に鑑み「破損しても発電し続ける特徴から、感電による二次災害が発生する恐れがある」と危惧し、大量導入を停止する必要性を述べている。
原子力については、「発電量当たりの人命リスクが最も低く安全な電源」と評価した上で、安価で安定な電力の安定供給に向けて、早期の再稼働、運転期間延長、更新投資、新増設が不可欠と強調。その一方で、安全規制と防災に関し「リスク・ベネフィット」の考え方がないバランス感の欠如から、「リスクゼロ」を追い求める姿勢を危惧。さらに、「原子力を利用しないことによるエネルギー安全保障上のリスク、経済上の不利益も大きい」ことを指摘し、今後のエネルギー基本計画改定の中で、さらに議論を深めていく必要性を示唆している。
福島第一原子力発電所事故から間もなく13年。報告書では、昨今の原子力発電を巡る状況に関して、BWRプラント停止の長期化、電気料金高騰による国民生活への悪影響などを踏まえ、「個別の審査だけではなく、中長期的な課題を含め検討すべき時期にある」とも述べている。