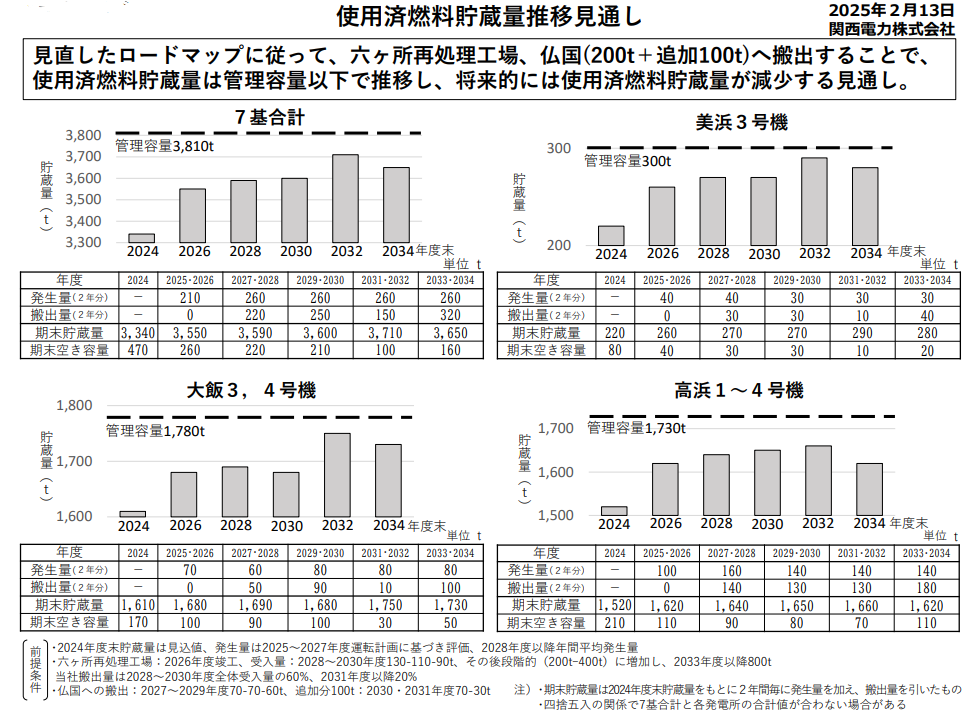【第57回原産年次大会】各国のバックエンド進捗を議論
11 Apr 2024
大会初日最後のセッション2では、「バックエンドの課題:使用済み燃料管理・高レベル放射性廃棄物(HLW)最終処分をめぐって」というテーマの下、(公財)原子力安全研究協会の山口彰理事がモデレーターを務め、国内外の専門家4名が講演した。高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定、使用済燃料管理の柔軟性確保について、海外事例も参考に、地元との共生という視点を取り入れた議論を通じて、今後のわが国の原子燃料サイクルに係る示唆を得ることが狙い。
山口氏は冒頭、原子力の持続的活用には、GX実現に向けた基本方針と国が決定する貢献(NDC)に合致する「正当性」、原子力基本法第一条にある目的(エネルギー資源の確保、学術の進歩、産業の振興、地球温暖化防止)との「合目的性」、革新技術による安全向上や合理的なバックエンドプロセスといった「将来性」、そして、社会的信頼と国民理解、立地自治体との信頼関係、中長期的な対応の柔軟性の「実現性」がカギであるとし、高レベル放射性廃棄物の最終処分へ向けた取組みは、国が前面に立つだけでなく、使用済み燃料の安全管理と貯蔵能力の強化により、対応の柔軟性を高め、中長期的なエネルギー安全保障に繋げるべきと指摘した。
その後、原子力発電環境整備機構(NUMO)理事長の近藤駿介氏が、日本の取組状況を発表。最終処分場の選定プロセスにおいて、2002年から文献調査の受入れを公募し、2017年に地層処分に係る科学的特性マップを公開。2020年に北海道寿都町と神恵内村から文献調査の申し出を受け、2024年2月に文献調査報告書草案が完成したばかりだと説明。「容易な道ではないが、原子力発電の持続的利用のために真摯に取り組む」との決意を示した。最後に同氏は、数々の地域社会との対話活動を通じて、事業者が正しい情報を提供し多様な意見に耳を傾け、信頼できる存在であること、事業者の提案する取組みがそこで実施する正当性を有すると認められること、そして事業者が地域社会を大切に考え、信用できる存在であること、が大切であると強調した。
続いて、フランス放射性廃棄物管理機関(ANDRA)国際関係部長のダニエル・ドゥロール氏が、「仏深地層処分場の立地から許認可取得までの主な課題と成功要因」と題して講演。ANDRAは2023年1月、高レベルならびに長寿命中レベル放射性廃棄物の深地層処分施設「Cigéo」の建設許可を申請しているが、同氏によると、「Cigéo」プロジェクトは段階的に進められ、フランス議会の継続的かつ強力な関与を受け、役割と責任の明確な分担の下、安定して資金を調達しているという。同氏は「Cigéo」プロジェクトの重要な成功要因について、①明確なガバナンスとステークホルダーとの継続的な対話、②意思決定に余裕のあるロードマップとマイルストーン、③各決定マイルストーンで科学的根拠を示せる研究開発、④安定した資金調達と複数年開発計画を可能にする法と政令──の4点を挙げた。
スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB)広報担当上級副社長のアンナ・ポレリウス氏は、スウェーデンのバックエンド進捗状況と地元での合意形成について発表。スウェーデンでは、高レベル放射性廃棄物はオスカーシャムの集中中間貯蔵施設(CLAB)で中間貯蔵し、短寿命の低中レベル放射性廃棄物は海底岩盤で処分するほか、使用済み燃料の最終処分場の建設がフォルスマルクで計画中であることなどを紹介した。同氏は、最終処分場をめぐっては、過去に住民とのコミュニケーション不足からデモ騒動にまで発展したが、2023年時点で支持する意見が86%に達していることを明らかにした。そして立地選定プロセスでは、安全第一を原則に、自治体の自発的参加を促し、オープンかつ透明性を確保しつつ合意形成に取り組むほか、調査、評価、運用の段階的な実施がプロジェクトの成否を握る、とその重要性を強調した。最後に同氏は、スウェーデンでは、規制当局が中立の専門家として信頼性が高いことに触れ、事業者は社会の一員となり、一緒に社会を築いていく意識が必要であると強調した。
またフィンランドPOSIVA社上級副社長のティナ・ヤロネン氏は、同国で建設中の使用済み燃料最終処分施設(オンカロ)について講演した。POSIVA社は、2001年に最終処分施設サイトとして正式に選定されたオルキルオトのオンカロの操業許可を2021年12月に申請。現在、建設とシステムの試運転を継続中で、今年中に試験操業を見込んでいる。また、オンカロの地上には使用済み燃料の封入プラントも建設している。同氏は、オルキルオトを処分地に選定した理由として、地質学的・長期使用の適切性、サイト面積の広さ、使用済み燃料の大部分がオルキルオトにあること、地元の既存インフラの活用、地元住民の理解、地域の将来戦略上の重要性を挙げた。同氏によると、地元との会合を2か月毎に実施するなど理解促進に努め、処分場を選定する直前に実施された住民調査では住民の約60%が建設候補地になることを支持、全国調査では地層処分の安全性について、1990年の肯定的回答の約10%が2020年には40%前後まで増えたという。立地決定の成功のカギは、①事業者の信頼性と透明性の堅持、②信頼できる当局、明確なプロセスと責任・役割分担、③国民に有益な原子力産業──と指摘した。
モデレーターの山口氏は最後に、日本が学ぶべき点として、地域の信頼を得るために原子力や最終処分の正当性を伝えること、ステークホルダーの役割と責任を明確にすること、独立性と専門性の高い信頼される規制機関が安全性を地域住民や国民に伝えること、といった貴重な示唆を得たと評価し、セッションを総括した。