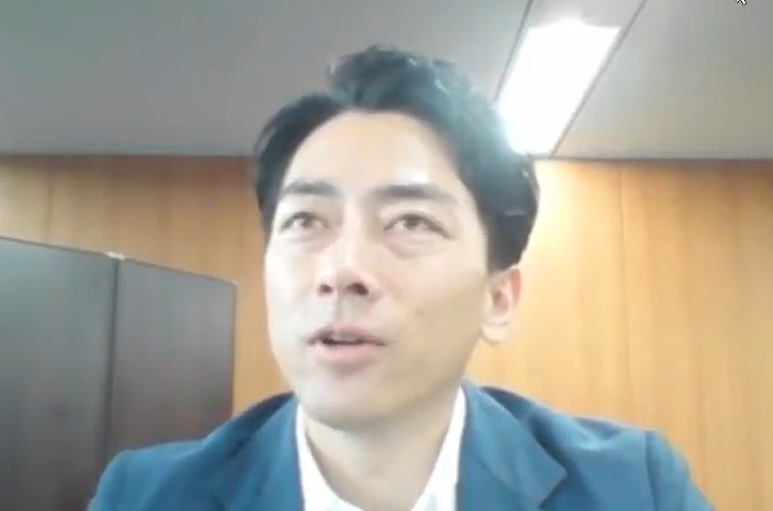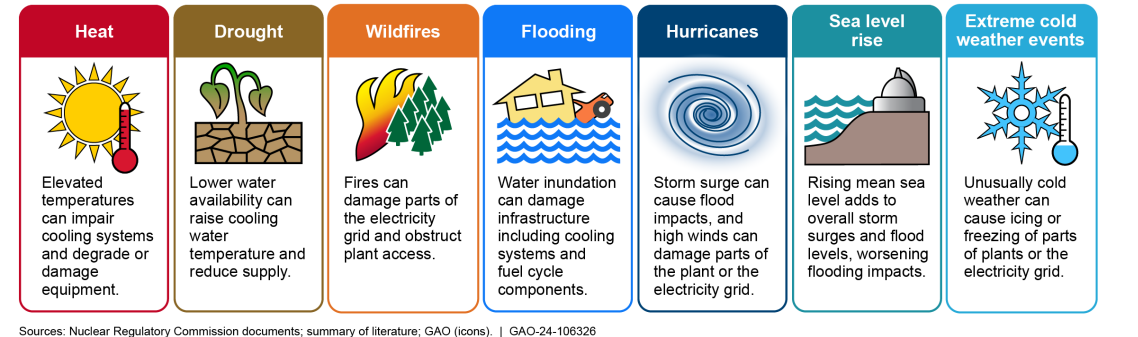環境省・経産省、今後の気候変動対策に向け議論開始
02 Sep 2020
地球温暖化対策計画の見直しを含めた今後の気候変動対策について検討する環境省と経済産業省の合同会合が9月1日に行われた。それぞれ、中央環境審議会、産業構造審議会のもとに、有識者らによる新たなメンバーが構成され、「環境と成長の好循環」を回す両輪としてキックオフ会合に臨んだ。〈配布資料は こちら〉
日本は2015年7月に「2030年度に2013年度比26.0%減の水準にする」との温室効果ガス排出削減目標を国連に提出し、同12月のCOP21で国際的枠組み「パリ協定」が採択された。これを踏まえ2016年5月に地球温暖化対策計画が閣議決定されている。2020年3月には「日本のNDC(国が決定する貢献)」を国連に提出しており、ここで示された「エネルギーミックスの改定と整合的に、さらなる野心的努力を反映した意欲的な数値を目指す」とする今後の削減目標の検討に向けた方向性や、昨今の新型コロナウイルス感染症が及ぼす経済社会活動への影響もとらえながら、日本における気候変動対策について議論することとなった。経産省の総合資源エネルギー調査会では、7月にエネルギー基本計画の見直しに着手したところだ。
合同会合の開始に先立ち挨拶に立った小泉進次郎環境大臣は、(1)NDCに留まらないさらなる温室効果ガスの削減努力、(2)新型コロナウイルス感染症がどのように気候変動に作用するか――を論点に掲げ、特に、コロナ禍による社会構造の変化を認識する必要性を「リデザイン(Redesign)」と強調。委員らに対し、「脱炭素社会、循環経済、分散型社会に移行する必要がある。経済社会の将来像をしっかりと見据え、今までの前提条件にこだわらず議論して欲しい」と訴えかけた。
また、松本洋平経済産業副大臣は、「地球温暖化対策は、『制約』ではなく『機会』ととらえることが重要」と強調した上で、経済活動を犠牲にすることなくCO2排出削減を実現すべく、イノベーション、ファイナンス、ビジネス主導の国際展開の3本柱で取り組んでいく考えを述べた。
委員からの意見表明で、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会委員を務める伊藤聡子氏(フリーキャスター)は、中小企業向けのセミナーに関わった経験から、エネルギーのコストが企業経営に与える影響を懸念し、「やはり安定的に供給できる原子力は欠かせない」とした上で、国民理解の促進なども含め、より現実的な施策を考えていく必要性を強調。
環境省で脱炭素化に向けた石炭火力輸出支援に関する有識者検討会をリードした髙村ゆかり氏(東京大学未来ビジョン研究センター教授)は、「昨今環境戦略を取り入れる企業が増えてきた」と、2015年の現行エネルギーミックス策定時以降の企業経営スタンスの変化を述べ、民間投資の有効性などを指摘。
様々な被災地を取材してきたという山口豊氏(テレビ朝日アナウンサー)は、昨今の豪雨災害の甚大化などに触れた上で、「地産地消と分散型社会」の構築を主張。災害に強い再生可能エネルギーのポテンシャルに関し、「工場の屋根の上など、地方には利用できる資源がまだたくさん眠っている」と述べ、長期的視点から主力電源として活用を検討していく必要性を述べた。
また、山下ゆかり氏(日本エネルギー経済研究所常務理事)は、「これまでの延長線上に答えはないことを肝に銘ずるべき」とした上で、中小企業がリードする仕組み、分野・部門を越えた新たなエネルギー供給システム、消費者自らによる行動とリテラシーの向上、成果の正しい評価と可視化などを議論のキーワードとして提示。
この他、社会イノベーション、デジタル化、海外への技術的貢献、産業界と金融機関との対話、統計・観測データの整理に関する意見があった。