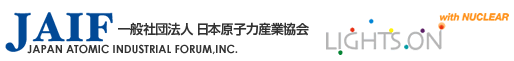【論人】 辰巳 渚 消費行動研究家 「捨てる」ことが問う生活者の哲学現在は、未曾有の不景気ということになっている。私もむろん例外ではないが、みんな、生活がたいへんなのだろうなあと思う。私たちの消費生活は、自動車メーカーや百貨店の赤字などの話を引きあいに出すまでもなく、縮小される一方なのだろう、と。 ところが、私の開いている講座――暮らしのこと、とくに片づけや家事についての講座に参加する多くの人たちは、ほとんどが「捨てる」ことに困っている。 暮らしがすっきりしない。片づかない。なんとかしたい。そんな願いから講座に参加する人たちに、まずはすっきりしないわけの自己分析のワークショップをしてもらう。すると、必ずといっていいほど「捨てられないから」という原因が出てくるのだ。 念のために解説しておくと、参加者は決して無秩序な、だらしない人ではない。買い物中毒でもなく、家が物で溢れているわけでもない(自宅の写真も拝見している)。どちらかというと、論理的に自己分析もでき、日々の暮らしにもていねいに堅実に取り組んでいる、「きちんとした」人たちといったほうが正しい。それなのに、実際の困難として「捨てればもっとすっきりするのに、捨てられない」と困っている。 10年前に「捨てる技術」を唱えて、それが多くの賛同を得たときには、急激に物質的に豊かになった時代のある側面なのだろうと納得していた。要は、現代の私たちは、自分の手に余る量の物を持つようになったのだと思っていた。 ところが、不景気がつづき、買い物も控えて、なおかつエコロジーが言われるこの今になっても、やはり捨てることは日々の困難として立ちはだかる。捨てればいいとわかっていても、捨てられないのが人情なのだ。 以前、日本人の捨てる文化について調べたときに、器物を捨てることでその器物が妖怪となり(付喪神)人にたたるという話をかいた絵巻が室町時代に登場したことを知った。日本文学の研究者は、これを飛躍的に工業生産力の伸びた室町時代だからこその発想だろう、と分析していた。日用の道具が庶民レベルでも豊富に持てるようになったことの表れとしていた。 そしてまた、まだ電気冷蔵庫が物珍しかった高度経済成長期に、すでに冷蔵庫のなかで物が腐っており、食べられない食品を捨てたら冷蔵庫の中身が3分の1になったという報告が『暮らしの手帖』に掲載されていることも知った。 どうやら、捨てることは、物の絶対的な量とはそれほど関わっていない気がしてきた。周囲に物が多ければ多いなりに、少なければ少ないなりに、人は身のまわりに寄せ集めた「物」と格闘するものなのではないだろうか。人は道具を使って生きる動物であるために、その道具を「使う―使わない」「まだ使う―もう使わない」「まだ使える―もう使えない」のあいだで、つねに困り果てるしかないのだ。 物の多少を問わないのであれば、現代の特徴は、誰もが等しく物の所有機会を与えられている点にあるだろう。お金がそれほどなくても、手に入れたいものであればほぼ手に入る。たとえローンであっても、いくつものほしいもののなかから厳選したものであっても。若者でも、一点だけはヴィトンのバッグやロレックスの時計は持てるのだ。 どんな物を持つか(私が使いたいか)は、その物を使ってどのような生活を営みたいかという意思とイコールである。つまりそこには、「私とは何か」「私の幸せとはどういうことか」という哲学が存在することになる。物の所有機会の平等が保障された現代だからこそ、生活者の哲学が育ってくる可能性を私は信じている。 (WEN(ウイメンズ・エナジー・ネットワーク)にも参画。著書『「捨てる!」技術』(宝島社新書)はミリオンセラーに) |
|
お問い合わせは、情報・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |