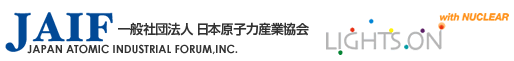【日米協定の検証】 日米原子力協定の成立 経緯と今後の問題点〈第5回〉 遠藤 哲也 元原子力委員会委員長代理、元外務省科学技術担当審議官 ― 協定の実質合意から正式署名まで ―日米原子力協定は1987年1月、5年近くの難交渉の結果ようやく両国代表レベルで実質合意に達した。次の目標は、正式署名であり、次いでそれぞれの議会の承認を得て、正式に発効させることである。一般的に言うと、二国間協定や条約は、実質合意から正式署名までに行われることは内容に深入りすることなく、主として法律的なチェック(日本の場合は、内閣法制局による審査)であってそれ程時間のかかるものではない。しかし、この日米原子力協定は例外であった。米国の場合、その過程が非常に難航し再交渉の可能性さえささやかれたほどであった。 ちなみに、筆者は1987年1月に前任の松田慶文大使に代わり、外務省科学技術審議官に就任し、日本側の交渉代表となり2年振りに協定交渉にかかわることになった。 〈協定締結に至る米国内の手続〉 米国では、原子力協定の交渉から発効に至るまでの手続が原子力法(1954年)に規定されている。それによれば、原子力協定は国務長官がエネルギー省長官の協力と同意を得て軍備管理軍縮庁(ACDA)長官(注:現在は省庁改編により存在しない)と協議の上交渉する。事実、米国の交渉団は国務省のR.ケネディ核不拡散担当大使(=写真)を代表に国務省、エネルギー省を中心に構成されていた。交渉が実質的にまとまった段階で、両省長官は共同で両省、原子力規制委員会(NRC)およびACDA長官の意見と勧告を付して協定を大統領に提出する。この間、国防省、国家安全保障会議(NSC)も意見を申し述べることができる。 大統領は、協定の実施が米国の防衛と安全を促進し、不当な危険をもたらすものでないことを文書で決定する。これらの手続を経て、正式署名の運びとなる。 正式署名後、協定は議会(上下両院)に提出されるが、継続会期中の90日間の議会審議を終了した後であって、その審議期間中に協定に賛成しない旨の共同決議が成立しなかった場合に、協定が発効することになっている。 アラスカ州、カナダの反対の動き 実質合意を経て、正式署名に向けての作業を進めている最中、プルトニウム利用反対を主張する米国核管理協会(会長レーベンソール氏)の報告書が発表され、大きな影響を与えた。この報告書はアラスカ州、カナダなどで大きく報道され、これを契機に協定のプルトニウム航空輸送問題に焦点があてられた。プルトニウムの航空輸送は技術的にも多くの問題があり、現時点での協定の締結は時期尚早というものであった。 カナダでは運輸大臣が下院本会議で批判的な発言をし、またアラスカではこの協定は州知事がアラスカの環境、州民の健康に重大な影響を及ぼしかねないとして環境影響評価書の作成を要請したりした。米国務省としては、このような動きを何とか押え込んだものの、これは協定が議会に提出された後、審議が難航することを予想するものであった。 〈米国行政府部内からの不協和音〉 協定交渉において、国務省とエネルギー省は国務省リードの下に二人三脚で対応して来たが、大統領決裁、正式署名に至る過程での関係省庁との協議を通じ多くの反対が出て来た。 1つはNRCからで、反対理由は次のとおりであった。 (イ)将来運転される施設について、具体的にどのような保障措置が適用されるのかがわからないにもかかわらず、これらの施設を包括同意の対象にするのは問題ではないか。 今1つは、国務省からであり、ワインバーガー長官とパール次官補がその急先鋒であり、反対論旨は、次のとおりであった。 (イ)非核兵器国の日本に30年間もプルトニウムの使用を認め、また建設準備中の再処理施設に対しても先取り承認を与えるのは、安全保障上かつ核不拡散政策上も問題である。 このように、米国の国内手続に予想以上の時間がかかり、1987年9月の日米首脳会談で中曽根総理よりレーガン大統領に対し迅速な処理を要請したほどであった。紆余曲折を経たが、10月28日にレーガン大統領は本協定を承認し、米国原子力法上必要とされる文書による決定を行い、かくして正式署名のための国内手続は完了した。 正式署名は、1987年11月4日、東京で倉成正外務大臣とマンスフィールド駐日米国大使との間で行われた(=写真上)。しかし協定発効まではこれからが大変であり、未だ「道半ば」であった。 |
|
お問い合わせは、情報・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |