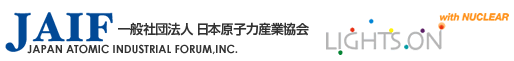規制側、事業者間で、「十分な議論を」 米国地球物理学誌 敦賀2号破砕帯、活動性ない地球物理学分野で権威のある「米国地球物理学連合」は、日本原子力発電の敦賀原子力発電所2号機の直下を通る破砕帯に関する問題を取り上げ、同破砕帯には活動性がないことや、主張を異とする規制側と事業者間の間では、十分な議論を交わした上での判断が不可欠だとする、専門家チームによる論文を掲載した。 同論文は「活断層と原子力発電プラント」と題し、1月28日付けで、同連盟が発行する論文誌「EOS」に掲載されたもの。執筆した専門家チームは、英国地質学者のニール・チャップマン氏(シェフィールド大学教授)、ニュージーランドGNSサイエンス研究所の地質学専門家のケルビン・ベリマン氏ら6名で構成されている。 原電の敦賀原子力発電所については、原子力規制委員会が昨年5月、同2号機原子炉建屋直下の破砕帯につながるK断層の活動性を指摘。それに連動するD―1破砕帯も活断層である可能性があると判断した。これに対し、原電側は否定する主張を展開し更なる調査を実施。7月には追加調査の結果を報告書として規制委員会に提出した。 「米国地球物理学連合」に掲載された専門家チームの論文は、活断層判断の対象となる後期更新世以降に動いた証拠はなかったとの原電の調査結果を支持。D―1破砕帯は後期更新世よりかなり古いもので、K断層も2号機には達しない段階で消滅する傾向が見られ、D―1破砕帯、K断層とも、以前より存在が知られている浦底断層との連動は見られず、2号機の直下に活動性のある構造を示す証拠はないとする原電の主張は正当であるとの結論を示している。 その上で、同論文は、敦賀発電所を評価したこの専門家チームが「単に活動性があるかないかによってのみ、重大な結論を引き出すべきでない」と結論づけていることも強調している。 また、他国の例として、米国カリフォルニア中央沿岸のディアブロキャニオン原子力発電所のハザード評価にも触れ、規制委員会(NRC)、地質・地震研究機関、学会、コンサルタントらによる最先端の地質科学調査への積極的関与によって、包括的な耐震計画が得られており、ピアレビューなどを通じ、規制側、事業者との開かれた対話と相互理解につながっているとしている。 論文は終わりに、「ベストアプローチの探求」として、国がエネルギー供給と公衆の安全に関する課題に向き合う際の重要な判断材料についても言及し、断層の最新活動の年代設定を重視することが重要なのか、地震に耐えられる構造設計を確保した上で断層の活動する確率を評価し現実的で合理的な対策を講じることが重要なのか、問題提起している。断層の活動性に関する確実な評価を可能とするためにも、最新の知見に基づき規制側と事業者の間での十分な議論が必要である点も強調した。 規制委員会による昨年5月の評価結果では、新たな知見が得られた場合は、結論を見直すこともあり得るとしていた。日本原電からの追加調査結果提示を受け、同委員会は1月20日、敦賀2号機の敷地内にある破砕帯の現地調査を始めたところだ。今後は、偏りのない科学的根拠や幅広い議論に基づく判断が求められよう。 お問い合わせは、政策・コミュニケーション部(03-6812-7103)まで |