原子力学会調査、中学校理科教科書で放射線関連の記述が倍増
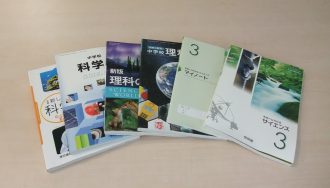
今年度から使用されている中学理科教科書
中学校理科では、2008年の学習指導要領改訂により、放射線を取り扱うことが約30年ぶりに盛り込まれたが、2016年度から使用開始の改訂版では、福島第一原子力発電所事故について、調査対象のすべての教科書で取り上げられていたほか、放射性物質の種類や半減期、放射線や被ばくに関する単位、事故と関連した放射線影響に関する説明など、放射線関連の合計ページ数は、2011年度使用開始の旧版が8ページだったのに対し、16ページに倍増したとしている。
一方で、今回の調査結果では、原子力発電所事故の対応と今後に関する記述について、「公的資料やメディア情報に基づいているが、極力正確で公正な取扱いをした資料を参照して欲しい」と指摘しているほか、放射線影響に関しても、最新の情報に基づいたより丁寧な説明を求めるなど、合わせてコメントを示している。

原子力学会記者会見の模様(同学会本部〈東京・港区〉にて、左から、工藤氏、このほど会長に就任した上坂充氏〈東京大学〉、前会長の上塚寛氏〈日本原子力研究開発機構〉)
今回の調査で示された教科書の記述内容とコメントの例
・記述…2011年に発生した東北地方太平洋沖地震では、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉が破損する事故が起こった。(社会、理科、技術・家庭)
(コメント) 「東北地方太平洋沖地震とこれにより起きた津波により…」とする方が適切と考える。
・記述…低い放射線量でも、長期にわたって被ばくすると、ガンになる可能性が高まります。(社会、理科、保健体育)
(コメント) 放射線被ばくによるがんの発生は確率的影響だから、高い放射線量では発生確率は高くなるが、低い放射線量での健康影響は、日常生活の他のリスクと区別できないほど小さくて、影響があるのかまだ「わからない」のが今の科学知識のレベル。「低い放射線量を長期にわたって被ばくしたときの、人に与える影響は明らかになっていません」といった表記にすることを提案する。
・記述…2011年の原子力発電所の事故後は、食品から放射性物質が検出されました。(技術・家庭)
(コメント) もともとすべての食品には放射性物質が含まれている。「食品から規制値を超える放射性物質が検出されました」等と表現するのが適当。
・記述…原子力発電の短所:使い終えた核燃料の処分や廃炉にすることが困難である。(理科)
(コメント) 「困難」というよりも、作業者や周辺公衆への被ばくを避けるために作業を慎重に行う必要があるのであり、「発電によって生じる強い放射線を出す廃棄物の処分場が未定であり、廃炉作業は作業者や周辺住民の安全を確保しながら慎重に進めるために時間がかかる」とする方が適切。