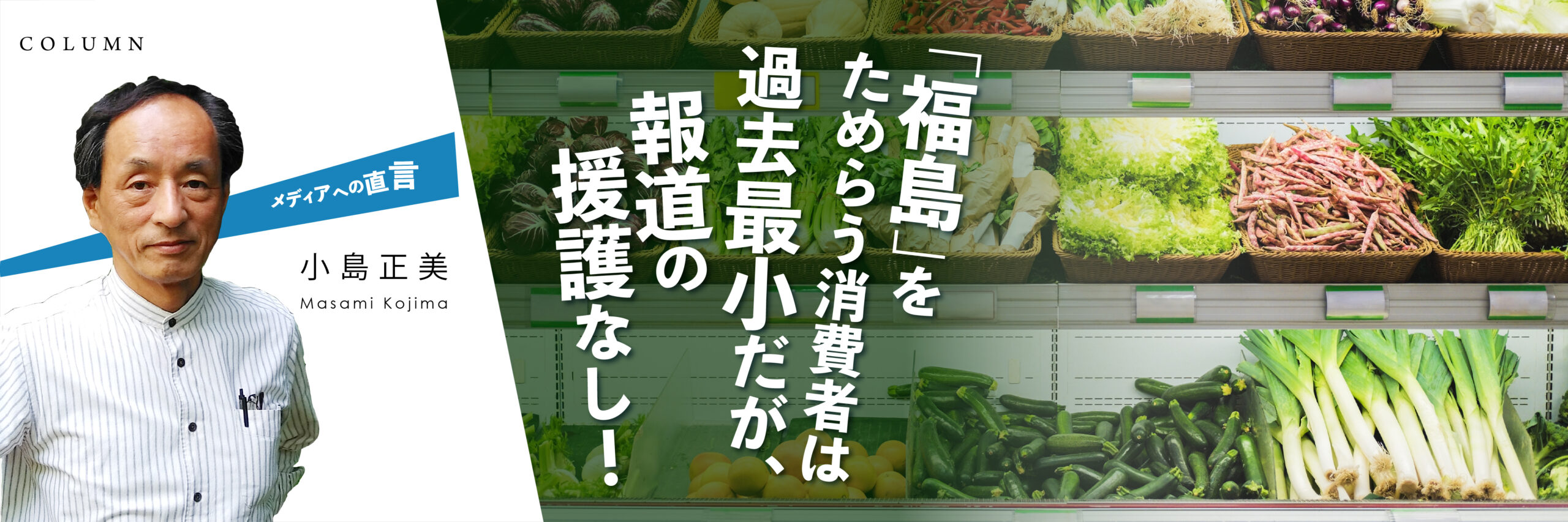「福島」をためらう消費者は過去最小だが、報道の援護なし!
二〇二三年五月十九日
福島第一原子力発電所の処理水の放出がいよいよ目前に迫ってきた。ことの成否は消費者の意識次第だが、タイミングよく今年三月、消費者庁が「風評に関する消費者意識の実態調査」(第十六回)を公表した。とても重要な調査結果なのだが、ほとんど報道されていない。たとえ地味な結果でも、メディアはもっと現状を伝えてほしい。
「福島産をためらう」は過去最小
処理水が実際に海へ放出された場合、最も注目されるのが、どのメディアも再三報じているように風評被害が生じるかどうかである。消費者が福島産の食品を従来通りに買ってくれれば、風評被害は発生しない。そこでポイントとなるのが、どれだけの消費者がいまなお「福島産食品を避けたい」と思っているかどうかである。
その重要な指標となる意識調査が今年三月十日、消費者庁から公表された。食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、第1回(二〇一三年二月)の調査では「福島」を挙げる人が一九・四%もいた。ところが、今年一月(第十六回)の調査では五・八%と過去最小に減った。
放射性物質を理由に購入をためらう産地として、東北(岩手、宮城、福島)を挙げる人の割合も同様に減り、二〇一三年の一四・九%から、今回は三・八%に減った。
安全な情報は国民に届かない
これらの数字を見ていると、スーパーなどで放射性物質を理由に福島産や東北産を避ける人は確実に減っていることが分かる。こういう調査結果こそ大々的に報じてほしいのだが、新聞を見ていてもほとんど報じられていない。
「福島産が危ない」といったニュースは瞬時に流れるが、安全だというニュースはなかなか国民に届かない。「そもそもニュースとはそういうものだ。記者とは危ない情報を好む職業だ」といってしまえば、身もふたもないが、処理水の放出が目前に迫ったいまだからこそ、逆に安全な情報にニュース価値があるはずだ。どうもいまの記者の感度は鈍いと言わざるを得ない。
どの新聞の記者たちも処理水の放出で最大の懸念は風評被害だと書いてきた。ならば、風評被害が生じにくい空気が醸成されつつあることは喜ばしいことなのだが、記者にとって「喜ばしいことはニュースとしておもしろくない」となってしまう。風評被害の解消にはメディアの的確な報道が欠かせない。にもかかわらず、安全な情報をシャットアウトしてしまう。こういう記者のスタンスでは、やはり風評被害の解消は難しいのではないかと思いたくもなる。
「検査知らない」は最高の六三%
一方、福島県ではいまも魚介類や食品の放射性物質の検査は継続して行われている。その結果も公表されているが、地味な話題のせいか、最近ではほとんど報じられない。その弊害は今回の調査結果にも表れた。
食品中の放射性物質の検査が行われていることを「知らない」と答えた人の割合は、二〇一三年の二二・四%から徐々に増え、今回はなんと過去最高の六三%にはね上った。「検査結果を知らない」ということは、よい意味に解釈すれば、もはや放射性物質のことは気にしていないということになるのだろうが、そういう無意識に近い状態のままだと突如、危ない情報が飛び込んでくると一気にひっくり返る恐れがある。
福島県の農林水産物のモニタリング検査結果(二〇二二年度)によると、米、野菜、果物、肉類、水産物など四七〇品目で一万二六四件が検査されたが、基準値の一キログラムあたり一〇〇ベクレルを超えた件数は、牧草・飼料作物の一件だけだった。もはや福島産を気にする理由は全くない状態になっている。こうした地味な調査結果を伝えるのが記者の仕事である。いや記者にしかできない仕事である。その自覚がいまこそ必要だろう。
流通事業者の存在意義を示すとき
風評被害の解消に欠かせない存在として、記者以外に見逃せないのが流通事業者である。特に大手スーパーの存在意義は大きい。
もう昔の話になるが、一九九九年に埼玉県所沢市でダイオキシン騒動があった。所沢産のホウレンソウが焼却場由来のダイオキシンで汚染されているというニュースが民放テレビ(テレビ朝日)で流れた。この問題が一気に大きな話題となったのは、大手スーパーが所沢産ホウレンソウの取り扱いを中止したときだった。大手スーパーが取引を中止すれば、当然ながら、記者たちは「危ないネタ」に喜び勇んで駆けつけ、ビッグニュースに仕上げる。以来、ハチの巣をつつくような大騒ぎになった。
この問題は結局、訴訟になり、五年後の二〇〇四年、テレビ局が謝罪し、和解金一千万円を支払うことで終決を見た。深く考えることなく、危ないニュースに飛びつく報道のDNAに警鐘を鳴らす事件でもあった。
結論。処理水の放出にあたって、過去の経験から学ぶべきことは何だろうか。
まず記者は現状を冷静に伝えること、そして安全な情報はたとえ地味ではあっても国民に伝える価値があることを自覚して報じることだ。
一方、流通事業者は風評被害の火付け役になりうる自覚をもち、福島産食品をしっかりと店の棚に置いてほしい(もちろん科学的に安全だという条件付きだが)。店に福島産食品があれば、あえて買うことで福島を応援する消費者もいるだろう。店にモノがなければ、選びようがない。記者と流通事業者が「風評被害を生じさせない」という意識をもつことこそが、処理水放出の成否を握っているのではないだろうか。