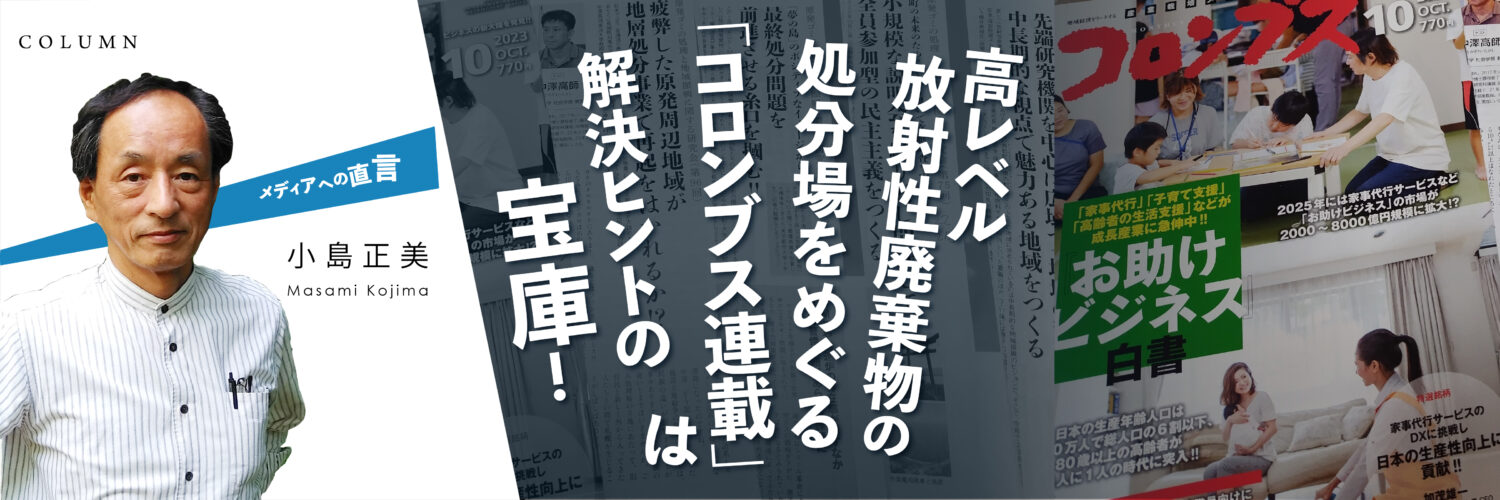高レベル放射性廃棄物の処分場をめぐる「コロンブス連載」は解決ヒントの宝庫!
二〇二三年十月二十四日
原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定が難航している。長崎県対馬市の比田勝(ひたかつ)尚喜市長が九月下旬、文献調査に応募しない考えを表明したことで、その難航ぶりがうかがえる。しかし、実は、選定をうまく進める方策のヒントはすでに出尽くしている。いったいどういうことか。
提言の宝庫の「コロンブス」
結論を先に言おう。地方を元気にする情報満載の月刊経済誌「コロンブス」(東方通信社発行)に連載されている「原発ゴミの処理と地域振興に関する研究会」の記事(写真参照)のことだ。毎回三~四ページにわたり、処分場の選定を成功させるヒントを数多く載せている。連載は二〇一五年から始まり、今年十月号で96回目を迎える。タイトルにもあるように処分場の選定と地域振興をセットにして論じているのが特徴だ。
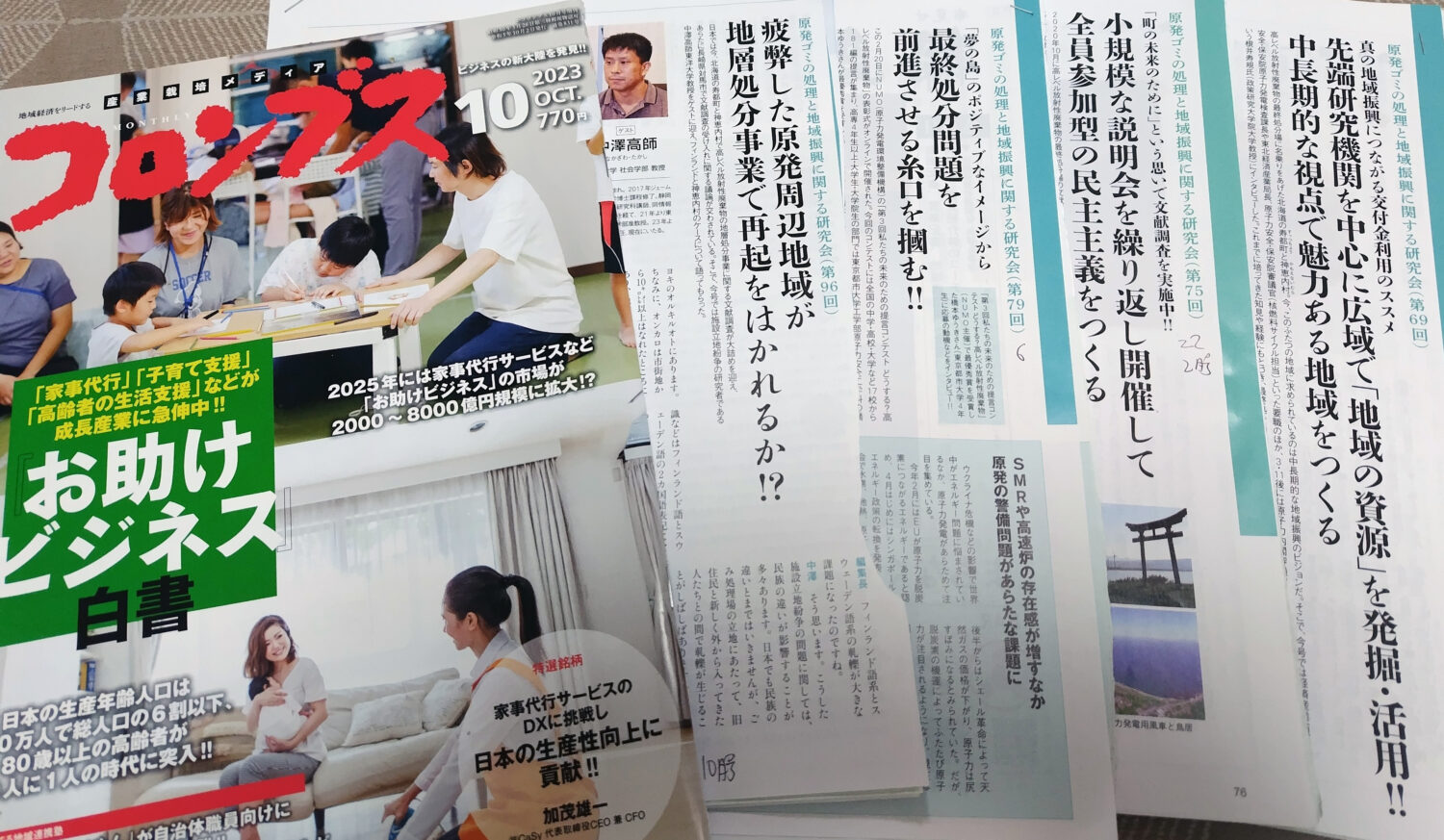
最近では、毎回、古川猛・編集長がインタビューする形で、さまざまな分野の専門家や行政関係者の個性的な意見や提言を見事に引き出していく。そこにあるのは、処分場の選定を通じて、地域をいかに振興していくかという視点である。地方の経済を元気にさせる方策のひとつとして、処分場の選定を考えていこうという明確なスタンスがあるため、読んでいて「なるほど、こういうアイデアもあるのか」とうなずくことしきりだ。そして、その論考に対して、複数の専門家がどの部分に共感し、どの部分に問題があるかをコメントするという贅沢な連載だ。
新聞の社説は
まるで評論家気取り
これに対し、処分場の選定をめぐる新聞報道は総じて反対運動の声を大きく取り上げたものが多い。いくら記事を読んでも、何をどうすればよいかのヒントはほとんど見つからない。
たとえば、長崎県対馬市が九月下旬、文献調査の受け入れを拒否したことに関しても、中國新聞の社説(九月三十日)は「カネ頼みの適地選定の限界を認識し、改めるべきだ。多額の原発関連の交付金を得て活性化した地域があるのか。交付金が発展にはつながらないことを多くの自治体は学んでいる」と書いた。北海道新聞の社説(九月二十八日)も「巨額の交付金で市町村を誘導する処分場選定手続きを抜本的に見直すべきだ。…地震国の日本に遠い将来まで地盤が安定した適地など本当にあるのだろうか。」と書いた。
ネットで読める地方紙の他の社説も読んでみたが、どの社説を読んでも、国や自治体のやり方を批判するだけで、処分場の選定をどう進めるべきかに関する提言やアイデアは全く見当たらない。まるで他人事意識の評論家のような論調だ。北海道新聞の同社説は「地方振興の政策と処分場の選定は切り離すべきだ」とさえ主張している。交付金もダメ、地域振興も考えるな。いったい何を言いたいのだろうか。地域の振興や発展につながらない処分場を受け入れる自治体があるとでも言うのだろうか。
批判することはたやすい。それに比べ、困難な状況を打開する建設的な提言は、はるかに知的な営みを必要とする。上記のような社説の言い様は以前からの社説と同じ内容であり、新鮮味がないばかりか、蓄積された知的な営みも全く感じられない。
熱く語る大学生に
耳を傾けたい
これに対し、コロンブスの連載記事はどうか。事態をなんとか解決しようとする真摯な提言と斬新なアイデアに満ちている。上記の社説とは正反対で、読んでいて胸が熱くなる。
第79回の連載(二〇二二年六月号)は、東京都市大学理工学部原子力安全工学科4年の橋本ゆうきさんが登場した。橋本さんは原子力発電環境整備機構(NUMO)主催の、第三回私たちの未来のための提言コンテスト「どうする?高レベル放射性廃棄物」で最優秀賞を受賞している。
東京都江東区にある「夢の島」はかつてゴミの最終処分場だったが、いまでは熱帯植物園やスポーツ施設が立ち並ぶ夢の島に変わった。そう言う橋本さんは「原子力ムラというとマイナスのイメージで見られますが、もっと呼び名も含め、地域住民が誇りをもてるようなポジティブなイメージ戦略を展開すべきではないか」と述べる。
そしてさらに、国際原子力機関(IAEA)の廃棄物の定義から、次のように話す。
「放射性廃棄物は、化学的毒性をもつ廃棄物の処分と何ら変わらないので、これまで人類が経験してきた処分の延長線上にあると思う。放射性廃棄物のガラス固化体を地下深くに埋設するという手法は安全性もしっかりと担保できているはずだ。放射性廃棄物を再利用するという形の発想も必要だ。福井県の美浜原子力発電所を見学した際は、地域の人たちが自分たちの歴史や文化を守るという姿勢と心が感じられた。みなの合意形成には原子力に関する基本的な知識の共有も大切だ」(筆者で要約)。
空論的な発想もあるかもしれないが、事態をどう前進させるかに関して、熱き思いが伝わってくる。
神恵内村の村長の心情は
何だったか
過去には、最終処分に関する文献調査を受け入れた北海道寿都町の片岡春雄町長や神恵内村の高橋昌幸村長も登場した。文献調査を受け入れると国から二十億円の交付金が支給される。高橋村長は現在の公募方式などに対して次のように語っている。
「…二十億円で村民の命を売るのかと批判されてしまう。しかし、たった二十億円で神恵内村を売るつもりはないし、その金額が百億円になろうが、売るつもりはない。日本はこれまで原子力発電の恩恵を受けてきた。高レベル放射性廃棄物をどうにかしなければならないという意識を持っていたので、最終処分場問題に一石を投じるためにも、文献調査を受け入れる必要があると判断した」(筆者要約)。
この連載を読んで、高橋村長の真の胸の内を初めて知った。新聞はこういう心情をなかなか素直に報じない。高橋氏は「村では、文献調査に同意してくださる方のほうが多数を占めているのに、反対の声のほうが大きいこともあって、マスコミは反対意見ばかりを取りあげる」とも言っている。処分場をめぐる新聞記事がいかに偏っているかが分かる。
連載をぜひ一冊の本に
九十六回もの連載の内容をここですべて紹介することは不可能だが、ざっと思い出すだけでも、以下のようなものがあった。
「処分場の候補地をエコツーリズムの対象にして、地域振興に結びつけたらどうか」「候補地を名乗り上げてもらうのではなく、国と第三者によって科学的な観点から適性候補地を選定すべきだ」「地層処分と地域振興にかかわれるファシリテーターとしての若い人材の育成にもっと力を入れるべきだ」「ハイテク都市として成功した米国のオースティン市のように、処分場のある地域に研究機関や民間企業を呼び、最先端テクノロジーの町として振興することは可能だ」。
一番新しい96回目の記事では、中澤高師・東洋大学社会学部教授が、放射性廃棄物の地層処分施設を建設しているフィンランドと、文献調査を受け入れた北海道神恵内村の事例を詳しく述べている。日本では経済産業省やNUMOが地層処分事業を推進しているが、フィンランドでは電力会社が推進しているという。
これまでの連載記事をすべて精査すれば、おそらく処分場をうまく選定する方策のヒントは、どこかの連載記事ですでに語られていることだろう。それくらい重厚な内容である。ぜひ、この連載をテーマ別に並べ替えて、一冊の本にしてほしい。だれにとっても、末永く参考にできる良質のテキストになるだろうと確信する。そして、行政関係者やメディア関係者にとっては必読の本となるだろう。出版社の出現を期待したい。