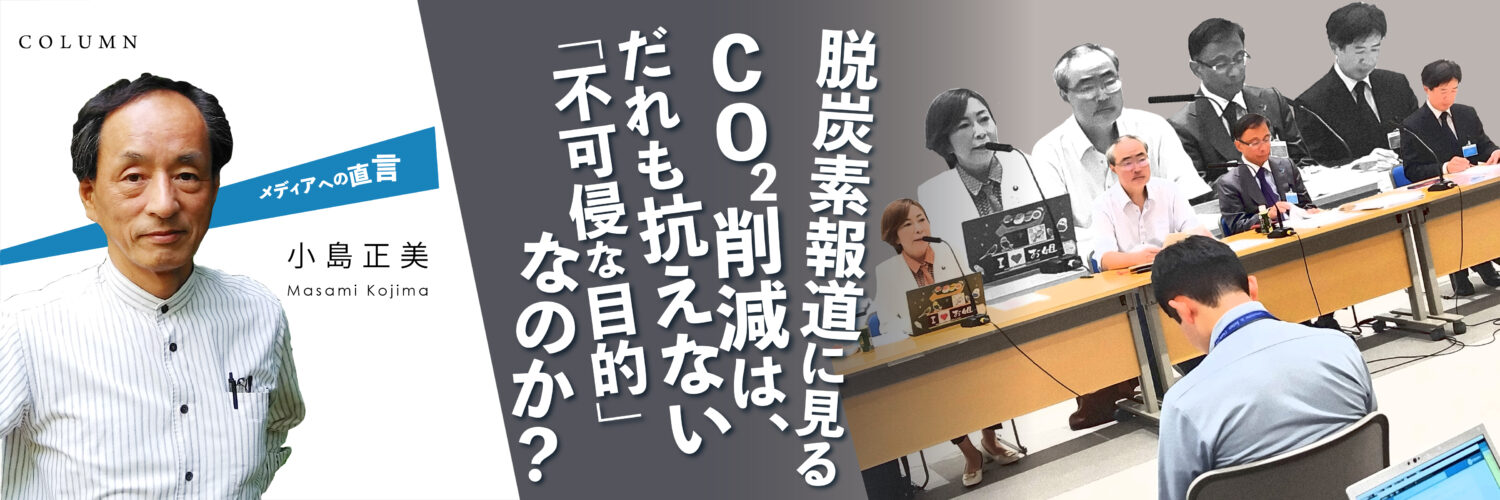脱炭素報道に見るCO2削減は、だれも抗えない「不可侵な目的」なのか
二〇二四年六月十日
東京都が新築住宅に太陽光パネルの設置(二〇二五年四月から施行)を義務づける問題で五月二十八日、杉山大志・キヤノングローバル戦略研究所研究主幹ら四人が記者会見を行い、設置義務化の中止・撤回を求める請願書を知事に提出した。翌日のニュースでは夕刊フジを除き、記事にはなっていないが、この会見を聞いていて、メディアの盲点に気づいた。それは何か。
中国のジェノサイドに
加担か?
この問題での会見は二〇二二年十二月に次いで二回目だ。今回は杉山氏のほか、経済安全保障アナリストの平井宏治氏、「全国再エネ問題連絡会」共同代表の山口雅之氏、上田令子・東京都議会議員の四人が会見に臨んだ。杉山氏は「日本の太陽光パネルの約八割は中国からの輸入品だが、その約半分は強制労働の疑いが強い新疆ウイグル自治区で生産されている。しかも、石炭火力を使ってパネルを生産しており、CO2を発生させている」と衛星画像の写真を示しながら、東京都の設置義務化はジェノサイド(集団的な残虐行為)に加担するものだと訴えた。
さらに「太陽光発電の平均利用率は一七%程度なので、太陽光が稼働していないときは火力発電が必要になり、二重投資だ。太陽光発電が増えた西欧では電気代が上がっている」と語り、小池知事は設置義務に伴って増える費用負担が全国民に及ぶことを説明すべきだと強調した。
再エネ賦課金は
再エネ事業者への贈与
平井氏は、英国の二名の専門家が中国での太陽光パネルの生産実態を克明に報告したレポートを片手に「中国製太陽光パネルには人権侵害(強制労働)で製造されたポリシリコンを使用しているものがあり、東京都は人権侵害サプライチェーンに組み込まれる。メディアはこの問題をもっと報道してほしい」と訴えた。
固定価格買取制度(FIT)とは、太陽光や風力などの再生可能エネルギー業者が、電力会社に固定価格で二十年間売電し、電力会社がこれを買い取ることを国が約束する制度である。その買取費用は電気を利用するすべての人が再エネ賦課金として負担し、その額は年間約三兆円にもなる。平井氏は「再エネ賦課金は、全ての電気利用者から電気代とは別に強制徴収されるもので、全電気利用者から再エネ事業者への贈与である」と語り、太陽光発電事業者などが、再エネ賦課金を原資とする利益の一部を「再生可能エネルギー普及拡大議員連盟」の議員に政治献金としてキックバックする利権構造が、再エネ推進のひとつの原動力になっていると指摘した。
山口氏は「太陽光発電は土砂災害、災害時の感電、環境破壊、悪質な事業者の存在、人権侵害など問題だらけだ」と訴えた。
会見には私も含め、約十名の記者が出席していた。前回の会見ほどの記者は集まらなかったが、杉山氏らの熱い訴えは記者たちの心に通じたと感じた。印象に残ったのは、東京新聞の記者が「太陽光以外に二酸化炭素を減らす方法はあるのか」と尋ね、NHKの記者も似たような質問をしたことだ。杉山氏は「原子力などがある。蓄電池を使っても、太陽光の平均利用率が低い壁は超えられず、三重投資になるだけだ」と答えていた。
CO2削減はもはや
「神」のような存在か
そうしたやりとりを聞いていて、ハッと気づいたことがある。記者たちは「今はCO2を何としても削減しなくてはいけない。そのためなら、太陽光の利用率が低くても、また電気代が上がっても、また全国民に負担が増えても、それはそれでしかたがない」と思っているのではないか。そんな気がしたのである。
世の中の空気やメディアの動きを見てみよう。少しでもCO2が減るならば、日本が誇るべき高性能の石炭火力産業が滅んでもやむを得ない。少しでもCO2が減るならば、日本が世界に誇るべきハイブリッド車が滅んでもやむを得ない。少しでもCO2が減るならば、西欧に追随するのもやむを得ない。そんな空気があるのではないだろうか。
大手金融機関が石炭火力など化石燃料事業への融資を止める愚かな所業を見ていると、もはや「CO2の削減」は、だれも逆らえない絶対的な至上命令であり、まるで宗教の原理主義もしくは神聖不可侵の「神」かのような存在にみえる。
「目的」を問うことが重要
この「神」は新型コロナの流行時に恐るべき威力を発揮した。新型コロナが猛威を振るった当時を冷静に振り返ってみよう。感染リスクを防ぐという絶対的な目的の前に、人々はいともたやすく外出・移動制限を受け入れた(=移動の自由の権利を手放した)。そして、会食や会議も開かず、イベントの開催も中止、ちょっと咳をするような人がバスに乗ろうものなら、一斉にその人を非難した。飲食店がつぶれて、自殺者が続出してもみな沈黙していた。身内に重症患者が出ても面会にも行けず、親しい死者を弔う葬儀へも行けなかった。
そこに立ち現れたのは、お互いがお互いを監視する恐るべき社会だった。
当時、私の友人は神経性の病で余命一か月と宣告された。私は病棟へ行こうとしたが、コロナ感染防止を理由に面会が許されなかった。友人は一か月後に他界した。長年の友に「ありがとう」の一言さえ言えなかった。コロナ感染を防ぐという緊急事態の前に、全国民がひれ伏すしかなかった。
これが何を意味するかと言えば、「コロナ感染を防ぐ」という「目的」が正しければ、どんな横暴な手段も正当化され、抗えないということだ。目的を達成するための手段が非合理なものでも、異議を唱えることが難しくなる。それが新型コロナ感染のときに繰り広げられた恐怖の構図だ。もうお分かりだろう。「CO2の削減」が絶対的に正しい目的なのであれば、いかにおかしな政策でも、抗うことが難しくなるのである。
「CO2減じて国破れたり」
「国破れて山河あり」をもじって言えば、「CO2減じて国破れたり」だ。CO2をいくら削減したところで、自国産業が滅んでは意味がない。たとえCO2が減っても、日本のGDP(国内総生産)が減れば、何の意味があろう。CO2を減らしたけれど、貧困は改善されず、経済格差も縮小されない。そんな結果になっても、CO2が減ったからよかったではないか、とでもいうのだろうか。
二〇五〇年、CO2は減ったけれども、裕福な国や層しか生き残っていない。そんな世界に突き進んでいる気がする。
東京都は再生可能エネルギーの促進などに千九百七十億円(二四年度予算)を投入する。杉山氏は千九百七十億円を費やしても、「気温の低下は〇・〇〇〇〇〇〇二度に過ぎない」との試算結果を示す。ほとんど効果なしである。しかし、CO2を削減するためなら、税金の無駄遣いも、電気代の負担増も、中国への依存も許されるのだろうか。
CO2を削減するために何をなすべきか、ではなく、そもそもCO2の削減は本当に正しい目的なのかをいまこそ問うべきではないだろうか。仮に洪水被害の防止が目的ならば、CO2削減よりも確実な対処法はいくらでもある。また仮に異常気象による被害を抑えるのが目的ならば、経済的な力を蓄えておくほうが手際よく対処できる。いったい、東京都はCO2を削減して、何を達成しようというのだろうか。
今こそ、みなが当たり前だと思い込んでいる「目的」を冷静に考え直すことが必要ではないか。目的が正しいとメディア、国民が思っている限り、行政による膨大な無駄遣いは続く。記者会見を聞いていて、そう気づいた。
なんと東京新聞が六月八日、「多額の税金を投入して見合う効果が出るのか疑問視する声も上がる」との見出しで、この問題を記事にした。太陽光の問題点として水没時の感電や廃棄時のコスト高に言及し、肝心の中国のジェノサイドへの依存や都民以外にも電気代アップのツケを回す点には触れなかった。とはいえ、会見の模様を写真付きで載せ、問題を提起した意義は高い。東京都庁の記者のほとんどは小池シンパと聞いていただけに、記者魂の一端を感じた。
【参考文献】
『目的への抵抗・シリーズ哲学講話』(國分功一郎著・新潮新書)
『ウイグル人に何が起きているのか』(福島香織著・PHP新書)
『在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイド』(ムカイダイス著・ハート出版)
『フェイクを見抜く』(唐木英明・小島正美共著・ウェッジブックス)