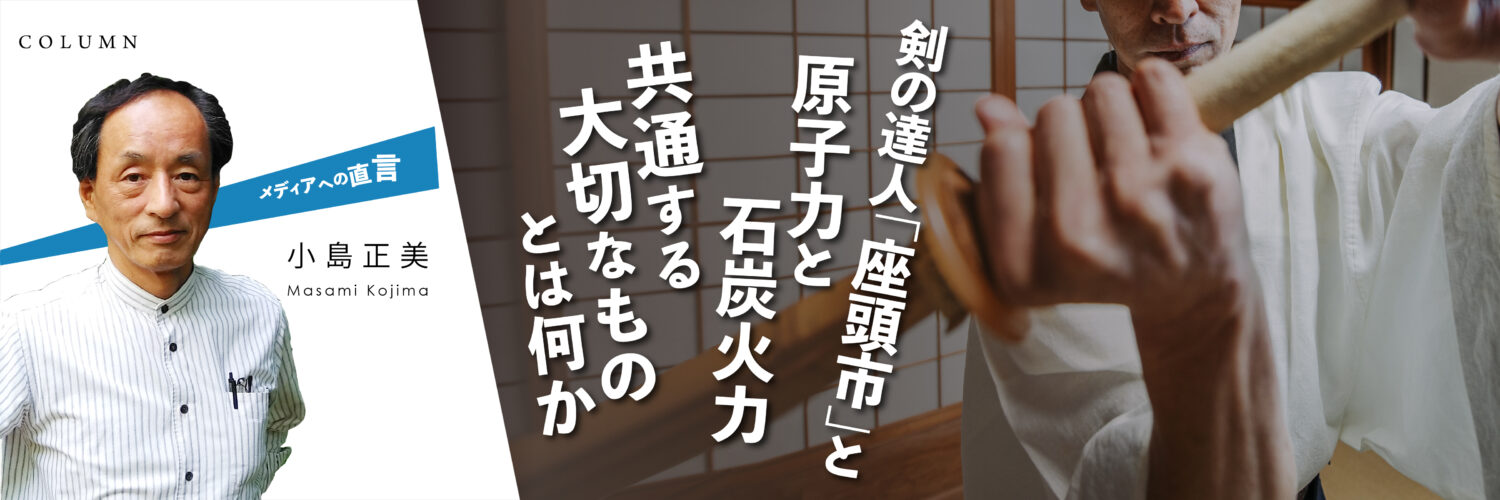剣の達人「座頭市」と原子力と石炭火力 共通する大切なものとは何か
二〇二五年三月十七日
NHKの大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』を見ている方はご存じだろうが、三月二日と九日に放送された第九話と第十話で、盲目の富豪である鳥山検校(男優は市原隼人さん)が、女優の小芝風花さんが演じる花魁「瀬川」を身請けするシーンが出てくる。なぜ、この話が原子力や石炭火力と関係するのか、私なりの考えを披露しよう。
座頭市は互助組織の身分だった
千四百両(いまなら一億四千万円らしい)もの身代金を払って、花魁の瀬川(実在した人物)を妻にした鳥山玉一(とりやまたまいち)検校とはいったい何者なのか。「検校」は「けんぎょう」と読み、官職の名称だ。実は、日本には室町時代から、「当道座」(とうどうざ)と呼ばれる男性盲人の自治的な互助組織があった。「検校」はこの互助組織の最高位の身分だ。
この互助組織は幕府から公認され、一定の自治を与えられて高利貸しなどを行っていた。鳥山検校はあくどい高利貸しで結局、幕府から処罰されてしまったようだが、おもしろいのは、剣の達人で知られる「座頭市」の「座頭」という名称も、この互助組織の官位だったということだ。頂点に立つ検校から順に別当、勾当、座頭など七十近い官位があったという。これらの官位によって、盲人たちは安定した地位と生計を保証されていたのである。
若いころ、映画で俳優の勝新太郎氏(故)が演じる「座頭市」をよく観て、その剣の達人ぶりに興奮したものだが、まさか「座頭」という言葉が互助組織の中の官位のひとつだとは思いもよらなかった。てっきり名前だと思っていた。
「当道座」は五百年間
邦楽作品を創作
この当道座という互助組織が、とてつもない文化遺産を残していたことを知ったのは、ちょうど一年前、指揮者で作曲家の森本恭正氏が著した「日本のクラシック音楽は歪んでいる」(光文社新書)という本を読んだときのことだ。この本には、検校のことをはじめ、驚くべきことが書かれていた。とても重要なので、やや長いが引用文(筆者で一部要約)を紹介する。
…日本の古典邦楽作品は、この当道座に在籍した盲人たちによってのみ作り出された。三味線、箏、胡弓、琵琶作品のほとんどは盲人たちによって作られたのだ。地歌も浄瑠璃も当道座の盲人たちが作った。十四世紀に障がい者による互助組織が日本に生まれていたこと自体、にわかに信じ難いが、事実だ。
そこでは、按摩、鍼灸のほか、琵琶、箏、三味線、胡弓などが教習されていた。この当道座を一教育機関と考えると、それはフランス革命前夜の一七八四年にパリで創設された世界初の盲学校よりも、四百年以上も前に設立されたことになる。初めてこの事実を知ったとき、私は茫然としてしばし動くことができなかった。日本の音楽が盲人たちによって作られてきた事実は、世界に類例がなく、音楽的にも驚嘆すべき事象である…
明治政府によって
あっけなく解体
この森本氏の引用文を読んで、みなさんはどう感じただろうか。世界に誇るべき盲人の互助組織が日本で五百年間も続いていたことに驚愕の念を覚えたのではないだろうか。恥ずかしながら、私は、この本を読んで初めてこういう盲人たちの組織があり、その盲人たちが邦楽のすべてを作っていたという事実を知った。
あれからちょうど一年たって、NHKの大河ドラマに検校が登場し、超裕福な検校がいたことも知り、改めて当時の盲人組織のすごみを感じた。
では、みなさんは、当道座がその後どうなったかご存じだろうか。
なんと、五百年も続いたこの互助組織が明治政府によってあっけなく解体されてしまったのである。すぐれた演奏家をかかえ、数百に上る邦楽作品を残してきた日本独特の組織が、明治政府の〝西欧崇拝〟の名のもとにいとも簡単に消えてしまったのだ。
著者の森本氏は同本で「ヨーロッパの四百年も前から、障がい者である盲人たちに為政者の手が差し伸べられていたのだ。外務省も、アニメの宣伝をする仕事の半分くらいの労を割いて、この点を世界に喧伝してもよいのではないだろうか」と述べているが、全く同感である。残念ながら、学校の授業ではこういう大事な事実を少しも教えてくれない。
日本はいまなお
西欧崇拝か
私が危惧するのは、西欧崇拝によって、日本の大事なものを捨ててしまうDNAがいまも日本の政府に生き残っているのではという恐れだ。
たとえば、農林水産省が二〇二一年に策定した「みどりの食料システム戦略」。二〇五〇年までのCO2ゼロエミッションを目指し、農地面積の二五%を有機農業にする方針だ。万が一、CO2がゼロ(不可能だと思うが)になったところで、価格が高く、収量の低い有機農産物では食料の安全保障にはならない。
不思議なことに、EU(欧州連合)は二〇三〇年までに農地の二五%を有機農業にする目標をたてている。日本も達成年度こそ異なるものの、同じ二五%という数値だ。なぜ、同じ数値なのかさっぱり分からない。そう思っていたら、解剖学者の養老孟子氏も同じ疑問を抱いたようだ。
養老氏と脳科学者の茂木健一郎氏、批評家の東浩紀氏の3人による鼎談をまとめた本「日本の歪み」(講談社現代新書)の第三章(維新と敗戦)に次のようなくだりがあった。
茂木氏 相手の価値基準に合わせ続けるというのはストレスですよね。
養老氏 日本は明治の頃からずっとそうですね。少し前に農林水産省の有機農業を推進するための会合に出席したのですが、そこで出てくる数値目標がすべて国際的な基準なんです。日本に住む人にとって必要な目標ではなく、外の基準に合わせるだけになっている。
この養老氏の話で分かるように、日本には日本独自の道があってしかるべきなのに、明治以降、何かにつけ「西欧に比べて日本は遅れている」といった図式の思考がいまも続いていることが分かる。
自国の技術に
無知なままでいると
石炭火力を例にあげてみよう。日本が誇る高性能の石炭火力発電は発電効率が高く、中国やインド、米国などにこの技術を導入すれば、日本の年間CO2排出量(約十億トン)よりも多い約十二億トンのCO2削減効果があるという。にもかかわらず、日本の大手金融機関までが西欧基準を信じ込み、日本の石炭火力を敵視している。
原子力はどうか。三菱総合研究所の「世界の原子力需要拡大で考える日本の使命」と題した解説(二〇二四年九月十七日)によると、日本は世界トップ3の規模を維持し続けてきた世界有数の原子炉部品の輸出国だという。原子力の安全に必要な高品質の重要部材を製造するモノづくり技術をもっているというのだ。
こういう自国の誇り高き技術に無知なままでいると、知らぬ間に西欧基準に飲み込まれ、気づいたら日本の驚嘆すべき技術が滅んでいたという事態になりかねない。世界に誇るべき盲人組織「当道座」の二の舞にならぬよう、自国が誇る技術を失わないようにしたい。