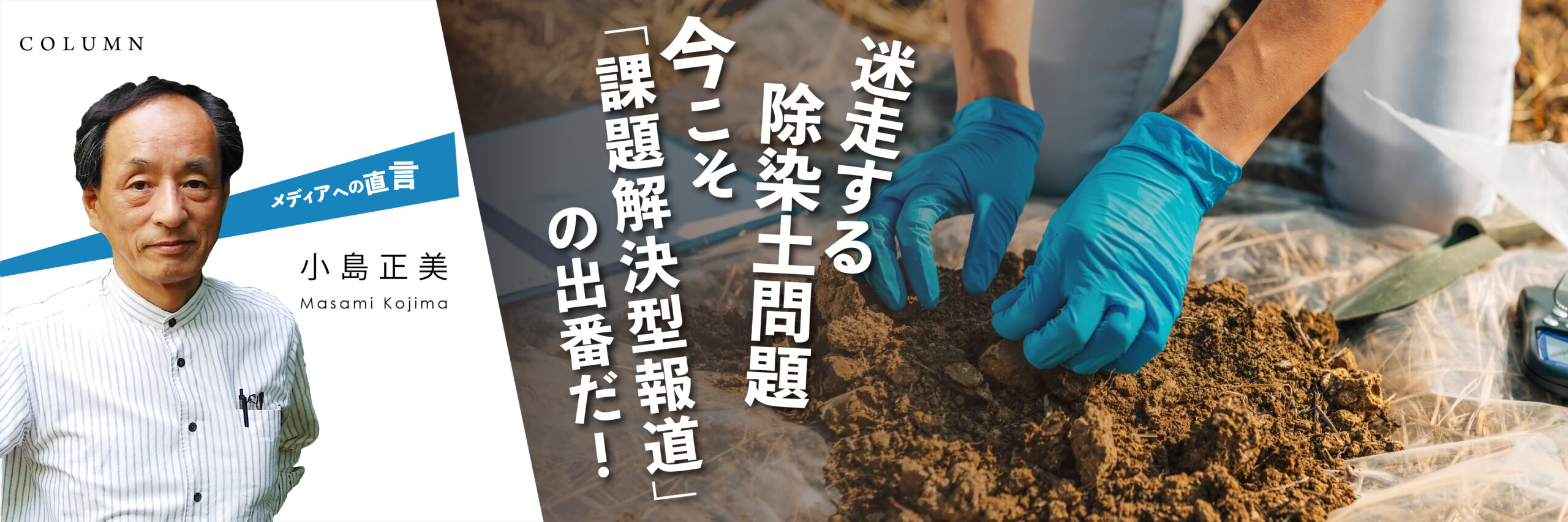迷走する除染土問題 今こそ「課題解決型報道」の出番だ!
二〇二五年四月三日
東京電力・福島第一原子力発電所事故で発生した除染土の再利用をめぐるニュースが目立ってきた。その中で中間貯蔵施設を抱える双葉町の伊沢史朗町長が町内で再利用を検討する考えを表明、停滞打破へ向けて大きな一石を投じた。いまこそ伊沢町長の勇気ある行動を結実させる「課題解決型報道」が必要ではないだろうか。
除染土の四分の三は
放射線量が低い
福島第一原子力発電所の事故では、放射性物質が周囲の住宅地や農地などに降り積もった。その除染作業で削り取られた土と草木がいま大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設に保管されている。その総量は東京ドーム約十一杯分の約一四〇〇万立方メートル。国は二〇四五年三月までに県外で最終処分する計画だが、同時に除染土の四分の三は放射線量が低いため、公共工事に再利用して除染土の総量を減らす方針も決めている。
国は二年前、再利用に向けて東京都新宿区と埼玉県所沢市で実証事業を進めようとしたが、住民の反対に遭い、頓挫してしまった。その後、表立った前進はない。
最終的には福島県外の処分地を確保するとしても、まずは最終処分量を減らすことが必要だ。だが、現状ではその入り口でつまずいている格好だ。
再利用とはどんなものか
つまずきの要因は何なのか。それには除染土の再利用事業がどのようなものかを知ることが先決だ。環境省は「中間貯蔵施設情報サイト」で再利用の具体案をイラストを交えて詳しく分かりやすく示している。それによると、コンクリートなどで被覆された道路や鉄道、防潮堤などの盛土、廃棄物処分場の覆土、海岸防災林の盛土や土堤、土砂で被覆された農地などに除染土を再利用する。
環境省は除染土の再生利用にあたっては、「放射能濃度が低い土を使用し、分別作業によって草木などの異物を取り除き、品質の良い土に再生してから利用する」と解説する。現に福島県飯舘村の長泥地区では、農地の盛土造成や花、野菜の栽培などを行う実証事業を進めている。そこで収穫される野菜の放射性物質の量は通常の食品と差がないことも分かっている。
再利用先が人の密集する住宅地ではなく、公共的な場所であれば、反対する合理的な理由は見つからず、どの自治体や住民もスムーズに受け入れてもよさそうに思うが、合意を得ることは簡単ではないようだ。
放射線量は
年間1ミリシーベルト以下
安全性の面はどうだろうか。仮に放射線による健康影響があるなら、反対運動が起きても当然である。しかし、再利用される土は一キログラムあたり八〇〇〇ベクレル(放射性セシウム一三四とセシウム一三七の合計)以下だ。これだと、仮にその土の上で長く作業をしたとしても、健康影響の管理指標値とされる年間一ミリシーベルト(この数値を超えたら健康影響が生じるという意味ではない)を下回る。
日本人は宇宙線や大地、ラドンの吸入や通常の食品から年間平均で二・一ミリシーベルトの自然放射線を浴びている。放射線は人工も自然も同じで、人への健康影響に差はない。日本国内だけでも地域によって線量に高低差があり、年間で最大一ミリシーベルトくらいの差があることを考えると、除染土による年間一ミリシーベルト以下の放射線量であれば、健康への影響はないとみてよいだろう。
私の住む千葉県北端部は、原発事故後に放射線量の高いホットスポットにあたり、事故後の数年間は一ミリシーベルトを超えていた。しかし、周りの住民は特に気にすることもなく生活していたことを思い出す。これと比べると、除染土を再利用した道路や盛土はその上に住むわけではなく、どう考えても健康影響は無視できるレベルだ。
この除染土の健康影響について、日本経済新聞は「CT検査を受けた場合に浴びるのは一回あたり十ミリシーベルト程度で、その十分の一ほどにとどまる」(二〇二五年三月三日付)と形容して報じた。こういう報道を見ても分かるように安全性の面ではクリアできそうだ。
今こそ必要な
課題解決型報道
ならば、もっとスムーズにことが運んでもよさそうだが、ここで重要になるのがメディアの「課題解決型報道」である。これは先進的な事例となる発言や専門家の提言を紹介しながら、課題を解決していく報道である。この報道には、記者たちが課題をなんとか解決したいと望む意欲と情熱が不可欠だ。
この点で注目したのは、毎日新聞が一面トップ(三月十七日付)で「除染土 停滞打開へ一石」の見出しで報じた記事だ。記事は、伊沢史朗・双葉町長が「県外に持って行ってと言うだけでは国民理解はなかなか進まない」としたうえで「双葉町内で除染土の再利用を考えている」との発言を報じた。毎日新聞は「覚悟を決めたように言った」と形容し、伊沢氏の覚悟が停滞打破の一石になるとの期待を込めた。
伊沢氏のこうした発言は2月下旬にあったことから、毎日新聞は社説(三月三日)で「首都圏などの自治体は、町長の発言をわがこととして重く受け止め、行動に移す時だ」と他の自治体の首長に向けてはっぱをかけた。
この除染土の問題はNIMBY(ニンビー)と似ている。ニンビーは“Not In My Back Yard”(うちの裏庭にはやめてくれ)の略語。ある施設をつくる必要性をだれもが認めていながら、「自分の庭や周辺はイヤだ」という例だ。そのイヤな役目を批判覚悟であえて引き受けた伊沢氏の行動は称賛に値する。であるならば、メディアはもっと伊沢氏の勇気ある熱情と意図を個別のインタビューで紹介し、他の自治体の首長に向けて「あなたたちは見て見ぬふりをしていてよいのか」と迫るくらいの記事がほしいが、そういう迫真の記事はほとんどない。
自治体の首長は
除染土再生事業を見学せよ
ただ、課題解決に向けた意欲を感じさせる記事もあった。読売新聞は三月十一日付朝刊で「除染土進まぬ理解」の見出しで全国の四十六知事に行った意向調査を載せた。新聞社自らが全国の知事に向けて「あなたは解決する気持ちをもっているのか」と尋ねて、知事の意向を調査した意義は大きい。
しかし、残念ながら、除染土の再利用について、「受け入れても良い」と答えた知事はゼロだった。山形、山梨、鹿児島、沖縄の四県は「容認できない」と答え、ほかは「どちらとも言えない」だった。最終処分場の受け入れについても、「条件次第で検討する意向がある」と答えた知事は秋田、千葉、兵庫、奈良、宮崎の五県にとどまった。
読売新聞は伊沢町長のインタビューも載せた。そこで伊沢氏は首都圏の自治体首長に対して次のように述べた。
「のど元過ぎれば熱さ忘れるで、自分の所の問題でなければ迷惑施設はいらないということだ。…福島で作った電力が首都圏で使われていたことを、今では忘れられたような気がする」。
この記事を受けて、読売新聞の社説(三月二十四日)は「地元だけに問題を押しつけず、全国の自治体で再利用に協力すべきではないか」と呼び掛けた。
義侠心(ぎきょうしん)とは、正義のために弱い者を助ける行動を言う。今後、伊沢町長の勇気ある行動を生かすも殺すも、自治体首長の義侠心、そしてメディアの報道いかんにかかっている。
現在、環境省は福島県飯舘村で除染土を再利用する環境再生事業を進めている。現状を知ってもらう見学会(連絡先は中間貯蔵事業情報センター)も実施している。少なくとも福島の電気を利用してきた首都圏の自治体首長全員は、一度は見学すべきだろう。