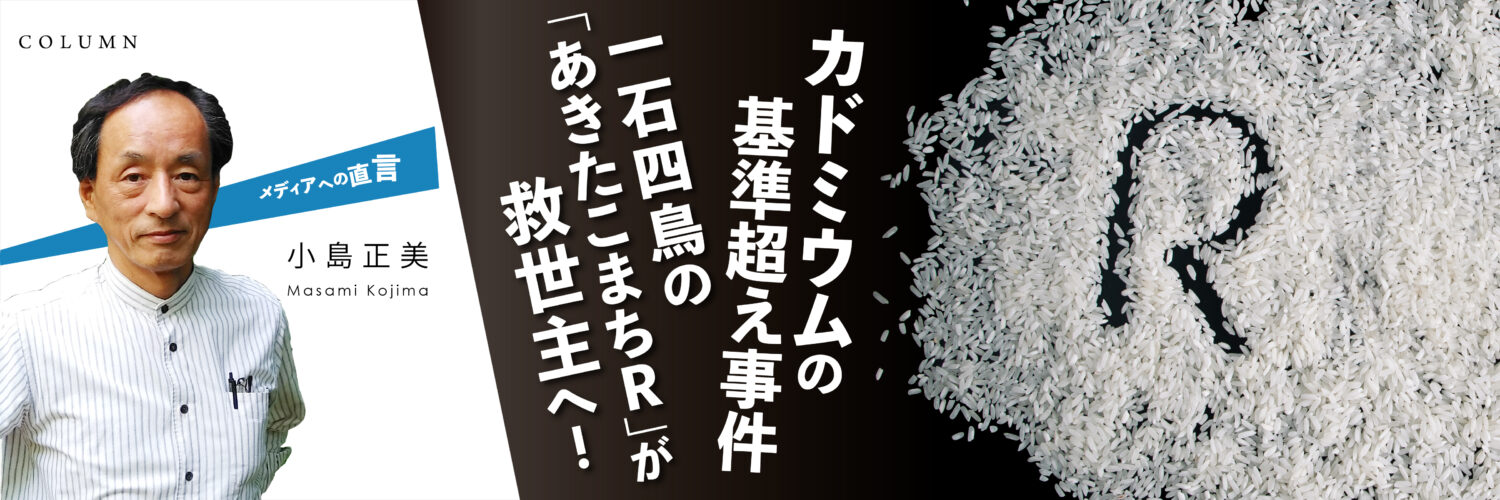カドミウムの基準超え事件 一石四鳥の「あきたこまちR」が救世主へ!
二〇二五年四月二十一日
四月上旬、秋田県内の農事組合法人が出荷したコメから基準値を超えるカドミウムが検出された。コメは首都圏の広範囲の店で販売され、自主回収が進む。こうした悲劇的事件を避ける救世主が、カドミウムをほとんど含まない画期的な新品種「あきたこまちR」だということを重ねて強調したい。これを大きく報じないのは、メディアの怠慢だろう。
基準超えは重大な失態
秋田県が四月四日に公表したリリースによると、農事組合法人・熊谷農進(秋田県小坂町)が出荷した約八六トンのコメの一部から食品衛生法で定められた基準値〇・四ppm(ppmは百万分の一の単位。一ppm=〇・〇〇〇一%)を超える〇・四七~〇・八七ppmのカドミウムが検出された。販売先は加工・卸売業者も含め、青森、茨城、埼玉、東京、神奈川、千葉など広範囲に及んだ。
基準超えのコメを知らずに販売した青森県の老舗米穀会社の社長は「裏切られた。農家の生産者として、全くプロ意識がなく、憤っています」(四月八日の青森朝日放送)と怒った。自主回収の対象となった数多くの販売店も同様の思いだろう。
基準超えのコメを一時的に食べても健康への影響はないが、今回の失態は「あきたこまち」のイメージ悪化につながる重大な事件だと認識したい。
小坂町はかつて鉱山の町
不思議なのは、この基準値超えを報じるメディアが、カドミウムをほとんど含まない「あきたこまちR」が登場すれば、今回のような悲劇的事件を避けることができるという事実に触れていない点だ。
コメに含まれるカドミウムは稲が土壌中から吸収したものだ。今回の事件で基準超えのコメを出荷した熊谷農進はカドミウムが高くなった原因について、「去年は水不足が発生し、田んぼに水が入っていない状況が続いた」(四月八日の青森朝日放送)と語っている。どの農家もカドミウムの吸収を抑えるために夏場に水をはるのだが、その湛水管理に失敗したというわけだ。
熊谷農進のある小坂町にはかつて小坂鉱山があり、周辺地域の土壌は他の地域に比べてカドミウムの濃度が高かった。一九七〇年代に土壌汚染対策地域に指定され、九〇年代に対策は完了していた。そうした苦い過去を考えると、生産者はより強い注意深さが求められていたのだが、ちょっとした油断が今回の悲劇を生んだといえる。
カドミウムとヒ素は
トレードオフ
ただ、生産者を責めるには酷な面もある。
首尾よく田んぼに水をはれば、確かにカドミウムの吸収は抑制されるが、逆に無機ヒ素の吸収は促進されてしまう。ヒ素はカドミウムと同様に国際がん研究機関(IARC)によるグループ分類で「発がん性あり」のグループ1に属する重金属だ。仮に湛水管理がうまくいっても、ヒ素が増えてしまうため、カドミウムとヒ素は相反するトレードオフの関係にある。
さらに言えば、田んぼに水をはると地球温暖化の原因となるメタンガスの発生量も増える。つまり、コメのカドミウムを低くしようとすると、ヒ素とメタンガスの両方が増えてしまうのだ。
日本列島を見渡せば、土壌中のカドミウムが高い地域があちこちにある。環境省によると、基準値を超えるおそれのあるカドミウムの土壌中濃度の高い地域(二〇二二年度)は秋田、富山、愛知、群馬、島根、福岡など九十七地域(面積約六七〇九ヘクタール)もある。
ではどうすべきか。結論を先に言えば、それを同時解決するのが「あきたこまちR」なのである。「あきたこまちR」なら、手間のかかる湛水管理が不要となるため、カドミウムが減るだけでなく、ヒ素もメタンも減らすことができる。そして、その先に日本人のコメを通じた健康リスクも低下する。つまり、カドミウムの吸収を抑制する新品種「あきたこまちR」はまさに一石四鳥の救世主なのである。
カドミウムとヒ素の
相対的リスクは高い
では、なぜ日本の記者たちはこのことをあまり報じないのだろうか。それはおそらく、記者たちが日本のカドミウムのリスクの現状をあまり知らないからだろう。この「あきたこまちR」に関しては、このコラムで過去に2回(「放射線を活用したコシヒカリの画期的な育種に反対運動 いまこそ放射線教育を!」、「汚染土の行方にも影響する『あきたこまちR』問題 いまは関ヶ原の戦いなり!」)書いているので重複する説明は省くが、日本人がコメから摂取しているカドミウムとヒ素による健康リスクは、食品中に残留していてよく話題になる農薬や食品添加物のリスクよりもはるかに高いという事実を知っておく必要がある。
もちろんコメを食べて危ないという意味ではない。日本人が平均的にコメから摂取しているカドミウムやヒ素の量は、健康影響の目安とされる耐容摂取量より低い(耐容摂取量の数分の一‘程度)ものの、農薬や食品添加物(許容摂取量の百分の一~千分の一程度)と比べると許容量に近いため、相対的なリスクが高いという意味だ。
日本人はカドミウムの約四~五割をコメから摂取している。天候に左右されず、土壌中のカドミウムをほとんど吸収しない形質をもった「あきたこまちR」の存在意義が高いのは、これでお分かりだろう。
自家採種は可能
こういう説明をすれば、どの消費者も「あきたこまちR」を食べたいはずだと思うが、残念ながら、それでも「あきたこまちR」を阻止しようとする反対運動が起きている。栽培意欲のある農家に対して、電話の抗議が来たり、「死ね」といったメールまで送られてくるケースがあるという。
反対派の主張の中に「県は一斉にあきたこまちRに切り替えるのではなく、従来の品種を栽培したいと思う個人の権利を守るべきだ」という声がある。確かに個人の選択を守ることは必要だろう。これに対して、県は「全農家に強制するものではない。従来の品種を希望する農家は自家採種してよい。県外産あきたこまちの種子を購入することも可能だ」と答えている。「あきたこまち」は品種登録されていないため、農家は自分で種子を採種(自家採種)できる。ならば個人の選択は守られているはずだ。
難しい表示の問題
二五年産米からは、従来の「あきたこまち」も新しい「あきたこまちR」も、「あきたこまち」として販売される。これに対して、反対派は「従来の品種とあきたこまちRの区別がつかないため、あきたこまちRと表示して販売すべきだ」と訴える。
この表示の問題はちょっと複雑な心境になる。私としては「あきたこまちR」を食べたいので、たとえば「あきたこまちR」が「しんあきたこまち」といったネーミングになれば、「しんあきたこまち」を選んで購入したい。従来の「あきたこまち」を避けたいからだ。
一方、カドミウムやヒ素の含有量が高くても、従来の「あきたこまち」を食べたい人もいるだろう。そういう意味では表示の区別があってもよいと考えるが、消費者に混乱をもたらす恐れもあり、「あきたこまち」(秋田産あきたこまちの大半は「あきたこまちR」なので)という統一表記でもよいかと思う。
乾田直播にも最適
今後、「あきたこまちR」が他県にも普及していくことを期待したいが、その理由は日本の稲作農業をさらに強くしたいという思いがあるからだ。カドミウムのコメの国際基準値は〇・四ppmだが、中国や香港、シンガポールは〇・二ppm、EU(欧州連合)は〇・一五ppmと日本より厳しい国もある。そういう国へコメを輸出する場合、カドミウムの基準値クリアーは必須要件だ。その意味からも「あきたこまちR」は優等生である。
さらに今後、日本の稲作では、田んぼに水をはらず、乾いた田んぼに直接、種子をまく乾田直播(かんでんちょくは)が増えていくだろう。この技術は育苗、代掻き、田植えという工程がなくなるため、大幅な省力化や低コストにつながる。そういう未来の稲作に対しても、「あきたこまちR」は大きく貢献できる。
知り合いの大手新聞記者に「なぜ、あきたこまちRの意義を記事にしないのか」と聞いてみた。すると「育種交配など問題が複雑で短めに分かりやすく書くことが難しい」との返答が返ってきた。難しいことを分かりやすく記事にするのが記者の仕事だ。記者の矜持をぜひ見せてほしい。