第58回 原産年次大会「会長挨拶」
一般社団法人 日本原子力産業協会
場所:東京国際フォーラム
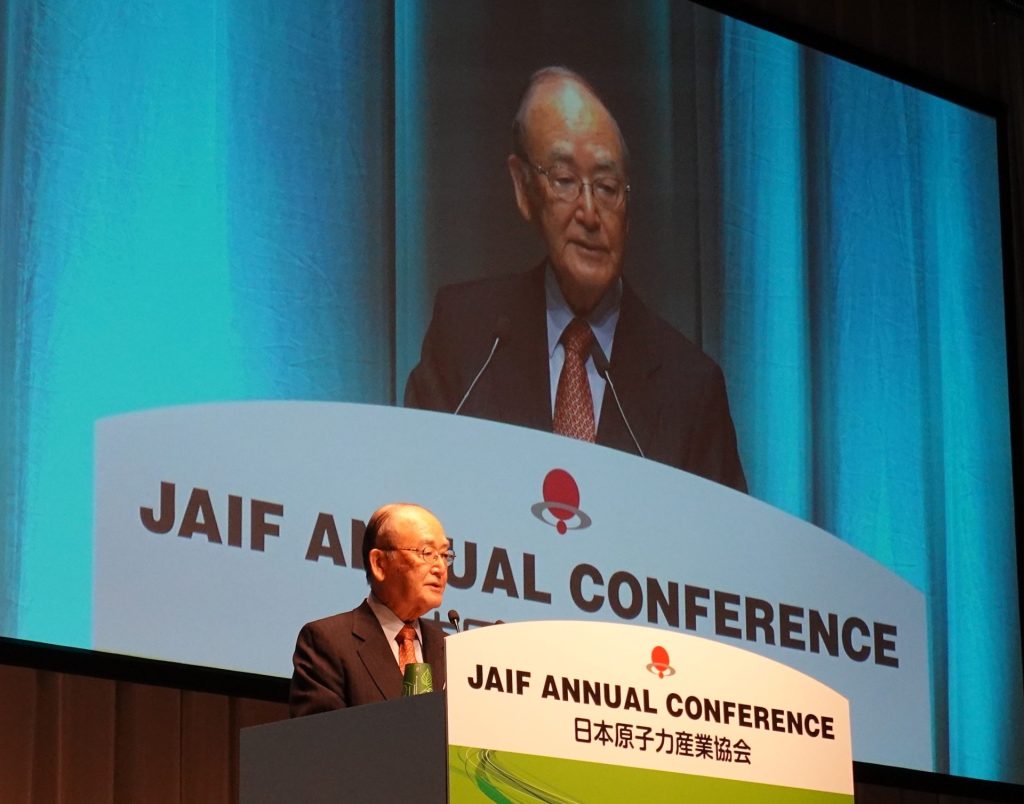
日本原子力産業協会会長の三村でございます。第58回原産年次大会の開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
まず、今大会にご参加いただきます740名の皆さまに、心より感謝申し上げます。また、お忙しい中、ご登壇いただく皆さまにも、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
前回年次大会からの1年を振り返りますと、世界では原子力活用のモメンタムがますます拡大しております。昨年3月には、ブリュッセルで史上初となる「原子力に特化した首脳会議」が開催されました。また、COP28で発表された「原子力三倍化宣言」の署名国は、昨年のCOP29で新たに6ヵ国が加わり、計31ヵ国となりました。
この動きを後押しするように、昨年9月には、世界有数の金融機関14社がファイナンス支援を表明したほか、本年3月には、大手IT企業など14社が、同宣言を支持する誓約書に署名しております。
国内でも、重要な前進がありました。昨年11月、青森県むつ市において、国内初の使用済燃料中間貯蔵施設であるリサイクル燃料貯蔵株式会社の「リサイクル燃料備蓄センター」が事業を開始しました。この施設は、原子力発電事業に柔軟性をもたらすものであり、大きな意義を持つものであります。
また、同じく11月に東北電力の女川2号機、12月には中国電力の島根2号機が、それぞれ再稼動を果たしました。これにより、再稼働したプラントは合計14基となり、待望の沸騰水型軽水炉2基の再稼働が実現したことは、大きな前進といえます。
さらに、本年2月18日には、第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました。これまでの「原子力依存度低減」に代わり、「原子力の最大限活用」が謳われたことは、私たち原子力産業界にとって極めて重要な前進であります。
また、次世代革新炉の開発・設置に取り組むとして、新規建設の方針も示されました。あわせて、資金調達・投資回収の予見性を高める事業環境の整備や、サプライチェーンや人材の維持・強化を進めることも明記されています。
こうした政府の原子力政策の前進は、産業界にとって大変意義深いことであります。
しかし、政策を現実のものとするためには、私たち産業界が、果たすべき役割をしっかりと果たしていかねばなりません。そのための不断の努力と準備が、今、求められています。
特に、新規建設の具体化・早期実現は、原子力の持続的かつ最大限の活用のため必要不可欠であると同時に、産業界が直面する諸課題を解決するうえでの鍵でもあります。
我々は、足下の電力の安定供給に責任を持っていると同様に、2040年、2050年といった将来の電力の安定供給にも責任を持っています。
こうした認識から、今大会のテーマは「新規建設の実現に向けて」といたしました。
この二日間の大会では、新規建設の早期実現に向けた実効性ある事業環境の整備を念頭に、国内外産業界の取り組みと課題解決の方向性について議論を進めます。
また、福島の地元関係者の皆様から復興への取り組みをご紹介いただき、将来を担う若手世代と原子力産業の未来を展望する機会といたします。
本日午後のセッション1と2では、新規建設に向けて、「資金調達と投資回収」と「サプライチェーンの課題」について取り上げます。新規建設を経験している海外から専門家にもご登壇いただき、わが国の専門家と共に活発な議論を行います。
福島第一原子力発電所事故の教訓と反省は、私たち原子力産業界が事業を進めていくうえでの原点であります。明日午前のセッション3では、「廃炉と復興の両立」をテーマに、廃炉に向けた取り組みの進捗と、地元である浜通り地区に居住し、復興に尽力されている方々の声を伺います。地域の課題や展望を共有し、原子力業界へのメッセージを受け取る貴重な機会となることを願っております。
総合科学技術である原子力は、脱炭素と持続可能な社会を高度かつ幅広い技術で支える事業であり、若者たちに夢を与えると同時に、若者たちの参加が不可欠な事業です。
セッション4では、国内外でご活躍する若手技術者と学生の皆さんにご登壇いただきます。新規建設が拓く原子力産業の未来について語り合い、原子力が夢とやりがいに満ちた、魅力的な仕事であることを発信してまいります。
今回の大会では、リレー方式の「バトンスピーチ」や、ざっくばらんな対話を促す「ファイヤーサイドチャット」を取り入れました。さらに、大手IT企業の方に初めてご登壇いただくなど、これまでにない新たな視点と議論の場を創出しております。
最後になりますが、第7次エネルギー基本計画のもと、原子力を持続的に最大限活用していく鍵は「新規建設」です。
この二日間の議論が、新規建設実現への諸課題の解決につながることを期待し、わたくしの開会挨拶とさせていただきます。
ご清聴、ありがとうございました。
以上
お問い合わせ先:企画部 TEL:03-6256-9316(直通)