キーワード:SMR
-

スウェーデンと韓国 SMRプロジェクトで提携
スウェーデンで小型モジュール炉(SMR)の建設を計画するシャーンフル・ネキスト(KNXT)社は、12月5日に韓国・ソウルで開催されたスウェーデン・韓国戦略産業サミットにおいて、韓国の建設大手のサムスンC&T社(サムスン物産)と協力覚書(MOU)を締結した。KNXT社はこのパートナーシップを、脱炭素エネルギー源の拡大を目的に、スウェーデン南部で実施する小型モジュール炉(SMR)開発を加速・強化する「Re:Firm South SMR」プログラムの一環に位置づけている。韓国のサムスンC&T社は、アラブ首長国連邦(UAE)のバラカ原子力発電所の建設プロジェクトに参画。また、2023年6月にルーマニア国営原子力発電会社のニュークリアエレクトリカ(SNN)と同国南部ドゥンボビツァ県のドイチェシュテイ(Doicesti)におけるSMR建設を目指して、建設プロジェクトの基本設計(Front-End Engineering Design:FEED)に共同参画している。KNXT社は、サムスンC&T社の最新の建設工法や設計、ライセンス、資金調達に関するノウハウを自社プロジェクトへ活用させたい考えだ。KNXT社は、スウェーデン南東部のバルデマーシュビークとニュヒェーピングの両自治体を建設候補地として予備的な実行可能性調査(FS)を実施している。両社は、今回のMOU締結により、炉型選定、環境影響評価など、SMR発電所建設へ向けた作業に直ちに着手する予定だ。スウェーデンは脱原子力政策を撤回し、大規模な原子力発電開発に向けて大きく舵を切っている。2022年の総選挙によって誕生した中道右派連合の現政権は、40年ぶりに原子力を全面的に推進しており、2023年11月には、原子力発電の大規模な拡大をめざすロードマップを発表。同ロードマップには、2035年までに少なくとも大型炉2基分、さらに2045年までに大型炉10基分を新設することなどが盛り込まれている。最近では、米国のMicrosoft社やAmazon社などの大手IT企業がスウェーデンにデータセンターを増設するという計画を発表。スウェーデン政府はSMRをはじめとする原子力発電所を建設し、データセンターに必要な電力供給を計画している。KNXT社とサムスンC&T社はこの機を捉え、2032年までにSMR発電所を建設、電力購入契約(PPA)を通じて、信頼性の高いクリーンな電力をデータセンターなどのエネルギー集約型施設に直接供給する事業モデルを検討している。今後も多数の発電所を建設し、同時にデータセンターの持続的な誘致を構想する。サムスンC&T社は今回のスウェーデン市場での協業を通じて、欧州市場でのSMR事業の一層の拡大をねらっている。
- 17 Dec 2024
- NEWS
-

次世代炉導入に向け各国が協力体制を構築
SMRなどの革新的な原子炉の導入に向け、各国が協力体制を構築している。このほど米国はリトアニアと政府間協定を、英国はフィンランドと協力覚書を締結した。米エネルギー省(DOE)のJ. グランホルム長官とリトアニアのD. クレイビス・エネルギー相は11月26日、米国のワシントンで、リトアニアの民生用原子力発電プログラムの開発に協力する政府間協定を締結した。同協定は、特に第4世代小型モジュール炉(SMR)のリトアニアへの導入に焦点を当てた、米国初となる政府間枠組み。米国は、リトアニアと次世代炉開発における知見を共有するとともに、第4世代のSMRのビジネスモデル分析と開発可能性評価を実施し、リトアニアが掲げる2050年までのネットゼロ達成目標を支援する。リトアニアは、2025年2月に同国を含むバルト三国がロシアの電力網から完全に切り離され、欧州の電力網に接続する予定で、欧州域内でエネルギー輸出国としてシェアを拡げたい考えだ。協定ではSMR導入に係る協力に加えて、リトアニアにおける最高水準の安全とセキュリティの促進や民生用原子力施設の核物質防護・セキュリティの強化のほか、廃止措置、燃料管理、人材育成に係るベストプラクティスなどを協議する専門家交流も想定している。グランホルム長官は「安全、クリーンで信頼性の高い原子力エネルギーは、リトアニアのエネルギー政策上のカナメとなる」と強調。クレイビス・エネルギー相は、「リトアニアの増大するエネルギー需要を満たし、ネットゼロ目標の達成のため、米国の次世代炉開発の知見に期待している」と述べるとともに、リトアニアの地政学的な安全保障、長期的な経済成長、技術力向上にも資する、本協定の意義を強調した。リトアニアでは、イグナリナ原子力発電所(軽水冷却黒鉛減速炉:RBMK-1500×2基、各150万kWe)が1980年代から稼働していたが、欧州連合(EU)は、チョルノービリと同型であるRBMK炉の安全性への懸念から閉鎖を要求、リトアニアはEU加盟と引き換えに同発電所を2009年までに閉鎖した。イグナリナ原子力発電所近傍のヴィサギナスに日立製作所が主導する新規原子力発電所プロジェクトも浮上したが、福島第一原子力発電所の事故により、原子力発電に対する国民の支持は低下。2012年の同プロジェクトへの支持を問う国民投票では、新規建設に対する否定的な意見が優勢となり、計画は2016年に凍結された。リトアニアの総発電電力量は約57億kWh(2023年実績)で、その内、約73%を再生可能エネルギー(風力、太陽光、水力)、約11%を火力発電(天然ガス)が占める。現在の電力消費量は約120億kWh。エネルギー部門の脱炭素化と電化には大量の追加電源が必要であり、2050年代には約6倍の740億kWhへの増大を予想する。そのため、エネルギーシステム全体の均衡を保ち、再生可能エネルギーへより多く投資することを可能にするSMRの導入を推進したいとし、2028年にはSMR建設の決定を目指している。 英国はフィンランドと一方、英エネルギー安全保障・ネットゼロ省(DESNZ)とフィンランド経済雇用省は11月18日、民生用原子力エネルギー分野における協力覚書(MOU)を締結した。協力の対象分野は、SMRや先進モジュール炉(AMR)のような革新技術の導入、既存・新設炉を対象とした燃料供給の多様化、SMRやAMRの効率的な導入に係わる規制組織間の意見交換、資金調達、使用済み燃料最終処分を含む放射性廃棄物管理と廃炉、原子力安全とセキュリティ、人材育成など。これらの分野で知見やベストプラクティスを共有し、両国の産官学の政策・技術・学術関係者の交流や、民間企業間の緊密な協力によるビジネスの機会の促進を図る。両政府は、SMRやAMRなどの新原子力技術が、エネルギーセキュリティと気候変動の双方に革新的な解決策となる可能性を認識。発電だけでなく、熱生産および水素製造、その他の非電力用途の原子力技術の研究開発でさらに協力する機会を模索したいとしている。今回のMOUにより、英国の輸出信用機関である英国輸出信用保証局(UKEF)は、英国の商品やサービスを購入するフィンランドを拠点とするプロジェクトに対し、最大40億ポンド(約7,600億円)の融資支援が可能となる。UKEFは、英国製SMRのフィンランドへの導入を念頭に置いている。フィンランドの輸出信用機関であるフィンベラ(Finnvera)も、フィンランドの商品やサービスを購入する英国を拠点とするプロジェクトに対して同様に資金提供が可能になるという。
- 04 Dec 2024
- NEWS
-
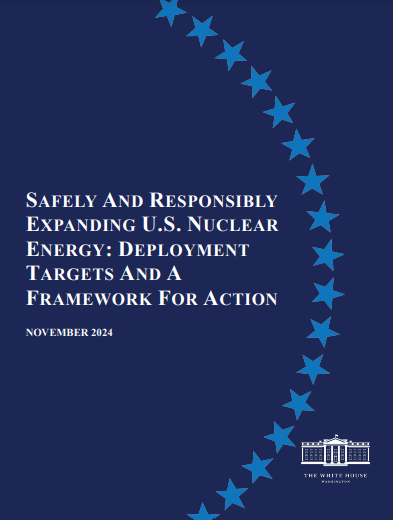
米政府 2050年原子力3倍化に向けたロードマップを発表
ホワイトハウスは、アゼルバイジャンのバクーにおける第29回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP29、11月11日~24日)会期中の11月12日、今後の同国の原子力発電拡大に向けた目標と行動を示した「米国の原子力を安全かつ責任を持って拡大する:展開目標と行動に向けた枠組み(Safely and Responsibly Expanding U.S. Nuclear Energy: Deployment Targets and a Framework for Action)」を発表した。同資料によると、米国が2050年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするためには、出力規模でおよそ15億~20億kWのカーボンフリー電力が必要であり、このうちの約30~50%は原子力発電などのクリーンで安定した電源が必要、と分析。現在約1億kWが運転中の原子力発電については、2050年までにさらに2億kWを新規導入する目標を掲げ、これらを大型炉や小型モジュール炉(SMR)、マイクロ原子炉のさまざまなカテゴリーの、第三世代+(プラス)および第四世代原子炉の新規建設や既存炉の運転期間延長、出力増強、経済性を理由に閉鎖された原子炉の再稼働などでまかなうとしている。米政府はまた、より近い将来の目標として以下の、導入に向けた「時間軸」と「規模感」も併せて明記した。2035年までに3,500万kWの新規設備容量を稼働または着工し、原子力導入を活発化させる。2040年までに導入のペースを年間1,500万kWに拡大し、原子力導入能力を加速、国内外のプロジェクト展開を支援する。これらをふまえ米政府は、野心的な導入目標の達成に向け、国内の原子力導入を加速、拡大するための「9つの分野((①新規大型炉の建設、②SMRの建設、③マイクロ原子炉の建設、④許認可の改善、⑤既存炉の延長/拡大/再稼働、⑥労働力の育成、⑦コンポーネントサプライチェーンの開発、⑧燃料サイクルサプライチェーンの開発、⑨使用済み燃料管理))」を特定、個々の分野における「具体的な行動」を詳述した。具体的には、「新規大型炉の建設」や「SMRの建設」の分野では、①発電事業者に対する技術中立的クリーン電力生産税額控除とクリーン電力投資税額控除など、税額控除による原子力納入コストの削減、②エネルギー省(DOE)融資プログラム局(LPO)による、革新原子力プロジェクトや、閉鎖された化石燃料発電所を原子力発電所に転換するような、資産・インフラ転換への融資や融資保証の促進、③新規プロジェクトに対して電力会社とリスク分担が可能な電力需要顧客との連携――などを挙げた。そのほか、「既存炉の延長/拡大/再稼働」の分野では、2回目の運転認可更新(80年運転)申請に係る審査の効率化や、構造材料の継続的な健全性確保のための研究など、100年運転に向けた長期運転への備えを挙げている。さらに、経済性を理由に閉鎖した原子炉の再稼働の可能性を追求するなどとしている。
- 25 Nov 2024
- NEWS
-

ポーランド企業 加企業とSMR導入に向けた調査を実施
ポーランドのオーレン・シントス・グリーン・エナジー(OSGE)社は11月14日、ワルシャワで加ローレンティス・エナジー・パートナーズ社と、ポーランドにおける初の小型モジュール炉(SMR)の開発と導入に向けて、予備安全分析報告書(Preliminary Safety Analysis Report:PSAR) の作成支援に係る契約を締結した。契約額は最大4,000万加ドル(約44億円)。今回の契約は、OSGE社がポーランドで導入を検討している米GE日立・ニュクリアエナジー(GEH)社製SMR「BWRX-300」建設の安全性の実証が目的。PSARは、ポーランドの原子力規制当局である国家原子力機関(PAA)が、建設許可申請の一環で要求する包括的な安全性分析報告書で、PSARの作成は許認可手続きにおいて最重要作業の一つである。PSARでは、提案されている原子炉のシステム、構造、機器の一般的な設計側面と詳細な説明の両方を提示。建設準備と管理体制、環境や地域の状況、原子燃料管理を含む発電所の運転期間のほか、廃炉プロセスの説明も含んでいる。ローレンティス社は、環境条件、サイト特性、施設の建設、運転、将来の廃止措置に関する資料作成を担当。OSGE社は、BWRX-300発電所の所有者兼運転者として、分析のためのデータの準備や進行中の作業のマネジメントを担当する。今後2年をかけてPSARを作成し、2026年半ばに完成する予定。OSGE社はまた、GEH社からもPSAR作成の支援を受け、GEH社はBWRX-300の設計者として、技術面および安全関連の分析を担当する。OSGE社は、ポーランドへのBWRX-300導入のため、大手化学素材メーカーであるシントス社(Synthos SA)のグループ企業シントス・グリーン・エナジー(SGE)社と最大手の石油精製企業であるPKNオーレン社が50%ずつ出資し、2022年に設立された合弁企業。2023年12月に気候環境省から、国内6地点における合計24基のBWRX-300建設計画へ原則決定が発給され、OSGE社は現在、許認可手続きの準備を進めている。一方、ローレンティス社は、加オンタリオ・パワー・ジェネレーション(OPG)社の100%子会社で、プロジェクト管理、許認可、運転準備、運転員支援などで、60年の経験とノウハウを有する。OSGE社に対しては2022年以降、SMRの導入に向けた初期的な計画立案などを支援しており、OPG社のダーリントン・サイトにおけるBWRX-300建設プロジェクト支援の実地経験を活用できるのが強み。OPG社は、2029年にBWRX-300初号機の稼働を計画している。OSGE社のR. カスプロウ会長は、「今回締結された契約は、これまでの一連の契約を締め括るもの。建設許可申請の重要要素であるPSARの作成にあたり、OPG社の一部であるローレンティス社との契約により、カナダの知識とノウハウを最大限に活用できる」と語り、両社間の協力への期待を滲ませた。「BWRX-300」は電気出力30万kWの次世代原子炉のBWR。2014年に米原子力規制委員会(NRC)から設計認証(DC)を取得したGEH社の第3世代+(プラス)炉「ESBWR(高経済性・単純化BWR)」をベースにしている。
- 22 Nov 2024
- NEWS
-

経産省 ポーランドの原子力開発に向け政府間覚書
日本とポーランドにおける原子力分野での協力が進展している。経済産業省の竹内真二大臣政務官は11月3~9日、エネルギー関連企業など、計23社とともに、ルーマニアおよびポーランドを訪問。7日のポーランド訪問では、マジェナ・チャルネツカ産業相と会談し、原子力分野を中心に、両国間の協力可能性について議論した上で、覚書への署名がなされた。〈経産省発表は こちら〉会談には日本企業も同席。2040年までのポーランドのエネルギー政策に従い、同国におけるSMR(小型モジュール炉)を含む原子炉の開発・配備を通じて、「強固で強靭な原子力サプライチェーンを構築する」など、相互にとって有益な協力分野を開拓していく。ポーランドでは、石炭火力発電への依存度が高く、排出ガスに起因した酸性雨などの環境影響が深刻な問題だ。そのため、エネルギーセキュリティ確保と環境保全の両立に向けて、同国政府は、原子力発電の導入を目指し、2043年までに大型軽水炉を6基導入する計画。2022年11月には、大型炉の米国WE社製AP1000を3基建設することを正式決定。また、産業振興も視野にSMR導入を目指す動きもみられている。既に2024年5月、東芝エネルギーシステムズと地元企業との間で、蒸気タービンや発電機の供給協業で合意に至っており、民間企業レベルでの協力も進みつつある。今回の覚書のもと、日本とポーランドは、人材育成、理解促進、原子力安全確保の分野で、情報交換、セミナー・ワークショップ、企業間マッチングなどの活動を実施。国際的基準・勧告に沿った放射性廃棄物管理・廃炉など、バックエンド対策も含めて、原子力発電導入に向けた理解活動に取り組んでいく。なお、日本によるポーランドへの原子力・放射線分野の協力は、エネルギー分野のみにとどまらず、これまでも、IAEAによる支援のもと、電子線加速器を利用した排煙脱硫や、その副産物として肥料生産も行われるなど、環境保全・食料安全保障の分野での実績も注目される。
- 12 Nov 2024
- NEWS
-
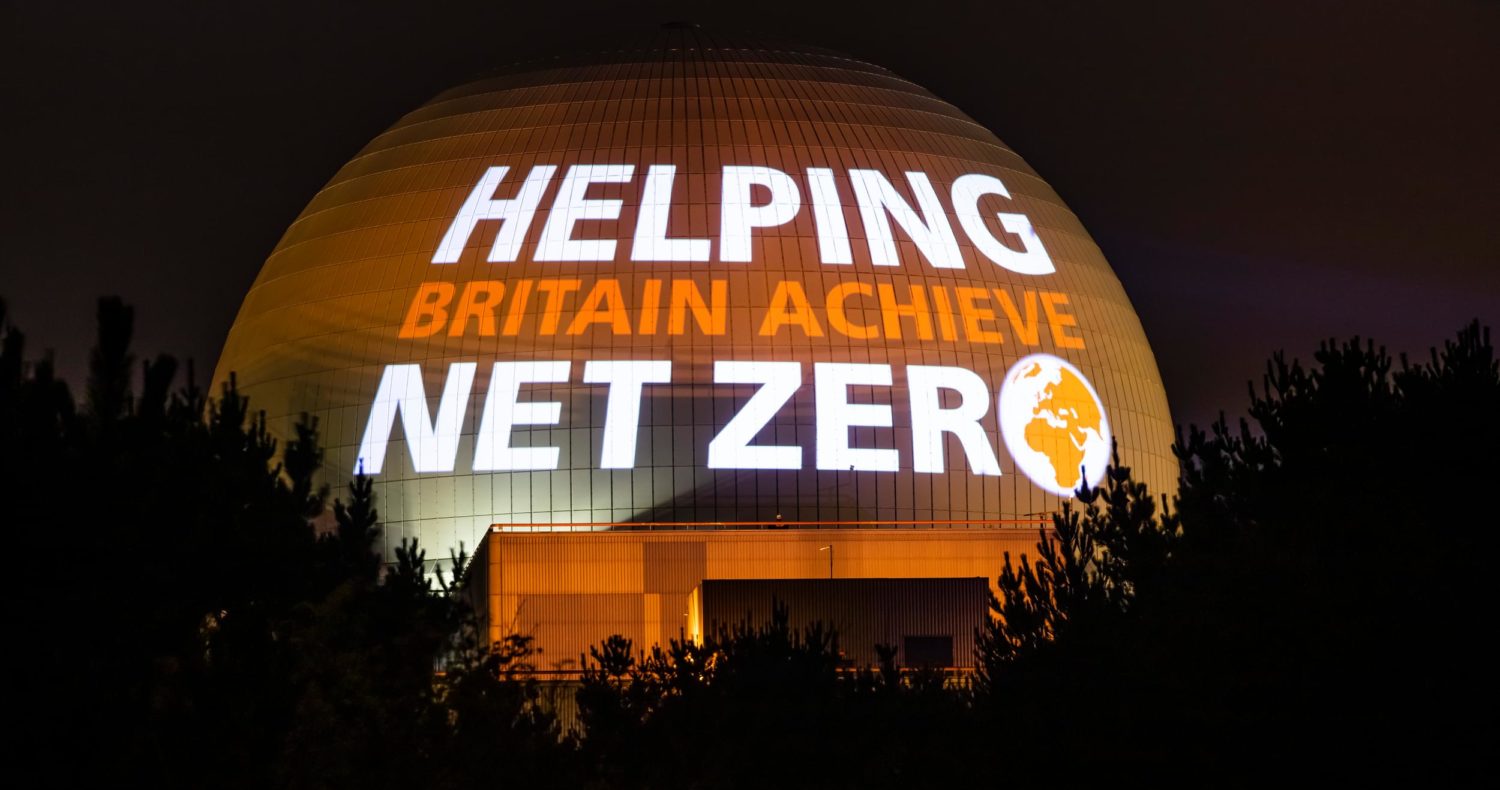
英国 SZCの最終投資決定とSMR支援対象炉決定を来春実施
英政府は10月30日、新政権として初の秋季予算案を発表。同予算案の中で、英サイズウェルC(SZC)原子力発電所新設プロジェクトの最終投資決定とSMR支援対象炉の決定を来年春に実施すると言及している。英政府(前政権)は今年1月、2050年のCO2排出実質ゼロに向けて原子力ロードマップを発表。2050年までに国内で合計2,400万kWの新規原子力発電所を稼働させ、国内電力需要の4分の1を原子力で賄うとする野心的な原子力開発目標を示した。今回の予算案の中で、新規炉は英国がエネルギー安全保障とクリーンエネルギーを実現する上で重要な役割を果たすとともに、何千もの熟練労働者の雇用を約束するものであると明言。SZCプロジェクトの継続のため、2025年~2026年にかけて、27億ポンド(約5,343億円)の予算を計上している。同プロジェクトはイングランド東部サフォーク州のサイズウェル原子力発電所サイトにEPR-1750(172万kWe)を2基建設する計画。2022年7月に開発合意書(DCO)、2023年3月に環境許可、今年5月にはサイト許可がそれぞれ発給されており、現在、サイト内の土木工事が進行中だ。なお、同プロジェクト向けの資金調達プロセスはまもなく最終段階に入り、春には完了する見通しだとし、同プロジェクトを進めるかどうかの最終投資決定(FID)を歳出見直し(Spending Review)の第2段階(来春)で実施するとしている。同予算案ではまた、大英原子力(Great British Nuclear:GBN)が実施している小型モジュール炉(SMR)の支援対象選定コンペについて、最終選考に残った4社と交渉段階に入ることを明らかにした。最終選考に残ったのは、米GE日立・ニュクリアエナジー・インターナショナル社、米ホルテック・インターナショナル社英法人、英ロールス・ロイスSMR社、米ウェスチングハウス(WE)社英法人。GBNは10月にこれら4社に対して交渉への招請状を発行。交渉の終了後、4社は最終入札の提出を求められ、GBNはそれを評価し、支援対象炉の最終決定を来年春に行うという。当初、今夏には選定企業との契約締結を計画していたが、遅延している。なお、GBNは10月28日に発表した商業活動の見通し(Commercial Pipeline)の中で、支援対象に選定された各SMR供給者への契約額を10年間で推定6億~8億ポンド(約1,187億~1,583億円)と見積り、調達開始予定は2025年7月、契約開始予定は2026年9月と設定。原子炉蒸気供給系(NSSS)以外の系統(Balance of Plant:BOP)の製造、供給、設置に関する別の2億ポンド(約396億円)の契約については、調達開始を2028年、契約開始を2030年と設定している。英国原子力産業協会(NIA)のT. グレイトレックスCEOは、「英国のSMR支援対象選定コンペがこれ以上遅れることなく、できるだけ早く決定を下すことが重要である。SMRへの支援に関する英政府の声明に対する信頼は、今回の約束を果たすことにかかっており、サプライチェーンの信頼だけでなく、野心的な原子力拡大目標を達成するためにも不可欠である」と指摘した。
- 11 Nov 2024
- NEWS
-

韓国 慶尚南道でSMR国際会議を開催
韓国南東部の慶尚南道(キョンサンナムト)は10月22日、「SMRの未来:世界が問う、慶南が答える」と題して、小型モジュール炉(SMR)に関する国際会議を昌原市で開催した。世界のSMR開発企業と韓国国内の原子力関連企業、研究機関によるSMRの設計・製造技術の開発状況の共有や、慶尚南道におけるSMR製造クラスターの育成を目的に開催されたもので、国内外の原子力関連企業や 研究機関など300名以上が参加した。冒頭、開会挨拶の中でパク・ワンス(朴完洙)慶尚南道知事は、「昨今の人工知能(AI)、ビッグデータのような先端産業の急速な発展により、世界的に電力需要が増大する中、持続可能かつ無炭素電源となるSMRが注目されている」と指摘。慶尚南道が昨年6月に策定した原子力育成総合計画により、SMR技術開発など原子力産業の育成に2032年までに2.6兆ウォン(約2,800億円)を投資することに触れ、「慶尚南道は名実ともにSMR産業のグローバルセンターとしての役割を果たすだろう」と展望した。開会式後、慶尚南道は、ナトリウム冷却高速炉(Natrium)を開発する米テラパワー社、ならびに小型熔融塩炉(CMSR)を開発するデンマークのシーボーグ社とそれぞれ、SMR部品やコンポーネントの設計と製造、道内における研究開発(R&D)センターの設立に向け、協力協定を締結。先進炉開発企業との協力により、道内における原子力関連企業の次世代原子炉技術の競争力強化のほか、技術開発への参加機会の創出を狙う。また、OECD・NEAのB. ルイアー局長と韓国原子力学会のチョン・ボムジン(鄭釩津)会長も出席、基調講演を行った。続いて海外セッションでは、先述のテラパワー社とシーボーグ社のほか、米ニュースケール・パワー社、米X・エナジー社、加アトキンス・リアリス社など、世界でSMR開発をリードする企業がそれぞれの技術開発や事業の現状を紹介。一方、韓国からは、韓国水力・原子力(KHNP)、韓国原子力研究院(KAERI)、斗山エナビリティ(旧斗山重工業)、道内の原子力関連企業であるBHI社が、海外の多様なSMR設計開発に対応して国内で推進する設計・製造技術開発の現況などについて発表した。翌23日には、これらSMR企業関係者が道内の原子力関連企業の斗山エナビリティ、JinYoung TBX社(タービン翼製造)、PKバルブ社、 BHI社(排熱回収ボイラー製造)を視察。SMR製造クラスター形成に向けた、道内企業の技術力を現場で直接確認し、将来の設計、製造、国際共同研究協力、原型炉製造などへの投資について話合いが行われた。
- 01 Nov 2024
- NEWS
-
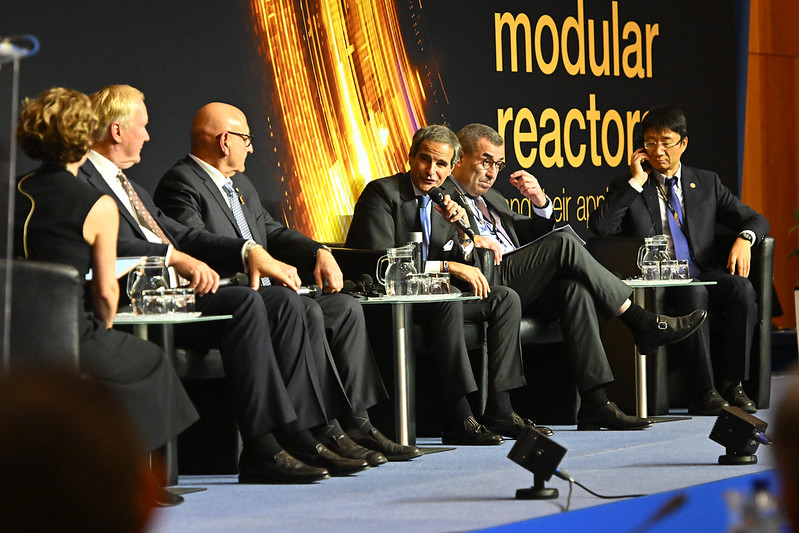
IAEA SMRに関する初の国際会議を開催
国際原子力機関(IAEA)が主催する小型モジュール炉(SMR)とその応用に関する初の国際会議がウィーンで10月21日~25日に開催された。SMRのサプライヤーや規制関係者など約100か国から1,000人以上が集まり、世界のSMR活動を評価し、新たな課題と機会について議論した。IAEAは同会議を、大手テック企業から海運業界や鉄鋼業界まで、脱炭素化の目標達成を目指すあらゆる企業にとって、SMRをあらゆる角度から検討するのに最適な場と位置付けている。会議冒頭、R. グロッシー事務局長は「SMRは原子力において、最有望で、エキサイティングで、必要とされる技術開発の一つであり、現実なものになりつつある。クリーンエネルギーの未来を実現する上で原子力の導入を加速する必要があるが、SMR は産業の脱炭素化、経済の活性化に貢献できる」と強調。そして世界の大手テック企業が、低炭素エネルギーによって生成AI(人工知能)やその他の科学イノベーションを推進するためにSMRに注目し、開発途上国にもSMRの利用を検討する国が増えていると指摘。SMRの導入支援の強化に向けてIAEAが開設したSMRプラットフォームを通じて支援及び専門知識を提供するほか、SMR導入には資金調達が極めて重要になることから、国際金融機関に対し、従来型およびSMRのような新型炉への投資を促していると言及した。オープニングセッションでは、ガーナのK. メンサー・エネルギー省次官、米原子力エネルギー協会(NEI)のM. コースニックCEOから基調講演が行われた。会議の開催期間中には、4つの主要テーマ(①SMRの設計、技術、燃料サイクル、②法規制の枠組み、③安全性、セキュリティ、保障措置、④SMRの展開を促進するための考慮事項)に関するパネルディスカッションやポスターセッションが行われ、SMRの可能性について議論した。なお、10月21日、原子力の調和および標準化イニシアチブ(Nuclear Harmonization & Standardization Initiative:NHSI)の第3回年次総会が開催された。IAEAは2022年、先進炉、特にSMRの世界展開には、迅速かつ効率的に、また開発者がスケールメリットを達成するために、標準化された設計が複数の国において認可され、かつ安全に導入されるための各国間の調和された規制アプローチが不可欠であるため、同イニシアチブを創設。同イニシアチブは、規制トラックと産業トラックの別個でありながら補完的な2つのトラック構成により、各国を支援する。前者は、原子力安全と国家主権を損なうことなく、加盟国間の規制協力を強化し、取組みの重複を回避して効率を高め、共通規制の作成を促進することを目標とし、後者は、SMR の開発、製造、建設、運転のより標準化されたアプローチの開発に焦点を当て、認可手続き、コスト、展開の所要時間の短縮を目指している。今回の総会では、各トラックの作業の進捗状況をレビューし、ワーキンググループが提案する多くの推奨事項を実施するという次の段階に移行することとなった。
- 28 Oct 2024
- NEWS
-
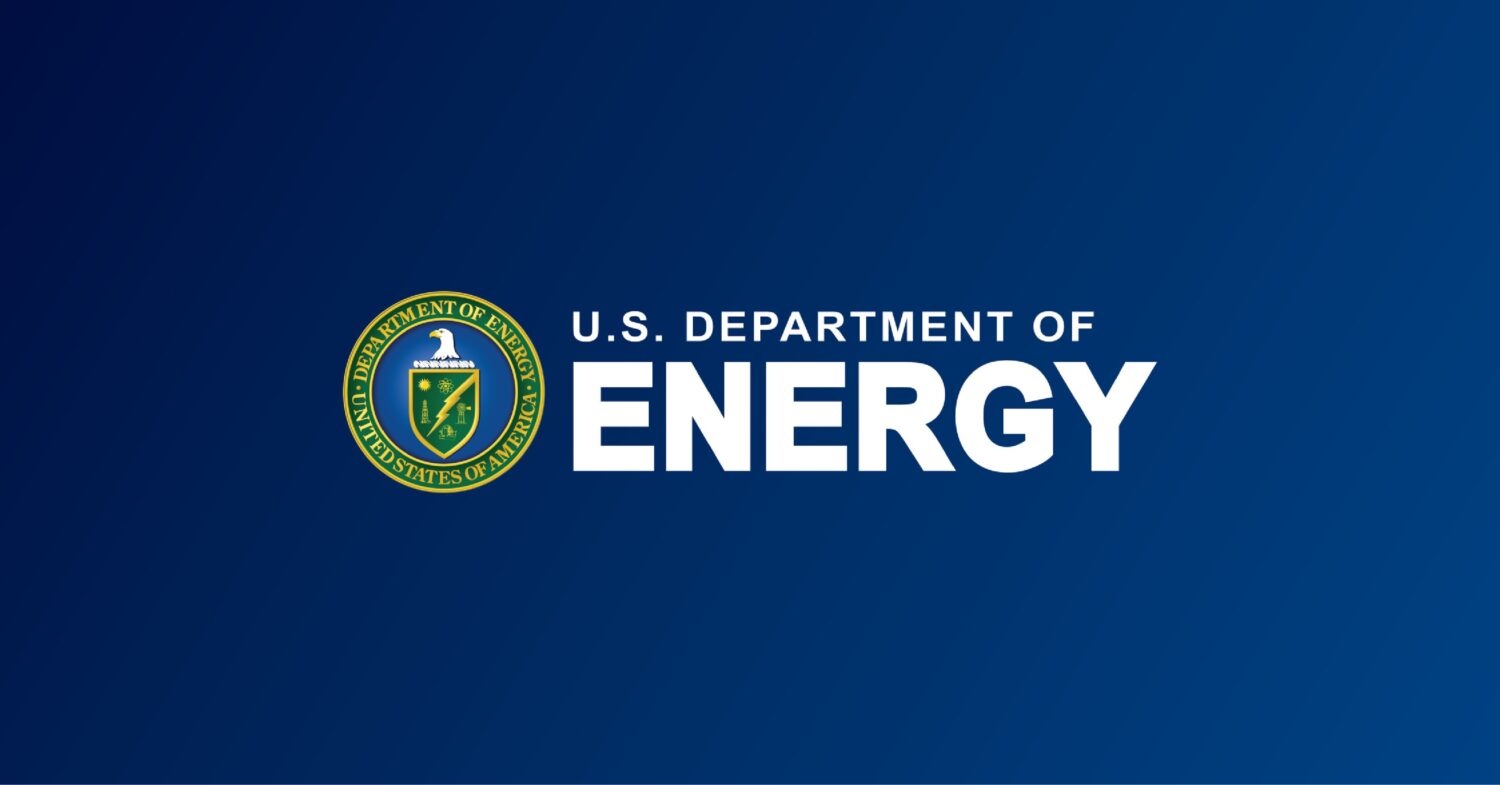
米DOE SMR初期導入に9億ドルを援助
米エネルギー省(DOE)は10月16日、バイデン大統領の「米国への投資(Investing in America)」アジェンダの一環として、第3世代+(プラス)の小型モジュール炉(SMR)の国内初期導入支援を目的とした、最大9億ドル(約1,359億円)の資金提供の申請プロセスを開始した。米国内での先進原子炉の導入促進や産業力強化のほか、後続の原子炉プロジェクトの支援に繋げることが狙い。資金は、2021年11月に成立した「超党派のインフラ投資・雇用法」から、2024年連結歳出法(Consolidated Appropriations Act of 2024)に割り当てられたものを活用する。 DOEによると、資金提供は2つのカテゴリーに分けて実施される。1つ目のカテゴリーとして先陣を切る、ファースト・ムーバー・チーム支援(First Mover Team Support)では、DOEは、同時に複数のSMRの受注促進を目的として、コンソーシアム・アプローチ、すなわち、電気事業者、原子炉ベンダー、建設業者、エンドユーザーなどがチームとして参加することを条件とし、最大2チームを支援する。支援額は最大で8億ドル(約1,208億円)。2つ目のカテゴリー、ファスト・フォロワー・導入支援(Fast Follower Deployment Support)では、設計、許認可申請、サイト準備など、国内原子力産業が直面する課題解決のため、計画中のSMR建設プロジェクトを主導する企業や、SMRのサプライチェーンの強化やコスト改善をめざす組織を支援する。支援額は最大で1億ドル(約151億円)。最新のDOEの「リフトオフ報告書」は、米国の原子力発電設備容量が、2024年の約1億kWから2050年までに約3億kWまで3倍になる可能性があると指摘。また、2050年ネットゼロ達成のためには、少なくとも7億~9億kWの追加のクリーンかつ信頼性の高い発電設備容量が必要としており、原子力は、これを大規模に達成できる数少ない実証済みのオプションの一つであると強調している。中でもSMRは、大型原子炉と比べて、発電コストが割高でも、閉鎖予定の小規模石炭火力発電所や高温熱を必要とする工業プロセスの代替となり得る点や、潜在的な立地、建設、およびコストなどの点で利点を有すると評価されている。今回の支援について、DOEのJ. グランホルム長官は、「米国の原子力部門の活性化は、カーボンフリーなエネルギーの供給量を増加し、AIやデータセンターから製造業、医療に至るまで、成長し続ける経済の需要を満たすためのカギとなる」とその意義を強調している。なお、支援金の申請期限は2025年1月17日まで。
- 25 Oct 2024
- NEWS
-

欧州原子力アライアンス 次期欧州委員会に原子力の貢献を認めるよう勧告
欧州原子力アライアンスは10月15日、次期欧州委員会(EC)((現EC委員の任期は2024年10月31日まで。任期は5年。))に対し2024-2029年の欧州の脱炭素化プログラムにおいて、原子力と再生可能エネルギーの貢献を認めるよう、共同声明を発表した。ECのエネルギー理事会(Energy Council)がルクセンブルクで開催されたのを機に、同アライアンスは会合を開催、声明を発表したもので、会合にはEU加盟14か国と欧州委員会の閣僚や上級代表が出席した。同アライアンスは2023年2月にフランスが中心となり、原子力発電を利用する国々の協力イニシアチブとして発足。現在12か国が加盟、2か国がオブザーバー参加((ブルガリア、クロアチア、チェコ、フィンランド、フランス、ハンガリー、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデンのほか、イタリアとベルギーがオブザーバーとして参加。))し、域内における原子力への支援拡大に向けた働きかけを強めているところ。EUでは現在、総発電電力量に占める原子力の割合は25%で、低炭素電力に占める割合は50%と半分を占めている。共同声明は、世界的な地政学的変動の中で、2024年から2029年までの次期欧州委員会の任務は、欧州経済の競争力と強じん性を確保しながら2050年までの気候中立の達成に向け、技術中立的なアプローチを採用し、あらゆる解決策の活用によって欧州の脱炭素化を追求することである、と指摘。そのうえで、原子力は、再生可能エネルギーと並んで、化石燃料を使用せずに電力の需要増に対応し、気候変動を緩和するためのコスト競争力のある解決策であり、安定したベースロード電源であることから、供給安定性と電力市場において必要な柔軟性の両方を併せ持つ、とその優位性を強調している。また、アライアンスは今年3月、強固な欧州の原子力産業を育成し、発電および非発電用途の核物質、とりわけ原子燃料の供給保証を確保する欧州の枠組みの設定に向けて、以下に掲げる4つの行動の柱を提示したことを紹介。これら4つの柱に関して、アライアンス内や志を同じくする他のEU加盟国及び欧州委員会との協力を強化すると表明している。大型炉、小型モジュール炉(SMR)および関連する欧州のバリューチェーンを支援するための民間および公的資金へのアクセスの拡大、欧州の資金調達手段の可能性と利点の追求すべての民生用原子力利用のため、熟練した多様な原子力労働力の開発具体的なプロジェクトを通じた、欧州のバリューチェーン全体での産業、研究、イノベーションの連携の拡大エネルギーミックスの脱炭素化に関する全ての加盟国の選択を尊重、結束の強化共同声明では、「既存及び新規の原子力発電所のメリットは、原子力を選択する加盟国の国境を越える。水力や原子力のような低炭素ベースロードのエネルギーは、我々の共通グリッド及び欧州電力市場全体を安定させ、原子力発電および再生可能エネルギーは、欧州連合にとって真の共有資産」と原子力の価値を改めて強調。さらに、「原子力発電は、そのベースロード特性と低い運転コストにより、市場環境の変動が少ない。このようなエネルギーがなければ、EUが2050年までにネットゼロを達成しつつ、市民に手頃な価格で信頼性があり、豊富な低炭素エネルギーを提供する道はない」と明言した。これらをふまえ、アライアンスは、次期欧州委員会に対し、統合エネルギーシステムの将来に向け、技術中立的なアプローチを採用して、再生可能エネルギーとともに原子力の役割を十分に認識し、エネルギー政策のパラダイムシフトの実現を勧告している。
- 24 Oct 2024
- NEWS
-

スロバキア SMR導入で米国から新たに助成金
スロバキアは10月8日、米政府の原子力エネルギー移行促進(NEXT)プログラムから小型モジュール炉(SMR)の建設に適したサイト選定を包括的に支援する、500万ドル(約7.5億円)の助成金を獲得したことを明らかにした。これにより2025年末までにサイト選定を完了させる。米国のJ. ケリー元・米気候問題担当大統領特使が立ち上げたNEXTプログラムは、SMR導入間近のパートナー諸国への技術支援が目的。今回の助成金は昨年、米国が主導する石炭火力発電所からSMRによる原子力への転換プログラムである「プロジェクト・フェニックス(Project Phoenix)」下で、石炭火力発電所跡地でのSMRの実行可能性調査(F/S)の実施に向けた200万ドル(約3億円)の助成金授与に続くものだ。プロジェクト・フェニックスとNEXTプログラムは、米国務省の「SMRの責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラムのサブプログラムの位置づけである。本助成金は、スロバキアの大手原子力事業者であるスロバキア電力のほか、スロバキア経済省、スロバキア工科大学、スロバキア原子力規制庁、スロバキア電力・送電システム社、エンジニアリング会社のVUJE、U.S. Steel Košice(在スロバキアの米製鉄企業)が国際入札に共同参加して獲得。NEXTプログラムは、SMR建設のための意思決定と、その実施のための能力開発に係わる活動を支援する。支援される具体的なプロジェクトは、SMRの技術的・規制的要件に関するコンサルティング、大学や原子力施設との協力、SMR導入戦略の策定など。スロバキア電力によると、2025年までにSMRの実行可能性調査(F/S)を終え、2029年までに環境影響評価(EIA)を含むSMRの初期設計と許認可手続きを完了、2035年の運転開始を目指している。既に米国務省の選定によって技術、コンサルティング支援を行う米エンジニアリング企業のサージェント&ランディ(Sargent & Lundy, L.L.C)社のスタッフがスロバキアを訪問し、F/S実施に向けた初期の現地調査を実施している。スロバキア電力のB. ストリチェクCEOは、電力需要が増大する中、SMRはスロバキアの電力需要の大部分をカバーする既存の原子力発電所をリプレースできるものではないものの、エネルギーミックスを補完し、エネルギーセキュリティを高めるものだと強調した。スロバキア電力の所有設備は、2023年のスロバキアの総発電電力量の70%以上を賄っている。ボフニチェ(3、4号機、各VVER-440)とモホフチェ(1、2号機、各VVER-440)の両発電所の他、31の水力発電所を稼働させている。2024年3月には石炭火力発電所をすべて閉鎖し、脱炭素電源100%を達成した。なお、モホフチェ発電所では追加の2基(3、4号機、各VVER-440)を建設中で、3号機は2023年1月に送電を開始した。スロバキア政府はまた、今年5月にボフニチェ発電所5号機(最大120万kWe)の新設を承認した。
- 22 Oct 2024
- NEWS
-

WEO2024「原子力はクリーンエネルギー移行に不可欠」
国際エネルギー機関(IEA)は10月16日、最新の年次報告書の「ワールド・エナジー・アウトルック(WEO)2024年版」を公表。原子力の拡大を予測するとともに、クリーンエネルギーへの移行を加速・拡大するためには、より強力な政策と大規模投資の必要性が高まっていると指摘した。報告書によると、地政学的緊張が続く一方で、2020年代後半に石油と天然ガスが供給過剰となり、太陽光や蓄電池など、主要なクリーンエネルギー技術の製造能力も大幅過剰となるとの見通しを示し、これまでとは異なる新たなエネルギーの市場環境になると予測。燃料価格の圧力から解放され、クリーンエネルギーへの移行に対する投資強化と非効率な化石燃料補助金の撤廃に取り組む余地が生まれることにより、政府や消費者による選択が、今後のエネルギー部門と気候変動に対する取組みに大きな影響を及ぼすとの見方を示した。WEOは、世界のエネルギー・ミックスに関する2050年までの見通しを次の3通りのシナリオで解説している。現行のエネルギー政策に基づく「公表政策シナリオ」(STEPS)各国政府の誓約目標が期限内に完全に達成されることを想定した「発表誓約シナリオ」(APS)2050年ネットゼロ目標を達成する「2050年実質ゼロ排出量シナリオ」(NZE)報告書は、STEPSでは、2030年までに世界の電力の半分以上を低炭素電源がまかない、石炭、石油、天然ガスの需要はいずれも同時期にはピークを迎えると分析。一方で、クリーンエネルギーへの移行は急ピッチで展開されつつあるものの、世界の平均気温の上昇を産業革命以前との比較で1.5℃以下に抑えるというパリ協定の目標達成は難しいと警告している。また、過去10年間の電力消費量は総エネルギー需要の2倍のペースで増加しており、今後も世界の電力需要の伸びはさらに加速するとし、STEPSでは、毎年日本の電力需要と同規模の電力量が追加され、NZEでは、さらに急速に増加する。F. ビロルIEA事務局長は、「エネルギーの歴史は、石炭、石油の時代から、今や急速に電気の時代へと移行している」との認識を示している。さらに、クリーンエネルギーが今後も急速に成長し続けるためには、とりわけ、電力網とエネルギー貯蔵への投資を大幅に増やす必要があると指摘。現在、再生可能エネルギーなどに不可欠な支援インフラがクリーンエネルギーへの移行に追いついていない現状を問題視したうえで、電力部門の確実な脱炭素化には、これらへの投資を増やす必要性を強調している。世界の電力供給と原子力再エネに代表される低炭素電源は、すべてのシナリオで電力需要よりも速いペース(出力ベース)で増加し、それに伴い化石燃料の発電シェアは低下。2023年には、再エネの発電シェアは前年同数の30%だったが、化石燃料の発電シェアは60%(2022年: 61%)に減少し、過去50年間で最低となった。STEPSでは、2035年までに太陽光と風力の発電シェアは世界で40%を超え、2050年には60%近くまで増加する。一方、原子力の発電シェアは、どのシナリオでも10%近くにとどまる見通し。原子力について、報告書は、手頃な価格で確実なクリーンエネルギー移行の鍵となる7つの技術(太陽光、風力、原子力、電気自動車、ヒートポンプ、水素、炭素回収)のうちの一つであると指摘。これらの技術は、APSとNZEでは、2050年までのCO2排出削減量の4分の3を占める一方で、電力網や貯蔵インフラなど、これらの導入に対する障壁を克服することが最優先事項と強調した。原子力の現状についてIEAは、COP28での「原子力3倍化」宣言、欧州を中心とした原子力回帰の動きを受け、「原子力発電に対する政策支援が高まっている」と指摘。原子力発電設備容量と発電電力量はともに、他の低炭素電源よりも遅いペースではあるものの、いずれのシナリオにおいて拡大すると予測した。具体的には、世界全体で2023年に4億1,600万kWだった原子力の発電設備容量が、2050年にはSTEPSで6億4,700万kWに、APSで8億7,400万kWに、NZEでは10億1,700万kWにそれぞれ拡大すると予測しており、この拡大には、主に中国、その他の新興市場や開発途上国における開発が貢献すると分析したほか、いずれのシナリオでも、中国が2030年頃までに原子力発電規模において世界第1位になるとの見通しを示した。また、現在、世界各国が開発にしのぎを削る小型モジュール炉(SMR)については、適切なコストで市場投入に成功すれば、世界市場で原子力発電の新たな機会を創出する可能性があると分析した。すでにSMRが稼働している中国とロシア以外では、2030年頃に最初のプロジェクトが運転を開始すると予想している。
- 21 Oct 2024
- NEWS
-

Amazon SMRプロジェクトを支援
米大手テック企業のAmazon社は10月16日、米X-エナジー社が開発する小型モジュー炉(SMR)の商業化に向けて、約5億ドル(約750億円)を出資すると発表した。主に、同社の気候変動対策に関する誓約のための基金(Climate Pledge Fund)から拠出する。今回の出資には、多国籍ヘッジファンドCitadel社、オルタナティブ投資会社Ares Management社、エネルギーに特化した未公開株式投資会社NGP社、ミシガン大学も参加する。同基金は2020年、Amazon社が20億ドル(約3,000億円)を投じて設立。2040年までに同社事業の温室効果ガス排出量を実質ゼロとするために、持続可能な技術やサービス開発を支援している。Amazon社は電力需要が拡大し続ける中、再生可能エネルギーへの投資を継続するとともに、新たな電源としてカーボンフリーで規模の拡大が柔軟な原子力発電に着目。とりわけ、設置面積が小さく、送電による逸失を最小限にするためにデータセンターなどのサービス施設の近傍に設置可能で、建設期間が短いSMRを活用する考えだ。両社は今回の出資により、2039年までに米国内で合計500万kWe以上のX-エナジー社製SMRの稼働を目指す。Amazon社は自社のデータセンター事業を支えるため、SMR建設プロジェクトへの直接投資と長期の電力購入契約(PPA)を通じて、増大する電力需要に対応する考えだ。さらに両社は、SMR導入と資金調達のモデルを確立することで、標準化させることを狙っている。X-エナジー社への具体的な支援策としてAmazon社は、SMR設計や機器製造、許認可取得活動、およびテネシー州オークリッジのTRISO(3重被覆層・燃料粒子)燃料製造施設の第一期の完成作業のほか、ワシントン州の電気事業者であるエナジー・ノースウェスト社のX-エナジー社製SMR×4基による合計32万kWeの建設プロジェクトに直接資金を投入。12基、合計96万kWeへの拡張も視野に入れる。Amazon社は、原子力発電への投資はその拠点となる地域社会に雇用などの経済的効果をもたらすと指摘している。X-エナジー社製SMRは「Xe-100」と呼ばれる電気出力8万kWの小型高温ガス炉で、TRISO燃料を使用。連結して32万~96万kWの発電容量への拡張が可能。米エネルギー省(DOE)が2020年、先進的原子炉実証プログラム(ARDP)で5~7年以内に実証(運転)を目指し、支援対象に選定した二つの設計のうちの一つである。X-エナジー社は、米・大手化学メーカーであるダウ・ケミカル社のテキサス州メキシコ湾沿いに位置するシードリフトの製造施設で、Xe-100を4基連結させた発電所の建設を計画。エナジー・ノースウェスト社とは2023年、同社のコロンビア原子力発電所(BWR、121.1万kW)の隣接地でXe-100を採用した発電所を建設する共同開発合意書を締結している。またAmazon社はドミニオン・エナジー社と、同社がバ―ジニア州で所有・運転するノースアナ原子力発電所(PWR、100万kW級×2基)の近傍に、少なくとも30万kWeのSMR設置を検討する契約を締結したことを明らかにした。ドミニオン社は今年7月、将来的なエネルギー需要を見据え、同発電所でのSMR導入の実現可能性を評価するため、SMR開発企業を対象に「提案依頼書(RFP)」を発行している。バージニア州には米マイクロソフト社、米アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)社をはじめ、世界の巨大データセンターのうち、約35%にあたる約150施設が立地している。ドミニオン社の予測によると、バージニア州の電力需要は毎年5%以上増加しており、今後15年間で倍増するという。生成AI(人工知能)の普及により、データセンターの電力消費量が急増する中、大手テック企業では、再生可能エネルギーへの投資とともに、信頼性の高い原子力の活用を進める動きが活発化している。米マイクロソフト社は今年9月、大手電力会社のコンステレーション・エナジー社と閉鎖済みのスリーマイル・アイランド(TMI)1号機(PWR、89万kWe)を再稼働させ、マイクロソフト社のデータセンターに電力を供給する、20年間の売電契約の締結を発表。また同機と同じくペンシルベニア州にあるサスケハナ原子力発電所(BWR、133.0万kW×2基)に隣接するデータセンターを今年3月、米Amazon傘下のAWS社が買収した。10月14日には、Google社と米原子力新興企業のケイロス・パワー社が2035年までに複数の先進炉導入による電力購入契約(PPA)を締結したばかり。
- 18 Oct 2024
- NEWS
-

フィンランド 新たなSMR建設計画が始動
フィンランドのステディ・エナジー(Steady Energy)社は10月12日、フィンランドのケラヴァ市が保有するエネルギー企業のケラヴァン・エネルギア(Keravan Energia)社と、ケラヴァ市での小型モジュール炉(SMR)を使用した地域熱供給に関する協定を締結した。早ければSMRの建設を2029年から行い、地域熱供給を2032年に開始する見込み。 ステディ社は2023年にフィンランド国営のVTT技術研究センターからスピンオフした、SMR開発を行うスタートアップ企業で、フィンランド国内では既にクオピオ市、ヘルシンキ市で同様の取り組みを進めている。 ケラヴァン社は、2030年までのカーボンニュートラル達成を企業理念として掲げており、現在の地域熱供給にはバイオマス燃料と泥炭が燃料として使用されている。同社のJ. レトCEOは「電力価格の変動に対抗するには、より安定した電源が必要である。ステディ社が開発するSMRは非常に現実的な選択肢だ」と強調した。 今後、SMRの立地適性および技術的・経済的実現可能性の評価、規制当局による許認可手続きなどが行われる見込み。 建設が予定されているSMRは、これまでの2都市と同様にステディ社の「LDR-50」(5万kWt)で、コストは約1億ユーロ(約162億円)と見積もられている。LDR-50は熱供給専用で、最大150℃の熱を発生させる。地域暖房以外にも産業用蒸気や海水淡水化での利用を視野に入れている。高さは約10mで、地下に建設される。 ステディ社は来年、LDR-50の機能性などの検証を目的に、LDR-50のパイロットプラント(電気加熱式)をフィンランド国内に建設予定で、建設コストは1,500万~2,000万ユーロ(約24~32億円)。建設候補地としてはヘルシンキ市、クオピオ市、エスポー市、ラハティ市が挙げられている。
- 17 Oct 2024
- NEWS
-

欧州SMR産業アライアンス 初支援のSMRを選定
欧州委員会(EC)は10月11日、今年2月に立ち上げた「欧州SMR産業アライアンス(European Industrial Alliance on SMRs)」による初回の支援対象として9件のSMRプロジェクトを選定したことを明らかにした。同アライアンスは、欧州域内での2030年代初頭までの小型モジュール炉(SMR)の導入加速と、熟練労働力の確保など堅固なSMRサプライチェーン確立を目的に今年2月に発足。SMR開発会社、電力会社、エネルギー集約型企業、サプライチェーン企業、研究機関、金融機関など300以上の組織が加入する。アライアンスは6月、具体的なプロジェクトの成果をあげるべく、アライアンスのプロジェクト・ワーキング・グループ(PWG)への参加を希望するSMRプロジェクトの募集を開始。その後、寄せられた22件の申請について審査と評価を行い、初回の支援対象となる9件のプロジェクトを選定した。プロジェクト提案の評価にあたっては、実現可能性は考慮していないという。10月7日の理事会で選定された9件のSMRプロジェクトは以下の通り。EU-SMR-LFR project(伊・Ansaldo Nucleare, ベルギー・SCK-CEN, 伊・ENEA, ルーマニア・RATEN)CityHeat project(仏・Calogena, フィンランド・Steady Energy)Project Quantum(米・Last Energy)European LFR AS Project(英・Newcleo)Nuward(仏・EDF)European BWRX-300 SMR (ポーランド・OSGE)Rolls-Royce SMR(英・Rolls-Royce SMR Ltd)NuScale VOYGR SMR (ルーマニア・RoPower Nuclear SA)Thorizon One project (蘭・Thorizon)PWGは5月下旬の総会にて設置が決定した8つの技術作業部会(TWG:①産業への応用、②技術および研究・開発・イノベーション、③サプライチェーン、④労働者の技能、⑤パブリック・エンゲージメント、⑥原子力安全と保障措置、⑦燃料サイクルと廃棄物管理、⑧ファイナンス)から、特定のニーズに応じて支援を受ける。各プロジェクトとの協力に関心のあるステークホルダーもPWGに参加することができる。なお、アライアンスから資金提供の支援はない。今回支援対象に選定されなかったプロジェクトに対しては、主な改善点の概要が示されており、2025年第2四半期に予定される第2回目の選考時に再申請が可能となっている。
- 16 Oct 2024
- NEWS
-

ルーマニア SMR建設プロジェクトに米輸出入銀行が融資承認
米輸出入銀行(US EXIM)は10月1日、ルーマニア南部ドゥンボビツァ県のドイチェシュテイ(Doicesti)で計画されている小型モジュール炉(SMR)建設プロジェクトに対し、9,800万ドル(約145億円)の融資を承認した。 ルーマニアは現在、ドイチェシュテイで13年前に閉鎖された旧・石炭火力発電所サイトに、米ニュースケール・パワー社製SMRである出力7.7万kWeの「ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)」を6基備えた「VOYGR-6」(合計出力46.2万kWe)の建設を計画している。プロジェクトは、ルーマニアの国営原子力発電会社であるニュークリアエレクトリカ(SNN)と民間エネルギー企業のノバ・パワー&ガス社の合弁企業であるロパワー・ニュークリア(RoPower Nuclear)社を中心に進められており、そのほか、大手EPC(設計・調達・建設)企業であり、ニュースケール社の大株主でもある米フルアー(Fluor)社、韓サムスンC&T社(サムスン物産)、米サージェント&ランディ(Sargent & Lundy)社も参画している。フルアー社は現在、7月にロパワー社と締結した同プロジェクトの基本設計の第2段階(Front-End Engineering and Design:FEED2)契約に基づき、作業を進めている。今後、同社は、プロジェクト実施に必要な設計・エンジニアリングサービスに加えて、最終投資決定に必要な安全・セキュリティ分析、最新のコスト試算、スケジュールを提供するとしている。今回のプロジェクトでは、約200名の正規雇用のほか、建設段階で1,500名、製造・部品組立で2,300名の雇用を創出するという。2029年の運転開始を目指しており、運転期間は60年、その間にも運転・保守に係る雇用がさらに創出される見込み。なお、ルーマニアのエネルギー省は、SMR初号機建設費用を現段階で49億ドル(約7,300億円)と試算している。ルーマニアのSMR建設をめぐっては、2023年5月、米国、日本、韓国、およびUAEの官民パートナーが、同プロジェクトに共同で最大2億7,500万ドル(約408億円)の支援の提供を発表しており、今回の融資はその一部と見られている。さらに、2024年3月にもUS EXIMと米国際開発金融公社(US DFC)は同プロジェクトに対して計40億ドル(約5,900億円)の融資を行うと発表するなど、米政府が後押ししている。ルーマニア政府は8月23日、「2050年を見据えたルーマニアのエネルギー戦略2025~2035年」を発表し、その中で化石燃料から再生可能エネルギーおよび低炭素エネルギー源への段階的な移行の必要性を強調。また、9月19~20日にフランスで開催された経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)による第2回「新しい原子力へのロードマップ」会議には、S.ブルドゥジャ・エネルギー大臣が出席し、ルーマニアが原子力分野において技術、教育面などから先進的な取組みを行っているとしたうえで、欧州のエネルギー転換において中心的な役割を果たすべく、原子力推進・拡大に向けて引き続き積極的に取り組んでいく姿勢を改めて示した。ルーマニアでは、1996年、2007年にそれぞれ運転開始したチェルナボーダ1,2号機(CANDU 6×2基)が運転中で、総発電電力量に占める原子力シェアは約20%(2023年実績)。1号機は、2061年までの運転が認可されている。建設中断中の同3,4号機(CANDU 6×2基)は、米加両政府などの支援を受けて、建設再開に向けた準備が進められている。
- 11 Oct 2024
- NEWS
-

英SMRコンペ 4社が最終選考へ
英国の大英原子力(GBN)は9月25日、小型モジュール炉(SMR)支援対象選定コンペで4社が選考に残ったことを明らかにした。今後、4社は最終選考に入る。最終選考に残った4社は、米GE日立・ニュクリアエナジー・インターナショナル社、米ホルテック・インターナショナル社英法人、英ロールス・ロイスSMR社、米ウェスチングハウス(WE)社英法人。米ニュースケール社は選外となった。英政府は原子力発電設備容量を、2050年までに2,400万kWまで拡大する計画を発表しており、SMR導入も謳われている。英国の原子力発電所新設の牽引役として2023年7月に発足した政府機関のGBNはSMRの支援対象選定コンペを開始。同年10月には関心表明をした6社が入札に招待され、今年7月の締切までに辞退した仏EDF社を除く5社が入札書類を提出した。なお、GBNは今年3月、最終選考では今年後半までに2社を選ぶと発表している。当初、今年夏には選定企業との契約締結を計画していたが、遅延している。最終的に選定された企業はGBNからSMRへのサイトを割当てられ、技術開発の資金を獲得する。英政府は2029年にSMRへの最終投資決定を行い、2030年代半ばには運転を開始したい考えだ。
- 27 Sep 2024
- NEWS
-

フィンランド SMR導入プログラムが始動
フィンランドのヘルシンキ市が保有するエネルギー企業のヘレン(Helen)社は9月9日、ヘルシンキ市に熱供給を行う小型モジュール炉(SMR)を導入するプログラムを立ち上げたことを明らかにした。同社は、プログラムの第一段階でビジネスモデルを確立、SMRの炉型および供給者、建設候補サイトを決定する。この第一段階は、2026年に完了を予定している。ヘレン社は、2030年までに地域熱供給における化石燃料を利用停止する目標を掲げている。同社の地域熱供給ネットワークは全長1,400kmに及び、北欧諸国の中で最大規模。このネットワーク全体の脱炭素化のため、ネットワークの近くに設置可能な、安定した信頼性の高い、電力に依存しない熱源が必要であり、同社は実証済みの技術による、熱のみ、または電気と熱の両方を生産するSMRを導入する計画である。なお、同社は石炭火力発電所を来春までに全廃予定であり、バイオエネルギーやヒートポンプ、電気ボイラーによる熱供給では不十分であるため、新たな熱源の導入が急務となっている。ヘレン社のO. シルッカCEOは、「順調に進めば、2030年代初頭までにヘルシンキに熱供給するSMR初号機が完成する。石炭火力発電の代替は、現実的には原子力発電が唯一の選択肢。地域熱供給の半分を原子力発電、半分を電気でまかなうのが最適であり、太陽光発電や風力発電にも多額の投資を行っている」と述べる一方で、「SMRの規制が厳しくなり、地域熱供給ネットワークと接続するSMRを建設できなくなると、地域暖房の価格が上昇する」との懸念を示した。なお、シルッカCEOによると、ヘレン社は2023年10月にフィンランドの熱供給用SMRの商業化を目的に設立されたスタートアップ企業のステディ・エナジー(Steady Energy)社と同社製SMR活用に関する基本合意書を交わしているが、実現可能性のあるすべてのSMRを検討していくという。ステディー社が開発する熱供給専用のSMR「LDR-50」(5万kWt)については、フィンランドの原子力規制当局(STUK)が8月末に、ステディ社からLDR-50の予備的な安全性評価の実施を要請されたことを明らかにした。STUKは、原子力法による許認可手続きとは別に、安全要件を満たしているかどうかを評価する。なお、ステディ社は、地域暖房用の原子力発電所の建設について、フィンランドのクオピオン・エネルギア(Kuopion Energia)社と今年7月、事前準備の実施で合意している。
- 24 Sep 2024
- NEWS
-

ガーナ 米製SMRを1基導入へ
ガーナの原子力発電公社(NPG)は8月29日、米国のレグナム・テクノロジー・グループと、ガーナに米ニュースケール社製の小型モジュール炉(SMR)「VOYGR-12」を1基建設することで合意した。「VOYGR-12」は、ニュースケール・パワー・モジュール(NPM)を12基組み合わせた発電プラント。レグナム社は、ニュースケール社などと提携する原子力プロジェクト開発会社で、近くNPG社とガーナで「VOYGR-12」を所有/運転する子会社を設立する計画だ。契約は、ケニアの首都ナイロビ市で開催された米・アフリカ原子力エネルギーサミットの会期中に締結された。同サミットは、米エネルギー省(DOE)が主催。原子力導入に向けたアフリカ産業界の準備事項に焦点を当て、原子力サプライチェーン、能力開発、ステークホルダーの参加、資金調達などのテーマで討議された。昨年11月、ガーナで開催された初回に引き続き、2回目となる。同サミットに出席した米国務省(DOS)のB. ジェンキンス軍備管理・国際安全保障担当次官は、「今回の契約締結により、ガーナはアフリカにおけるSMR建設のリーダーとなり、地域の経済発展と雇用創出の起爆剤となる」と指摘。米DOEのA. ダンカン国際協力次官補代理は、「ガーナをはじめとする多くのアフリカ諸国が、経済発展、エネルギー安全保障、脱炭素化の目標達成のために原子力導入を目指している。米国がノウハウとリソースを提供する、強力かつ積極的なパートナーであり続け、アフリカ大陸全体への原子力導入を成功させたい」と抱負を語った。米DOEは2014年以来、NPMを複数設置したVOYGRシリーズの設計および許認可取得への支援に、5.79億ドル(約830億円)以上を投じてきた。5万kWeのNPMは、米原子力規制委員会(NRC)から唯一、設計認証(DC)を取得しているSMR。ニュースケール社は2023年1月、出力を7.7万kWeまで引上げたNPMの標準設計承認(SDA)を申請し、NRCが現在審査中である。米DOSは、今年5月にガーナで開催された、アフリカ原子力ビジネスプラットフォーム会合で、ガーナをSMRの地域ハブとすることを含む、新たな民生用原子力協力を発表している。DOSが主導する「SMRの責任ある利用のための基礎インフラ(FIRST)」プログラムなどの能力開発イニシアチブを通じ、ガーナをアフリカにおける最初のSMRの運転者とし、将来のSMRサプライチェーンのニーズを支える人材育成と雇用創出を支援していく考えだ。なお、ケニアのエネルギー・石油省のA.ワチラ筆頭次官は、同サミットでのスピーチの中で、2034年までにケニア初の原子力発電所を、2030年までに研究炉を完成させる目標を再確認した。米DOEは、次回のサミットを2025年7月にルワンダで開催、特にSMRに焦点を当てる予定だという。
- 10 Sep 2024
- NEWS
-

スロベニア 国民投票前に国民理解を促進
国営スロベニア電力(GENエネルギア)は8月28日の月例記者会見で、クルスコ原子力発電所の増設計画(JEK2プロジェクト)について今年後半に実施される国民投票の決定に先立ち、同プロジェクトに係る調査結果を公開した。JEK2プロジェクトは、クルスコ発電所(PWR、72.7万kW×1基)に最大240万kWeまたは2基を増設する計画。GENエネルギアは、国民投票前にJEK2プロジェクトについて広く国民の意識を高め、必要な情報を提供する方針の一環として、主要な調査結果を公開している。5月に示したJEK2の経済性評価に引き続き、今回、洪水危険性の分析、原子燃料輸入に関連する財務・安全リスクの評価、およびJEK2から発生する放射性廃棄物と使用済み燃料の管理に関する調査結果を公開した。国民投票前に設定されたスケジュールに従い、他の調査結果も順次公開する予定である。洪水危険性の調査の結果、想定される最大水位より低い洪水はJEK2の建設計画地に脅威を与えないが、1万年に一度の洪水を想定した再評価を実施すると強調。原子燃料の輸入に関連する財務および供給リスクの評価については、電力コストに占める燃料費の割合が、原子燃料の方が化石燃料よりもはるかに小さいことに加え、原子燃料の供給はユーラトムへの加盟によって保証されていると指摘した。放射性廃棄物と使用済み燃料の管理については、JEK2の運転時までには既存の技術や経験に基づき、処分・管理施設は完成しているが、相応の増強が必要になると説明している。また、JEK2プロジェクトにSMRを導入する可能性についての調査結果も報告。同プロジェクトの予想スケジュールとSMR開発状況の比較分析により、どのSMRもいまだ初号機リスクが高く、SMRの導入は小国のスロベニアにとって、時間的にもコスト的にもリスクがあるため適切ではないが、今後のSMRの開発の進展状況を注視していく考えを示した。なお、チェコのドコバニ、テメリンの両原子力発電所の増設計画で、韓国水力・原子力会社(KHNP)を優先交渉者に選定したチェコ政府の7月の決定についても概説。KHNPによるドコバニ発電所(5、6号機)へのAPR1000の建設提案で、総事業費の予想額は1基あたり79億ユーロ(約1.26兆円)であったが、5月のJEK2の経済性評価では、同規模の原子炉1基あたり約93億ユーロ(約1.48兆円)であったことを踏まえ、経済的仮定を再検証する国際的なレビューが進行中であると言及した。また、一般市民を対象とし、同プロジェクトやエネルギーに関する対話型の巡回プレゼンテーションを継続的に実施しており、9月末までに国内のさらに10か所で開催する計画だ。なお、JEK2プロジェクトの最終投資決定(FID)は2028年、着工は2032年、運開は2040年直前を予定している。スロベニアでは現在、クルスコ原子力発電所が1983年1月に営業運転を開始して以来、同国の総発電電力量の約40%を供給している。同発電所はGENエネルギアと隣国クロアチアの国営電力会社のHrvatska elektroprivreda(HEP)が共同所有。スロベニアの電力需要は、2050年までに倍増することが予想されているが、2033年以降は総発電電力量の約3分の1を供給する火力発電所を閉鎖する計画だ。2043年にはクルスコ発電所の運転期間(60年)も満了する。
- 06 Sep 2024
- NEWS




